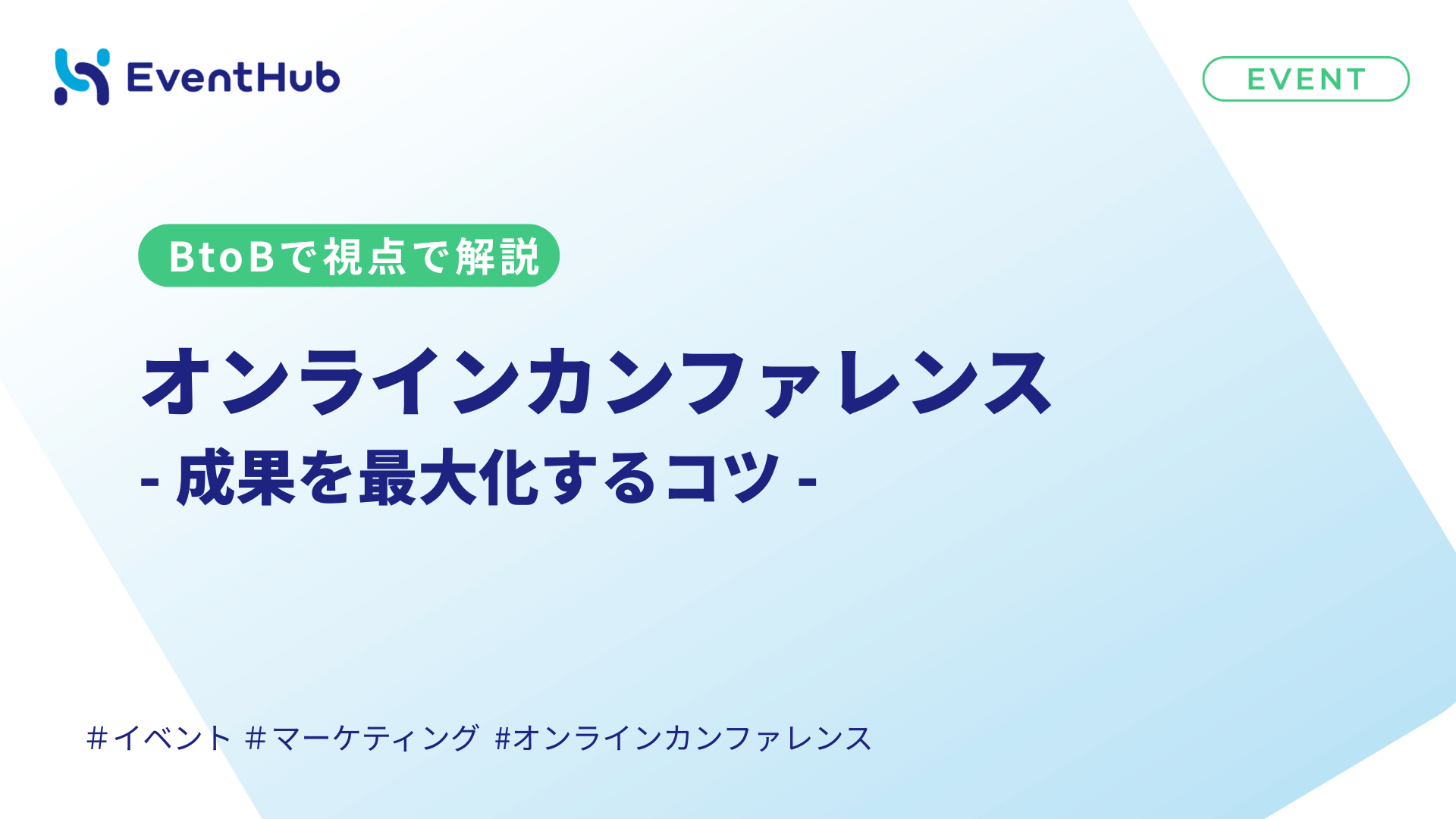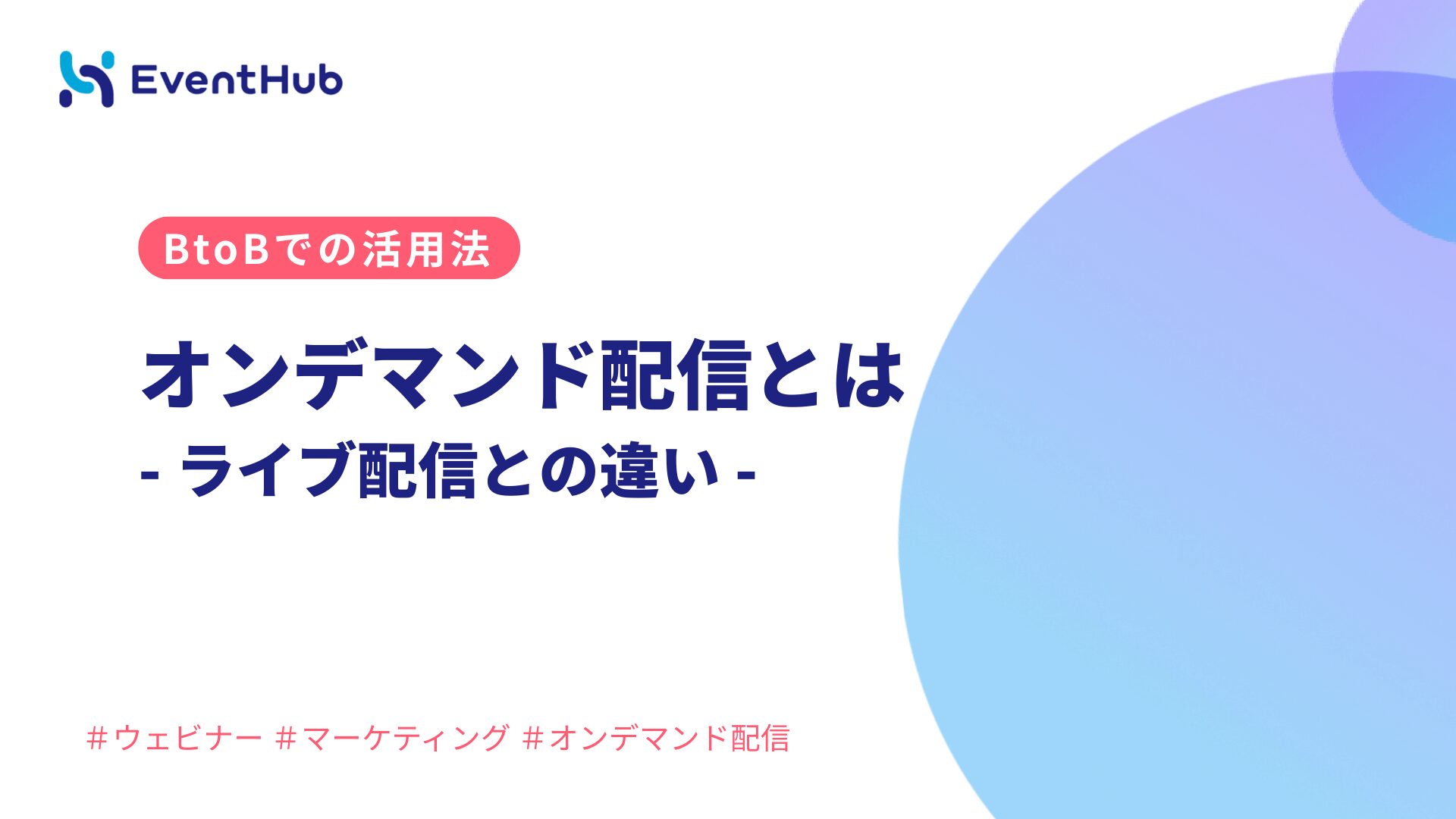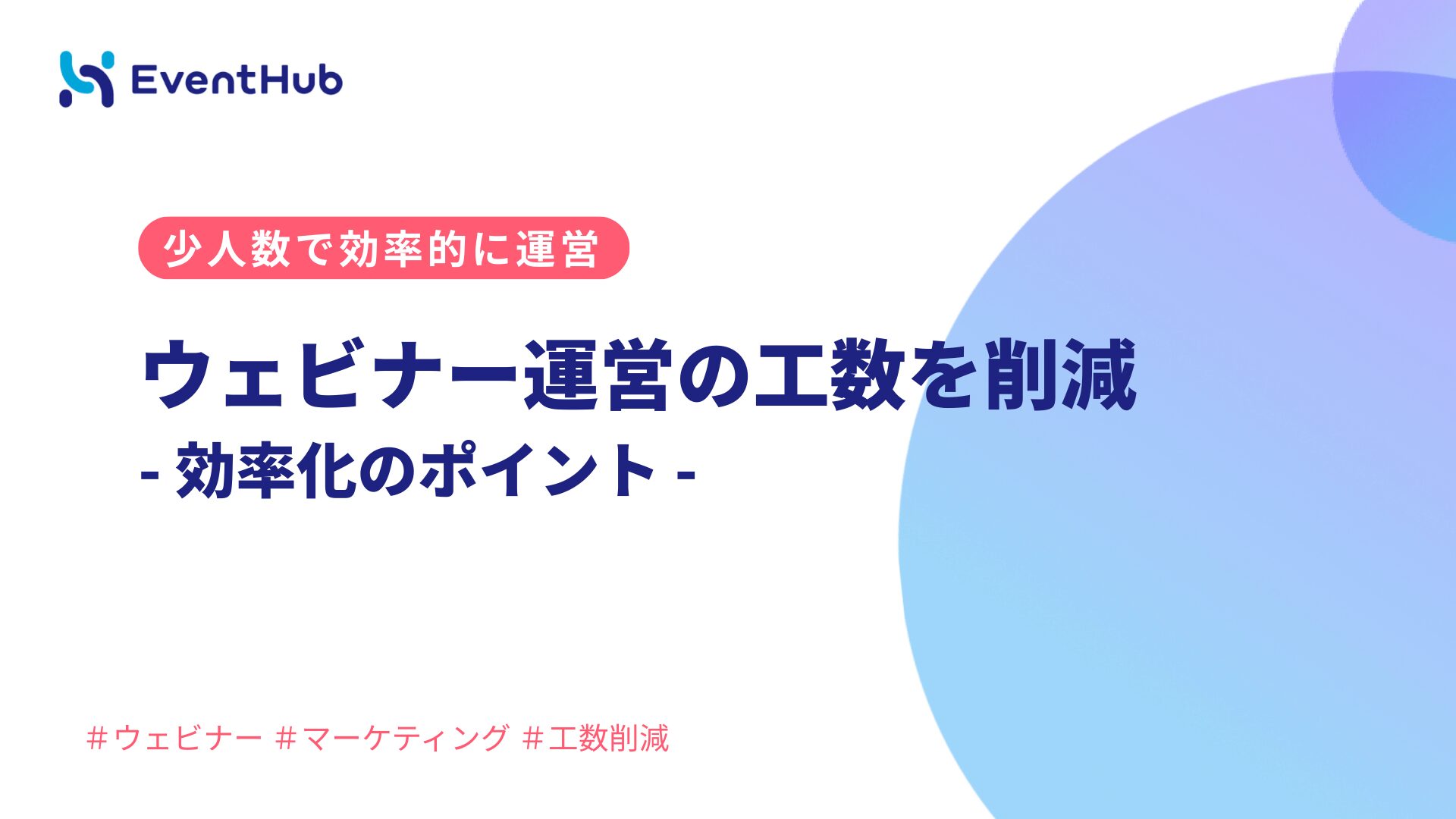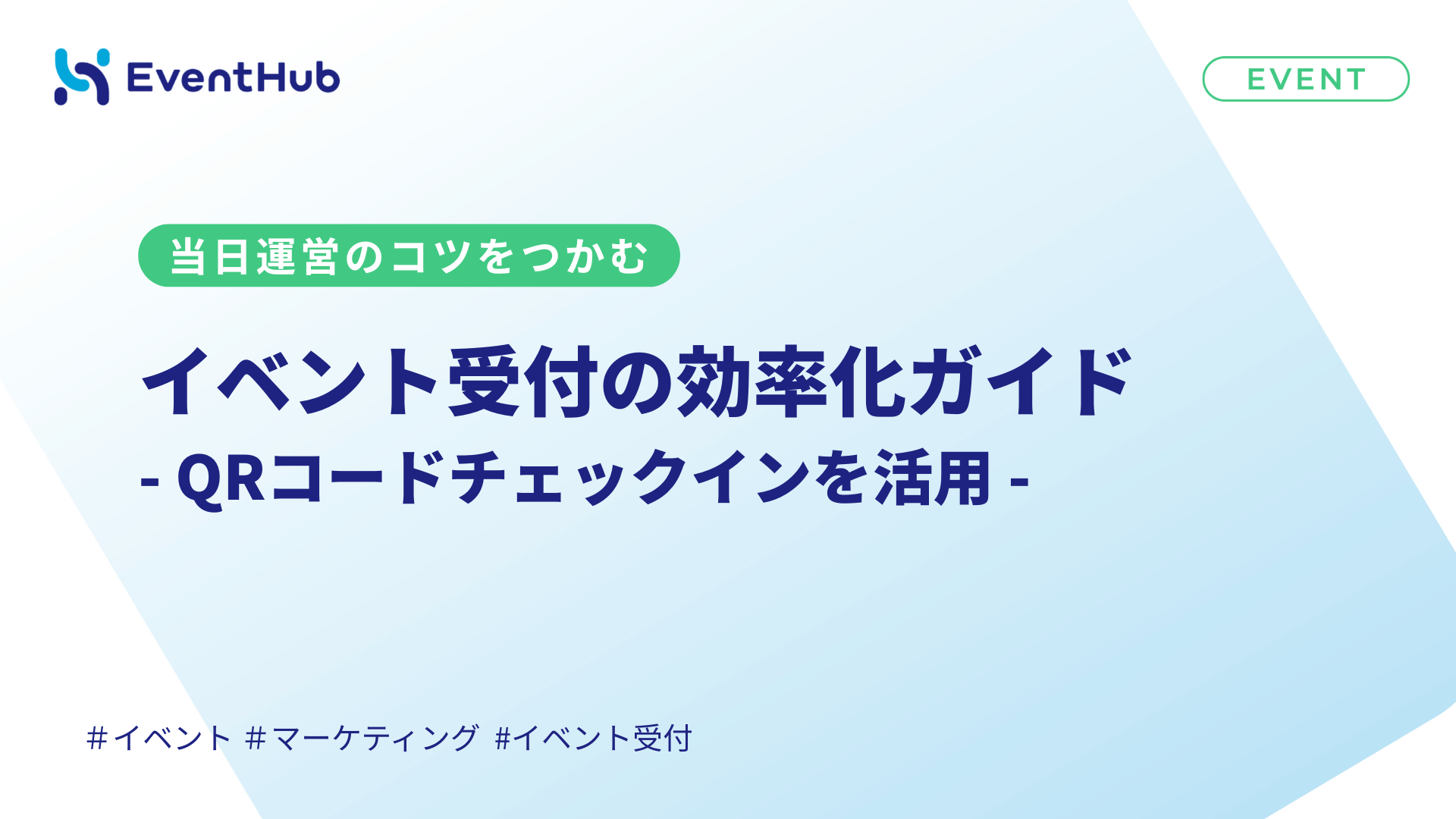イベント管理システムとは?導入する前に理解したい機能と比較軸【チェックリスト付き】
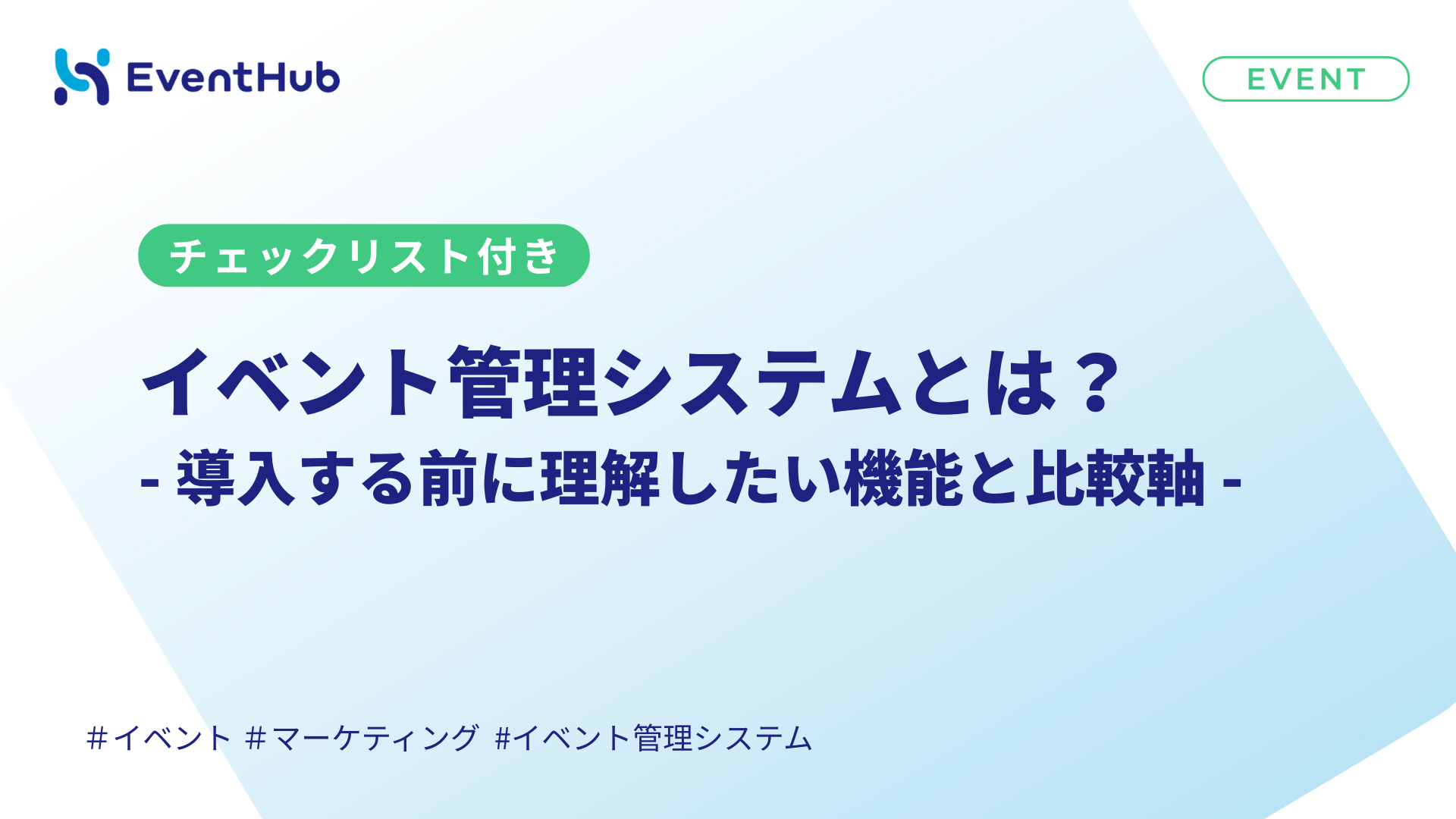
イベントの開催においては、申込み受付、来場者管理、資料配布、アンケートの実施、さらにはリードの獲得からフォローアップまで、多くの業務が発生します。こうした煩雑な業務を効率的に一元管理するために活用されているのが「イベント管理システム」です。
このシステムは、展示会、セミナー、カンファレンスなどイベントのタイプを問わず、企画から当日の運用、終了後の分析まで、各工程をサポートする多機能なツールです。主催社にとっては、業務効率化だけでなく、イベントの目的達成に向けたマーケティング施策の実現にも直結する重要な存在といえます。
近年では、オンラインやハイブリッド形式での開催も増加し、必要な機能も多様化しています。参加者の行動データをリアルタイムで取得・分析できる機能や、QRコードによるチェックイン、動画配信との連携など、イベント体験を向上させるためのツールとしても注目を集めています。
本記事では、イベントの種類ごとに求められる機能や、導入前に比較すべきポイントをわかりやすく解説し、自社に最適なツールを選定するための視点とチェックリストを紹介します。
イベント管理システムの定義と役割
イベント管理システムは、イベントの準備から開催、終了後のフォローまでを一元化して支援するシステムです。特に参加者とのタッチポイントが多いイベント業務においては、申込み管理、受付対応、アンケート収集、リード情報の取得といった幅広い業務に対応する必要があります。
このような業務の煩雑さやヒューマンエラーを軽減し、効率的かつ正確に運用するために、専用のシステムを導入する企業が増えています。参加者情報の登録や当日のチェックイン管理、来場履歴のログ取得、動画配信やメール配信機能の搭載など、専用の管理システムには、業務効率化に直結する機能が多く含まれています。
さらに、オンライン開催やハイブリッドイベントに対応したプラットフォームでは、ライブ配信、視聴ログの取得、オンラインセッション設計など、Webを通じた双方向コミュニケーションの実現も可能です。従来の紙ベースやExcel中心の運用から脱却し、リアルタイムで状況を把握・改善できる環境が構築できるようになってきています。
イベントの種類に応じた管理の必要性
イベントには展示会、セミナー、カンファレンス、ウェビナー、社内イベントなど多くの形式があり、それぞれのイベント目的や規模、開催方法によって求められる管理機能が異なります。
| イベントタイプ | 主な目的・特徴 | 必要な管理機能・対応項目 |
|---|---|---|
| 展示会 | 複数出展社による商談・製品紹介の場。来場者数が多く、リアルでの交流が中心。 | ・ 出展社・ブース情報の登録と管理 ・ 事前告知・チケット発行 ・ QRコードによる受付・入場管理 ・ 来場者の行動ログ・滞在履歴の取得 |
| セミナー | 自社製品やサービスの理解促進・リード育成を目的とした説明会形式。 | ・ カスタマイズ可能な申込みフォームの作成 ・ 資料の事前・当日配信 ・ 参加率向上のためのリマインド配信 ・ アンケート作成と回答データの取得 |
| カンファレンス | 複数のセッションを持つ専門性の高いイベント。ハイブリッド開催が多い。 | ・ セッション単位のスケジュール作成と予約受付 ・ 講演者・プログラム情報の掲載 ・ 同時開催トラックへの対応 ・ ハイブリッド対応と動画配信機能 |
| ウェビナー | オンラインで完結する情報発信型イベント。参加のハードルが低く、幅広い層へアプローチ可能。 | ・ ライブ配信・録画配信の切替対応 ・ 登録者への自動リマインド通知 ・ チャットやQ&Aなどのインタラクティブ機能 ・ アーカイブの共有・視聴ログの分析 |
| 社内イベント | キックオフや表彰式、研修など、社内向けのコミュニケーション強化を目的とする。 | ・ 社員の申込み管理・グループ分け ・ 資料・動画の配信と視聴状況の可視化 ・ 出欠管理とアンケートの自動集計 ・ セキュアな認証・アクセス管理 |
また、オンラインやハイブリッド形式の増加に伴い、動画配信の品質、参加者の視聴環境、認証・セキュリティ対策などにも注目が集まっています。これらを適切に運用するためにも、イベントのタイプに合った管理システムの選定が重要です。
イベントタイプ別:必要な機能と選び方のポイント
イベント管理システムを選ぶ際は、イベントのタイプに応じて求められる機能を整理することが不可欠です。展示会やセミナー、カンファレンスでは、運営上必要となる要素や重視すべき機能が大きく異なるため、それぞれの目的や業務内容に即したシステムを選定する必要があります。
また、導入を検討する際には、単に機能の多さで比較するのではなく、「自社の運用体制に合っているか」「現場の担当者が使いやすいか」「将来的な拡張性があるか」など、多角的に評価することが大切です。以下では、代表的なイベントタイプ別に必要な機能や選び方のポイントを紹介します。
展示会に必要な機能:受付・来場者データ・リード管理
展示会では来場者数が多く、ブース対応に追われるため、現場オペレーションの効率化が求められます。次のような機能を備えているシステムが有効です。
- QRコードを活用した受付管理
事前登録情報に基づいたQRコード発行により、スムーズなチェックインと混雑の回避が可能です。 - 来場者データのリアルタイム取得
受付・チェックインと同時に参加者の基本情報や滞在時間、移動履歴などを取得でき、営業支援や後追い活動に役立ちます。 - 名刺管理・リード情報の自動連携
商談に発展する可能性のある来場者データをCRMやMAツールと連携させることで、リード獲得からフォローアップまで一貫して対応できます。 - アンケートや資料ダウンロード機能
展示製品やサービスへの関心を数値化し、見込み度の高いリードを特定する材料として活用できます。
展示会は大規模かつ短期間で開催されるため、会期中に収集する情報の質と量が重要になります。データの取得と一元管理、リアルタイムでの分析が可能なシステムを導入することで、展示会の成果向上につながるでしょう。
セミナー運営で重視すべき要素:申込み・資料配布・アンケート
セミナーのように参加者との接点が比較的近く、情報提供を目的としたイベントでは、いかにスムーズな運営と参加者の満足度を両立できるかが重要です。申込みから資料提供、アンケート回収までを効率的に管理することが不可欠です。
以下のような機能に特化したイベント管理システムの導入が有効です。
- 申込みフォームの作成とカスタマイズ
フォームは自社のブランディングに合わせてデザインでき、カスタムドメイン対応で信頼性も向上します。キャンセル待ちや申込者数制限の設定など、柔軟な運用も可能です。 - 自動リマインドメールと通知機能
事前のリマインド配信により参加率が向上し、セミナー当日の無断キャンセルや問い合わせを減らす効果があります。 - 資料の事前送付・当日配布
URLによる資料配布に加えて、セミナー中の画面共有や資料ダウンロードの対応もスムーズに行えます。 - アンケート作成とアンケート回答率の向上
セミナー直後にアンケートを自動送信し、回答率を最大化。設問設計の自由度が高く、定量・定性のデータをバランスよく取得できます。 - 視聴履歴・行動ログの取得と分析
誰がどのセッションをどの程度視聴したかを可視化し、興味関心の高い参加者を特定。インサイドセールス(IS)部門との連携にも活用可能です。
ウェビナー形式の開催も一般化しており、配信形式の柔軟性や操作性もシステム選定のポイントとなります。ライブ配信や録画コンテンツのアーカイブ対応も含め、自社の開催体制に適した形式を選ぶことが重要です。
カンファレンスでの活用:セッション管理と集客強化
カンファレンスは、複数のセッションや講演が並行して行われる大規模なイベントであり、展示会やセミナーに比べて、より高度な設計と運用が求められます。主催社や担当者は、当日の混乱を避けるだけでなく、参加者の満足度を向上させるために、各セッションを効果的に管理する体制を構築します。
そのため、カンファレンスに特化したイベント管理システムでは、以下のような機能が重視されます。
- セッションごとの予約・申込み機能
参加者は事前に希望セッションを選択でき、当日の参加者数予測やリソース配分に役立ちます。 - スケジュール作成と画面表示の自動化
複数トラックのセッションを時間帯ごとに整理し、Webサイト上に見やすく表示することで、参加者の迷いを軽減します。 - セッション単位での視聴ログ・参加履歴の記録
どのセッションに参加したかを可視化することで、興味関心に基づくフォローアップ施策の精度を高めます。 - 登壇者情報の掲載と資料の個別配信
講演者のプロフィールや関連資料を事前に共有することで、イベント全体の情報価値を高め、参加者の理解を促進します。 - リアルタイムでの告知・変更対応
会場変更やタイムテーブルの調整が発生した場合でも、メールやアプリ通知によって即時に情報を伝達できます。
加えて、カンファレンスは集客面でも戦略が重要です。ランディングページ(LP)による告知、SNS連携、参加登録後のフォローメールなど、各フェーズに応じたアプローチが必要です。MAツールやCRMとの連携により、イベント終了後のリードナーチャリングや商談化もスムーズに進められます。
イベント管理システムの主要機能一覧
イベント管理システムには、開催形式や規模にかかわらず共通して求められる基本機能が多数搭載されています。これらは単なる業務効率化にとどまらず、参加者体験の向上や商談創出といったビジネス成果の実現にも寄与します。
以下に、代表的な機能を整理して紹介します。
- 申込み受付と参加者情報の一元管理
申込者のデータは自動で蓄積され、リストとして可視化・分析可能。セグメントごとの管理や情報の一括編集にも対応します。 - QRコードによるチェックイン管理
イベント当日の受付業務を効率化し、入場履歴やチェックイン時間のログ取得にも対応。混雑を回避し、スムーズな導線設計が実現できます。 - アンケート作成と回答データの集計
回答率を向上させるUI設計や、リアルタイムでの回答確認・集計が可能。アンケート結果をもとに満足度分析や今後の施策設計に活かせます。 - 資料配布と動画配信の管理
事前・当日の資料送付だけでなく、ウェビナーやセミナーのライブ配信・録画配信も管理可能。参加者ごとの視聴履歴も把握できます。 - CRM・MAツールとの連携
イベントで取得したリード情報を、インサイドセールス(IS)や営業チームにリアルタイムで共有。フォロー体制の強化やリードの商談化を支援します。 - セキュリティと参加者認証機能
パスワード保護、メール認証、アクセス制限、カスタムURLの発行などにより、安心してイベントを運用できます。 - 配信メール・リマインド通知の自動化
イベント前後のメール配信をスケジュール設定でき、申込み完了通知や前日のリマインド、参加後のお礼メールまで自動で送信されます。
これらの機能は、オフライン・オンライン・ハイブリッドといった形式を問わず、さまざまな業務に対応します。特に、リアルタイムでのログ取得や行動データの分析は、次回以降のイベント企画やマーケティング戦略にも活かせる貴重な情報源となります。
比較ポイント:自社に合うシステムの見極め方
イベント管理システムの選定にあたっては、機能の充実度だけでなく、自社の業務内容や運用体制、イベントのタイプや規模に応じた適合性が重要です。「人気」「無料」「多機能」といった基準だけではなく、目的達成に必要な機能が備わっているかを軸に検討することが成功への近道となります。
以下の視点から、導入前に比較・確認すべき項目を整理します。
| チェックカテゴリ | チェック内容 | 補足説明 | 評価ポイント |
|---|---|---|---|
| イベント対応機能 | イベントの目的と形式に合った機能を搭載しているか | 展示会・セミナー・カンファレンス・ウェビナーなど、開催形式に応じた最適な機能(動画配信、セッション管理、チェックイン等)を備えているか | 自社イベントのタイプに合った対応範囲の広さ |
| 操作性・UI | 業務フローに合った操作性があるか | 担当者が使いやすい画面設計か。専門知識が不要なUIか。直感的な操作で作業負担が少ないか | 教育コストの低さ、日常業務への適合度 |
| 外部連携 | 連携できる外部ツールの範囲は十分か | CRM、MA、フォーム、チケット販売、配信ツールとの連携可否。API連携や突合作業の自動化など | 社内外システムとの連携性・自動化対応力 |
| セキュリティ | セキュリティ・プライバシー対策は万全か | アクセス制限、パスワード設定、認証機能、暗号化対応など、個人情報の保護対策が整備されているか | 情報漏洩リスクへの対応力と安全性 |
| 費用・契約条件 | 費用対効果と契約条件が自社に合っているか | 無料・有料プランの違い、利用料、カスタマイズ費、契約期間、サポート範囲などのコストバランス | コストと機能のバランス、柔軟な契約内容 |
| 導入実績 | 導入事例やサポート体制に信頼性があるか | 同業種・同規模での活用実績、導入時の支援体制、トラブル対応の速さなど | 信頼性・安心感・長期運用のサポート力 |
このような比較軸をもとに、実際のイベント運用フローと照らし合わせながら、最適なシステムを選定していくことが成功の鍵となります。
導入事例に学ぶ:成功企業の活用ポイント
イベント管理システムを効果的に活用している企業の事例を参考にすることで、具体的な運用イメージや成果の出し方を把握しやすくなります。ここでは、特に大規模イベントを運営する企業や、限られたリソースで成果を上げている企業の活用ポイントを紹介します。
カオナビ社の事例:イベントマーケティングの商談化率を大幅に向上
タレントマネジメントシステム「カオナビ」を提供する株式会社カオナビでは、ウェビナーやカンファレンスを中心としたイベントマーケティング施策に力を入れており、その施策を支える基盤としてEventHubを導入しています。
カオナビ社のマーケティング部門は、インバウンド施策とイベントマーケティングを掛け合わせたアプローチで、より広範囲なリード獲得と商談化を実現。なかでもEventHubの導入により、総商談の約40%がイベント経由で生まれるという成果を挙げています。
同社では、共催ウェビナーや自社カンファレンスを通じて毎月複数回のオンラインイベントを実施していますが、以前は開催数が増えるにつれてアンケート回収やデータ突合作業に膨大な工数がかかり、ミスも発生していました。EventHubを導入することで、以下のような効果が得られました。
- MarketoやSalesforceとのノーコード連携により、リード情報の一元管理とデータ突合作業を大幅に効率化(約5時間→1時間に短縮)
- ウェビナー中のアンケート回答率が向上し、優先的にアプローチすべきリードの可視化を実現
- Slack通知との連携で、来場タイミングをリアルタイムに把握し、営業が即座に対応可能な体制を構築
- オフラインカンファレンスの受付業務もEventHubに委託し、当日の不安や負荷を軽減。顧客対応に集中できる体制を整備
さらに、2025年2月に開催された大規模カンファレンス「FACE to FES’25」では、参加者同士の交流を促す設計やセッション構成に加え、EventHubを活用した円滑な運営により大きな成功を収めました。受付、配信、顧客情報管理、アフターフォローまでを一貫して最適化したことが、イベント価値を最大化するカギとなっています。
このように、カオナビ社ではEventHubの機能をフルに活用し、イベントを単なる集客施策ではなく、商談獲得・顧客体験強化の中核施策として運用しています。
👉 導入事例「総商談の約40%がイベントマーケティングから!イベントマーケの効果をEventHubで最大化し、事業成長に貢献」

ビズリーチ社の事例:営業接点を最大化し、満足度95.8%の大規模カンファレンスを実現
即戦力人材向け転職サービス「ビズリーチ」などを運営する株式会社ビズリーチでは、年間数十回に及ぶイベントを開催しており、なかでも年に数回行われる大型カンファレンスは営業部門・マーケティング部門を横断した全社規模の施策として位置づけられています。
2024年に開催された「HR SUCCESS SUMMIT」では、2,500人超の来場者を迎える中で、受付混雑や営業機会の損失を防ぐ運営体制の構築が課題となっていました。
同社はその解決策としてEventHubを導入し、QRチェックイン機能とSlack通知機能を活用。以下のような効果を実現しています。
- 来場時・セッション参加時など複数箇所でQRチェックインを実施し、顧客行動をリアルタイムで把握
- 営業担当者へ即時通知することで、お客様への挨拶や商談機会の創出に成功
- 過去最高の参加者満足度(95.8%)を記録し、混雑やトラブルの声も一切なし
- ノーコード連携により社内システムとの統合もスムーズに実施
さらに注目すべきは、イベント成功の裏側にある「ビズリーチ流イベントマーケティング」の取り組みです。同社では事業部横断でアンバサダー制度を導入し、全社を巻き込んだプロジェクト体制を構築。イベント当日までに顧客接点を最大化し、社内外のコミュニケーション活性化にもつなげています。
Slack通知の導入については、営業担当からも「今誰が来場しているかが即時で分かるため、積極的に声をかけられた」という声が多く上がり、前年度を上回る営業接点数を達成。単なる来場者数の増加だけでなく、質の高い対話と体験を提供できたことが、大きな成果につながりました。
👉 導入事例「営業からも『多くのお客様にご挨拶できた』という満足の声多数来場時や様々なチェックポイントの通過時のSlack通知機能により前年度よりも多くの顧客接点を創出」

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの事例:フルスクラッチからEventHubに切替え、工数最大50%削減を実現
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートは、主力製品であるエンタープライズ・ローコードプラットフォーム「intra-mart Accel Platform」を中心に、SaaS・コンサルティング・システム開発など幅広いサービスを展開し、企業のDX推進を支援しています。
同社は、20年以上にわたり続くフラグシップイベント「intra-mart LIVE」を通じて、見込み顧客の創出・パートナー企業との連携強化を図ってきました。2023年よりEventHubを導入し、フルスクラッチ開発からの転換による大幅な効率化に成功しています。
フルスクラッチから脱却し、準備・運用工数を大幅削減
それまでのイベント運営では、毎回開発を要するフルスクラッチの環境で開催準備に多大な手間とコストがかかっていたことが課題となっていました。EventHub導入後は、SaaS型のイベントプラットフォームの利便性により、準備工数を50%・管理運用の工数を30%削減することができました。
成果につながる運営改善とKPI達成
EventHubの導入によって、単に運営効率が向上しただけでなく、申込者数は前年から129%増加。また、参加者からの運営や受付に関するネガティブなフィードバックも大きく減少し、ユーザー体験の質も向上しています。
具体的な成果としては以下の通りです。
- セッション数:49→51(前年比104%)
- スポンサー数:25→30(前年比120%)
- 展示ブース数:17→38(前年比224%)
- 申込者数:3,061→3,948(前年比129%)
Marketo連携や自動印刷などの機能改善が運営を後押し
同社では、リード管理の効率化も重要課題でしたが、MarketoとのAPI連携や当日受付での自動印刷機能が新たに実装されたことで、当日の運用も格段にスムーズに。カスタマーサクセスチームの手厚いサポートもあり、「要望していた機能の8割が改善されていた」と評価されています。
ハイブリッド開催での柔軟な対応も可能に
「intra-mart LIVE 2024」では、1日目をオフライン、2日目をオンラインというハイブリッド開催形式を採用。EventHubは両形式に対応しており、オペレーションの一元管理やUI/UXの一貫性も高評価を得ています。
フルスクラッチでの開発に限界を感じている企業や、イベントごとの負担を軽減したいと考えている主催社にとって、非常に参考となる事例です。機能改善に対する柔軟な対応とカスタマーサクセスの伴走支援によって、初年度にとどまらず2年目以降も継続的に成果を伸ばしています。
👉 導入事例「フラグシップイベント開催をフルスクラッチ開発システムからEventHubに変更 開催準備が50%・管理や運用が30%の工数削減」

primeNumber社の事例:オフライン初開催で集客125%・商談数も大幅達成
株式会社primeNumberは、「あらゆるデータをビジネスの力に変える。」をビジョンに掲げるデータテクノロジーカンパニーであり、クラウドETLサービス「TROCCO」やデータカタログ「COMETA」などのSaaSを展開しています。
同社では、自社プロダクトやデータエンジニアリングの価値を広めるため、カンファレンス「01(zeroONE)」を中心にイベントマーケティングを推進しており、2024年12月には初めてのオフライン開催に挑戦しました。
今回のイベントでは、単なる集客数ではなく「コミュニケーションの質」を重視し、リアルな対話や顧客との接点の質的向上を主なKPIに設定。EventHubの導入により、以下のような成果を挙げました。
- 集客目標を125%超で達成
- 商談数が目標を大きく上回り、期待を大幅に超える結果に
- QRコードによるチェックインで参加者の動向をリアルタイムに可視化
- スポンサーブースでは交流機能を活用し商談予約が活発化
- 開催後はLookerやSalesforce、Zapierと連携し、データの即時可視化と一元管理を実現
特に印象的だったのは、セッションごとの参加者データをもとにリアルタイムで会場誘導を行った運営体制です。参加人数が少ないセッションにはスタッフがその場で声掛けを行うなど、データを活かした柔軟な運営によって会場の活性化と顧客体験の最大化に成功しました。
また、EventHubのAPI連携機能を通じて、MarketoやSalesforceとスムーズに連携できたことも大きなメリットでした。商談につながるリード情報の取得・共有・管理が高速かつ正確に行える環境が構築され、初のオフライン開催とは思えないほどの完成度でイベントを成功に導いています。
社内でもマーケティング部だけでなく、営業・エンジニア・広報・人事が連携し、全社一丸で取り組んだ結果、イベントを通じて「本当に会うべき顧客と出会えた」という実感がチーム全体に広がりました。
👉 導入事例「集客目標の125%超え!コミュニケーションの質を重視した結果、商談数のKPIも大幅に上回る」

ネットワンシステムズの事例:ビジョンに寄り添う企画支援で顧客体験と社内評価の両立を実現
ネットワンシステムズ株式会社は、ネットワークインフラやICT利活用の分野で豊富な実績を持つ情報通信企業です。自社の中期経営計画と連動する戦略的なイベント「netoneDay」を、2021年よりEventHubと共に3年間連続で企画・運営してきました。
特に2024年の開催では、参加者体験の向上・社内評価・リード獲得すべてにおいて高い成果を収めています。
「中期経営計画」と連動したイベント企画
netoneDayは、単なるマーケティング施策ではなく、将来の売上に繋げる種まきとしての意味合いが強いイベントです。開催にあたっては、企業の中計を反映しながら顧客・社員双方に価値提供できる構成が求められました。
EventHubのイベントプロデューサーは、主催社の事業方針やイベントの目的を深く理解した上で企画を提案し、イベント全体を「戦略的コミュニケーションの場」として構築。その結果、来場者・登壇者・社員・協賛企業にとって有意義な時間となりました。
イベント成果:満足度の高さとリード獲得
2024年のnetoneDayでは、ハイブリッド形式での実施により幅広い参加者層へのリーチを実現。イベントの成果としては以下の通りです。
- イベント満足度向上:「会社の思想がしっかり伝わった」との社内評価
- 新規接点の創出:80件のリードを創出
- 登壇を通じた顧客関係の深化:既存顧客との関係が強化され、新たな部署への接点も拡大
特に、将棋棋士・羽生善治九段とAI研究者による基調講演は、テーマ性・話題性・戦略性すべてにおいて非常に高評価でした。
運営の効率化と一元管理による負荷軽減
EventHubを導入した理由のひとつは、動画配信を含むカンファレンス機能のオールインワン提供。配信、コメント、申込フォーム、メール配信、データ管理などを一つのプラットフォームで実現できたことで、スクラッチ開発不要で運営工数を大幅に削減できました。
また、参加データのリアルタイム可視化や来場通知機能なども社内のモチベーション維持に貢献し、イベント運営を全社で支える体制づくりに繋がっています。
EventHubのプロデュースチームが果たす価値
主催社は、EventHubのイベントプロデュースチームに対し、「社外パートナーでありながら、自社の一員のように寄り添ってくれる存在」と高く評価。提案の質・実行力・スピード感いずれも高く、信頼関係の上でイベントを進行することができました。
「やりたいこと」を話すと即座に複数の選択肢を提示してくれる柔軟性や、突発的な変更への迅速な対応など、経験値の高さとホスピタリティがイベント成功につながりました。
「技術的な使いやすさ」と「伴走型のプロデュース支援」の両輪で、企業の戦略とイベントを接続した成功事例です。参加者満足度・社内評価・営業成果すべてを向上させたい企業にとって、非常に示唆に富んだ導入事例といえるでしょう。
👉 導入事例「EventHubのイベントプロデューサーと共に歩んだ3年間 会社の中期経営計画や課題を汲み取った上で企画運営を行ったことが絶大な信頼感に」

導入前に使えるチェックリスト
イベント管理システムの導入にあたっては、目的や運用体制に合わせて、あらかじめ必要な条件を明確にしておくことが重要です。導入後のトラブルや期待外れを防ぐためにも、事前の確認ポイントを整理し、社内での情報共有を徹底しましょう。
以下は、導入前に検討・確認しておくべき代表的なチェック項目です。
| チェックカテゴリ | チェック内容 | 補足説明 | 評価ポイント |
|---|---|---|---|
| イベント対応機能 | イベントの目的と形式に合った機能を搭載しているか | 展示会・セミナー・カンファレンス・ウェビナーなど、開催形式に応じた最適な機能(動画配信、セッション管理、チェックイン等)を備えているか | 自社イベントのタイプに合った対応範囲の広さ |
| 操作性・UI | 業務フローに合った操作性があるか | 担当者が使いやすい画面設計か。専門知識が不要なUIか。直感的な操作で作業負担が少ないか | 教育コストの低さ、日常業務への適合度 |
| 外部連携 | 連携できる外部ツールの範囲は十分か | CRM、MA、フォーム、チケット販売、配信ツールとの連携可否。API連携や突合作業の自動化など | 社内外システムとの連携性・自動化対応力 |
| セキュリティ | セキュリティ・プライバシー対策は万全か | アクセス制限、パスワード設定、認証機能、暗号化対応など、個人情報の保護対策が整備されているか | 情報漏洩リスクへの対応力と安全性 |
| 費用・契約条件 | 費用対効果と契約条件が自社に合っているか | 無料・有料プランの違い、利用料、カスタマイズ費、契約期間、サポート範囲などのコストバランス | コストと機能のバランス、柔軟な契約内容 |
| 導入実績 | 導入事例やサポート体制に信頼性があるか | 同業種・同規模での活用実績、導入時の支援体制、トラブル対応の速さなど | 信頼性・安心感・長期運用のサポート力 |
これらのチェック項目をもとに、関係部署と連携しながら導入計画を立てることで、失敗のリスクを抑え、より効果的なシステム運用が実現できます。
まとめ:イベント成功の鍵を握る管理システムの最適化とは
イベント管理システムは、イベントの成功を左右する重要なツールです。開催形式やイベントの規模を問わず、申込み受付から参加者管理、データ分析、フォローアップに至るまで、幅広い業務を効率化し、質の高いイベント体験を提供します。
以下に、本記事の要点を整理します。
- イベントの種類に応じた機能の見極めが重要
展示会、セミナー、カンファレンスなど、イベントタイプにより必要な機能は大きく異なります。目的と形式に合致したツール選定が成果の第一歩となります。 - 管理業務の一元化で担当者の負担を軽減
申込み、受付、資料配信、アンケート、ログ取得などをシステムで一括管理することで、手間とミスを削減し、業務効率が向上します。 - 配信機能や外部ツールとの連携で活用範囲が拡大
CRMやMA、配信ツールなどと連携することで、リード獲得や商談化につなげやすくなり、イベントのビジネス価値が高まります。 - 導入前のチェックリストで最適な選定が可能に
自社の体制や課題に即した比較ポイントを押さえて検討することで、失敗リスクを最小限に抑え、導入効果を最大限に引き出せます。 - 導入事例から運用のヒントを得る
他社の成功事例を参考に、自社のイベント体制に取り入れるべき工夫や運用改善の方向性を明確にできます。
イベント管理の精度を高めることは、イベント自体の成功と、その後の顧客との良質な接点構築や営業成果にも直結します。システムの選定から運用設計、社内連携までを戦略的に進める視点が、これからのイベントに求められるでしょう。
よくあるご質問
質問:イベント管理システムを導入することで、どのような業務が効率化されますか?
回答:申込み受付、参加者管理、当日のチェックイン、資料配布、アンケート回収、視聴ログの取得、フォローアップメールの配信など、多岐にわたる業務が一元管理可能になります。これにより担当者の作業負担が軽減され、業務の属人化も防げます。
質問:展示会で来場者の情報を取得するにはどのような機能が必要ですか?
回答:QRコードによる受付やチェックイン、行動ログの記録、名刺情報のデジタル化機能が有効です。これらのデータをCRMやMAと連携すれば、見込み顧客のフォロー施策にもすぐ活用できます。
質問:セミナー参加者への資料配布はどのように行えますか?
回答:イベント管理システム上で、申込み完了時やセミナー後にURLを使って資料を配信できます。資料のダウンロード履歴も取得できるため、参加者の関心度分析にも活用できます。
質問:オンラインイベントにおけるセキュリティ対策にはどのような機能がありますか?
回答:メールアドレス認証、パスワード設定、URLのアクセス制限、操作ログの取得などの機能があります。これにより、参加者情報の保護や不正アクセスの防止が可能です。
質問:イベント後のアンケートを活用してどのような改善が可能になりますか?
回答:参加者の満足度や関心テーマ、改善要望などを収集することで、次回イベントの企画や施策の質を高めることができます。アンケート回答率を上げるには、終了直後に自動送信する設計が効果的です。