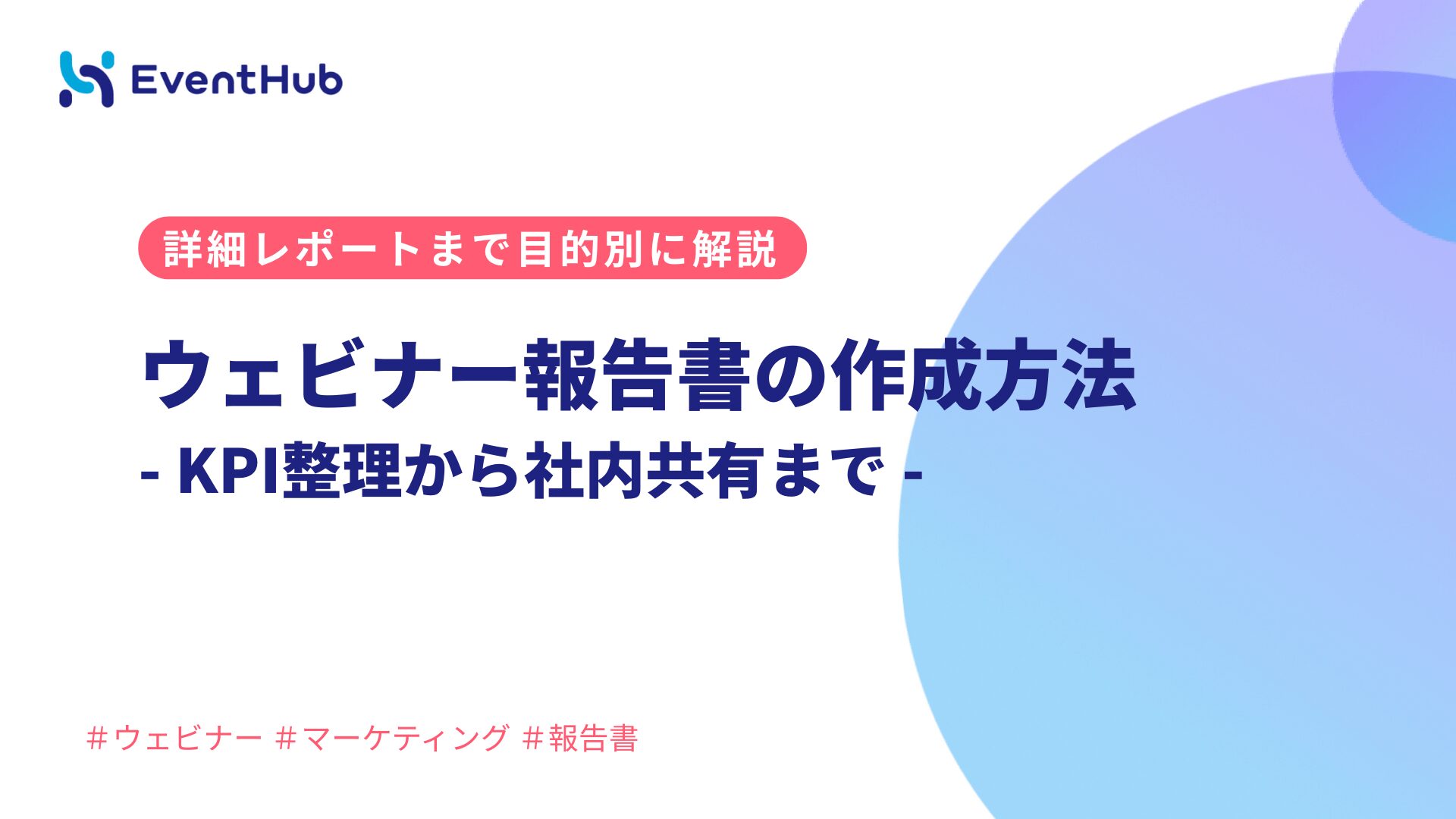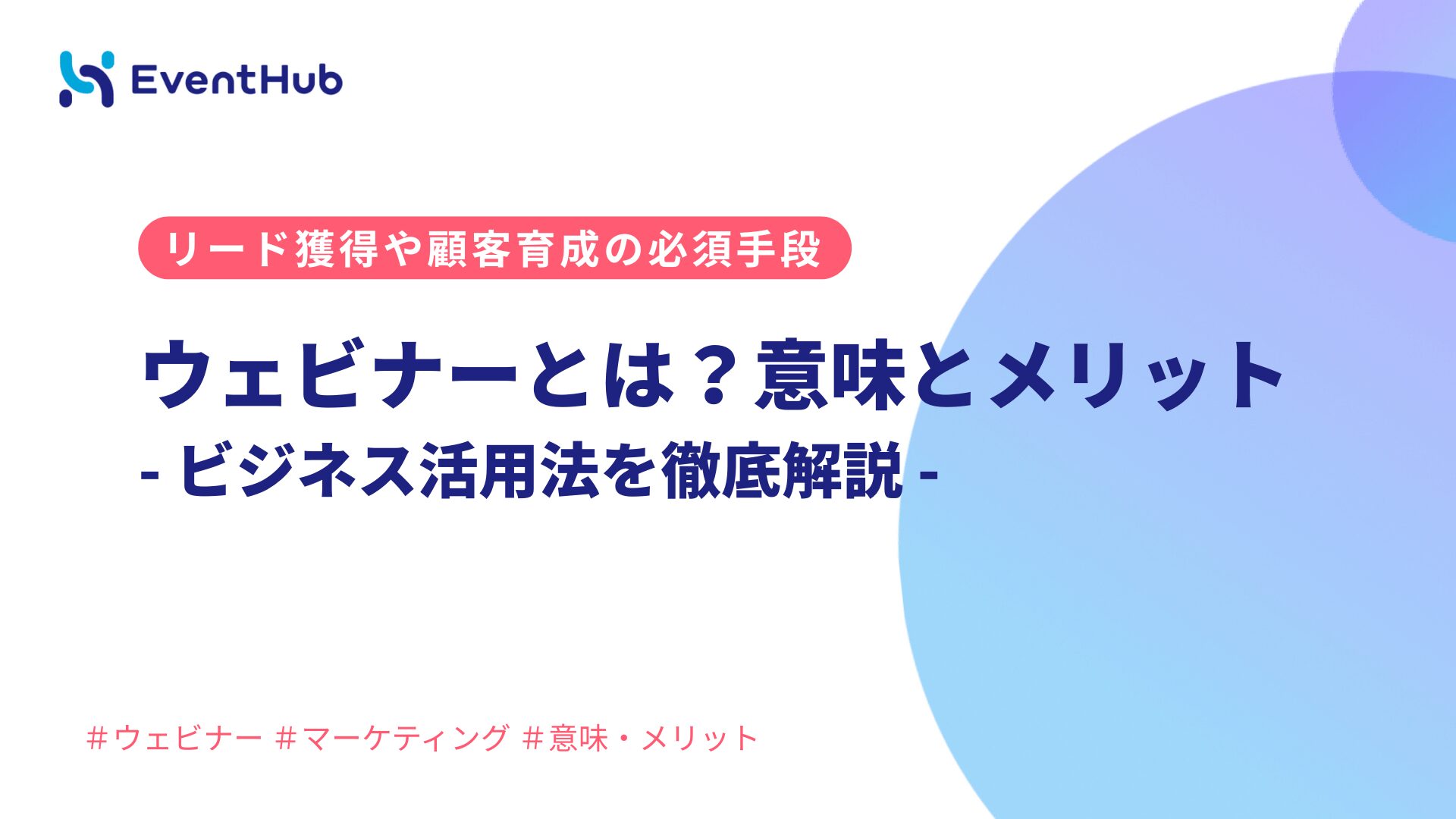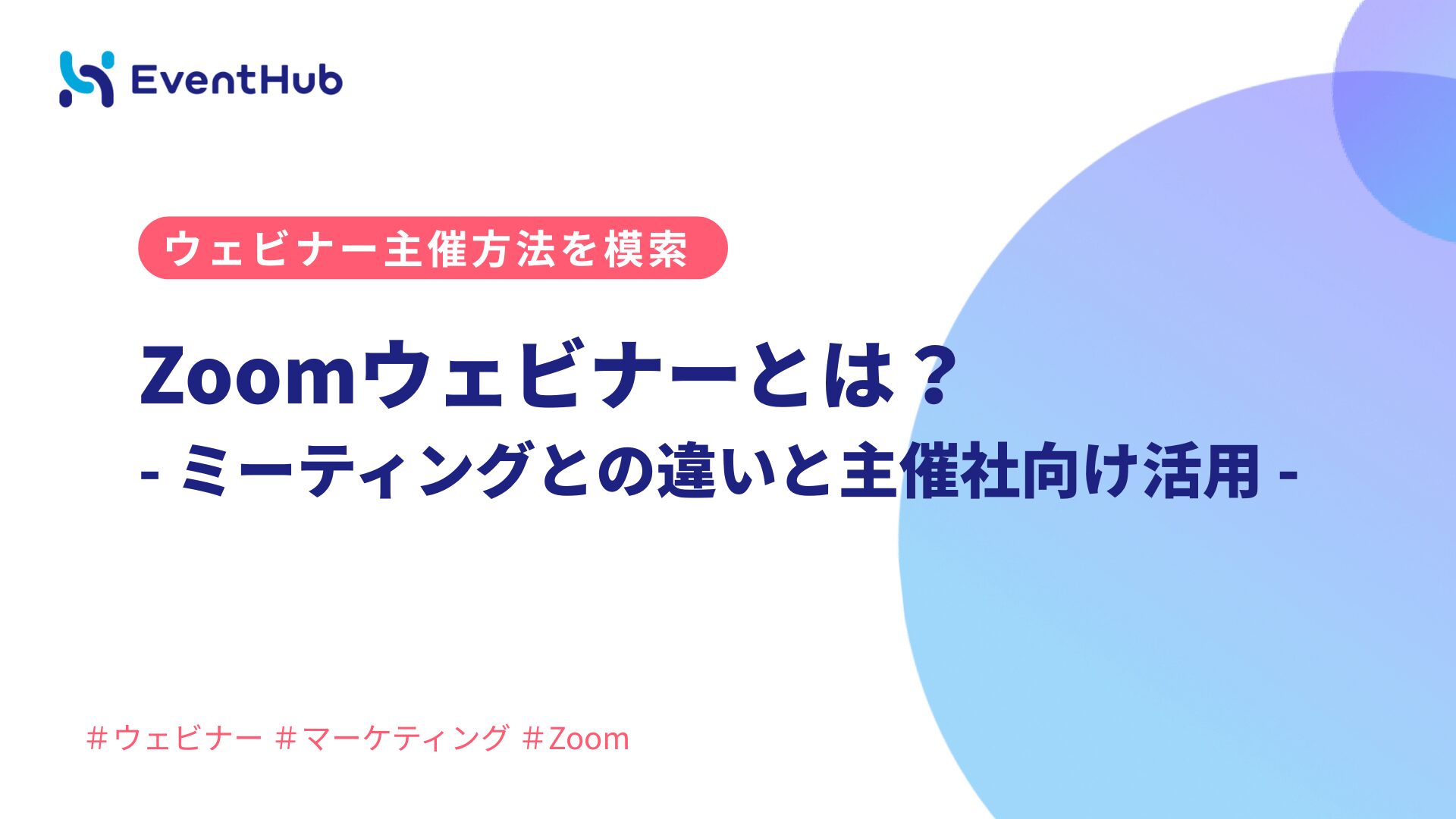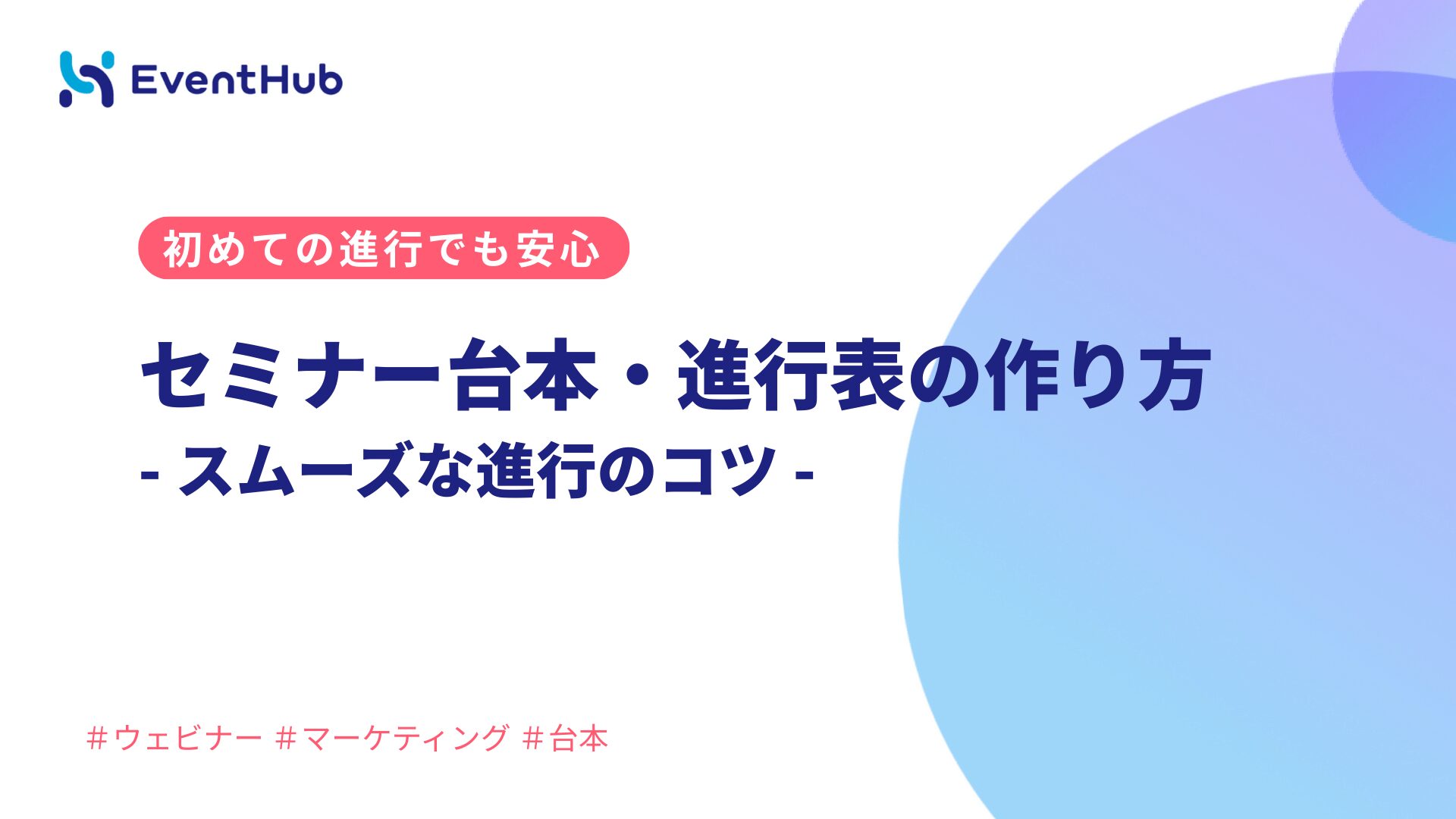イベント企画書の書き方とは?|企画書で抑えるべき構成や盛り上げる企画につなげるテンプレート
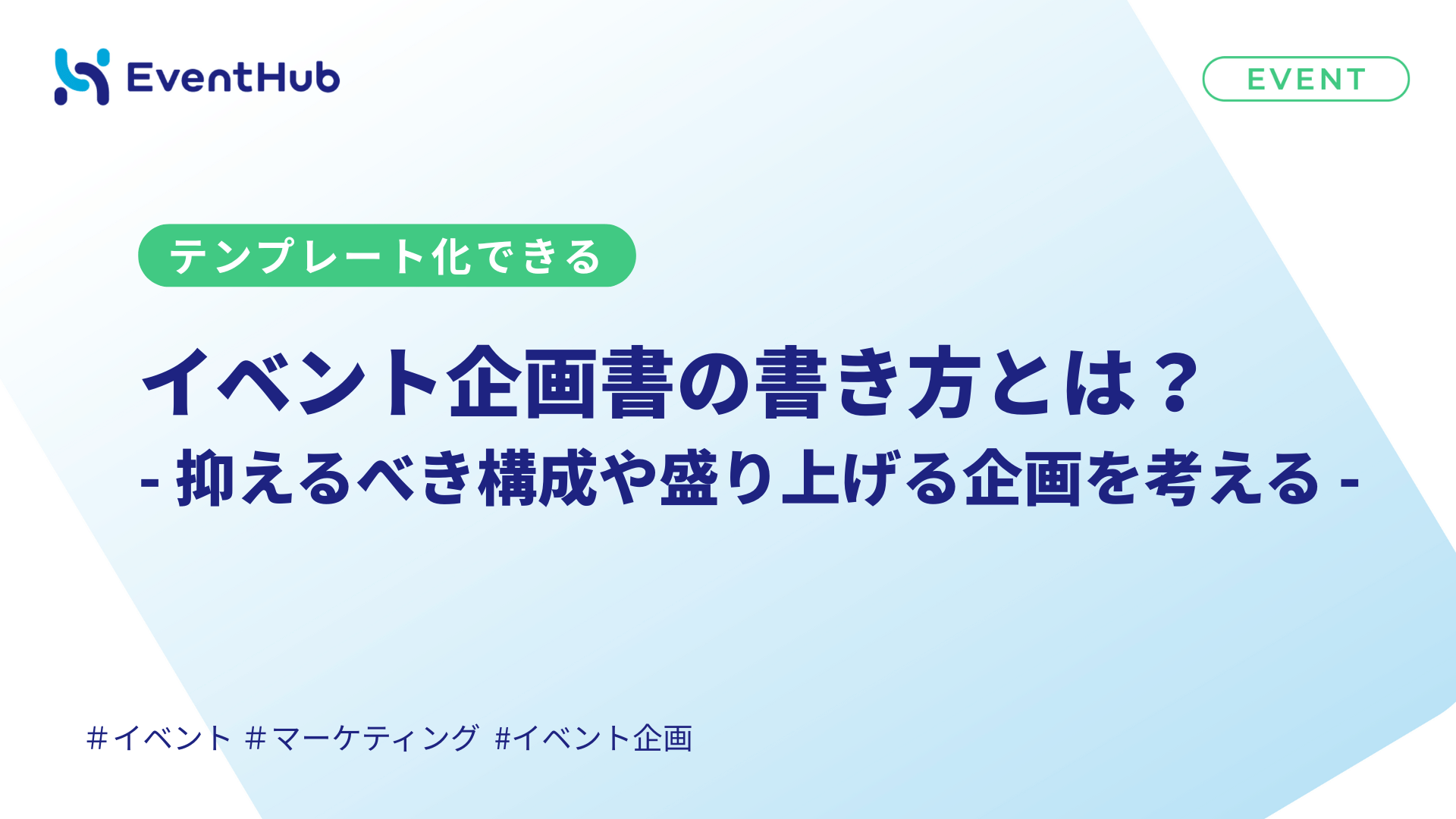
イベントを成功に導くためには、開催目的や全体設計が明確な企画書の作成が欠かせません。特に社内の関係者や決裁者が理解しやすく、スムーズに承認を得るためには、企画書の構成や項目を整理し、具体的なプランとして示す必要があります。本記事では、イベント企画書の基本的な書き方や構成、テンプレートの活用方法までを解説します。企画立案から資料作成、開催準備、効果測定に至るまで、初心者でも実践しやすい流れを紹介します。自社の目的やターゲットに合わせて最適なイベントを計画したい担当者に向けて、成功する企画書づくりのポイントを整理します。
イベント企画書の基本構成と目的の明確化
イベント企画書は、イベントの目的や全体像を明確にし、関係者が同じ方向を向いて準備・実施を進めるための重要な資料です。特に主催社や社内の決裁者、外部協力会社など複数の担当者が関わる場合、企画書の内容が理解しやすく整理されていることが重要です。
企画書を構成する際は、以下の基本項目を意識するとよいでしょう。
- イベントの目的・概要・テーマ
- 開催日時・会場・規模・対象となる参加者数
- 目標(KPI)や達成指標の明記
- スケジュールと各メンバーの役割分担
- 予算と収支計画
- 想定されるリスクとその対応策
- 効果測定と改善方法
このような項目を段階的に整理することで、企画の意義を明確化しやすくなります。特に目的やゴールを先に設定しておくと、資料全体の流れに一貫性が生まれます。また、タイトルやテーマの表現を簡潔にし、関係者がすぐに理解できる構成にすることが重要です。
イベント企画書の役割とは?
イベント企画書には、単なる計画書以上の役割があります。
それは、社内外の関係者と「何を」、「なぜ」、「どのように」行うかを共有し、目的を達成するための行動指針を明確にすることです。
特に次のような効果が期待できます。
- 社内承認プロセスの円滑化
明確な目的・スケジュール・予算が記載されていれば、決裁者が判断しやすくなります。
- 関係者間の共通認識形成
関係者全員が同じゴールとスケジュール感を共有でき、準備や当日の動きにブレがなくなります。
- 外部パートナーへの説明資料として活用
会場担当者、協力会社、PR担当などへも的確に情報を伝えられます。
- 効果測定の基準づくり
事後にアンケート結果やKPIを基に成果を評価する際の指標になります。
企画書は「実施するための資料」であると同時に、「判断・承認を得るための提案書」でもあります。そのため、目的とゴールを明記し、読み手が短時間で全体像を把握できるよう意識することが鉄則です。
成功するイベント企画の立案プロセス
イベントを成功させるためには、単に開催するだけでなく、目的達成に向けた明確な立案プロセスが必要です。企画段階では、目的・ターゲット・テーマの3要素を中心に構成を検討し、全体像を整理していきます。
イベント企画のプロセスを整理すると、次のような流れになります。
- 目的と目標の明確化
なぜ開催するのか、どんな成果を得たいのかを明確にします。 - ターゲット設定
参加者像(ペルソナ)を具体的に描き、どの層に最も効果がある企画かを検討します。 - テーマ設計とタイトル決定
目的とターゲットに合致したテーマを設定し、印象に残るタイトルを考案します。 - プログラム内容の検討
講演、出展ゾーン、セミナーなど、目的に適した形式を選択します。 - 体制・スケジュールの構築
社内外のメンバーの役割を明確にし、スケジュールを作成します。
特にターゲットとテーマが適切に設定されていないと、宣伝活動や集客施策にも影響します。SNSやメディアでの告知内容を検討する際にも、明確な方向性を持つことが重要です。
ターゲット設定とテーマ設計の鉄則
ターゲット設定は、イベント企画の成功を左右する重要な要素の一つです。ターゲットが曖昧だと、企画内容や訴求ポイントがぼやけてしまい、結果的に集客効果が低下します。まずは、自社のビジネス目的と参加者のニーズを整理し、明確なペルソナを定義することから始めましょう。
ターゲットを設定する際の基本的な視点は以下の通りです。
- 参加者の属性(業種・職種・役職など)
- 課題や関心領域(製品理解、顧客獲得、情報収集など)
- 行動特性(オンライン参加か、現地参加か)
- 参加動機(学習、交流、商談など)
その上で、設定したターゲットに響くテーマを設計します。テーマは短く、明確なメッセージ性を持たせることが重要です。タイトルには、「成果」、「体験」、「最新情報」などのキーワードを含めると、訴求力が高まります。
また、テーマやタイトルは企画書の冒頭に明記し、関係者や決裁者が一目で理解できるようにすることが大切です。特にビジネスイベントでは、目的とゴールの一貫性が求められます。社内共有用の資料に加え、外部向け提案書としても活用できるような構成を意識しましょう。
イベント企画書に必要な項目と書き方のコツ
イベント企画書を作成する際は、読む人が一目で全体像を把握できるように、必要な項目を整理して記載することが大切です。特に決裁者や関係者は限られた時間の中で判断するため、構成のわかりやすさと内容の簡潔さが求められます。
一般的なイベント企画書の項目は以下の通りです。
- イベントの目的・開催意義・ゴール
- 開催日時、会場、形式(オンライン・オフライン・ハイブリッド)
- 企画の概要、対象となるターゲット層
- スケジュールと実施体制(社内外の担当者、協力企業など)
- 予算と収支計画、会場費や外注費の内訳
- 期待される成果と効果測定の方法
- 想定リスクとその対応策
- 宣伝や集客施策(SNS・メディア活用)
これらを構成に沿って整理し、読みやすくまとめることが成功のポイントです。表紙にはタイトルと開催日を明記し、関係者がすぐに内容を理解できるようにします。
目的・概要・タイトルの明記方法
目的と概要は、イベント企画書の中でも最も重要な要素です。目的が不明確なままでは、どれほど魅力的な企画内容でも説得力に欠けてしまいます。まず、「なぜこのイベントを開催するのか」を明確にし、企業や自社の課題解決とどのように結びつくかを整理しましょう。
概要では、開催形式や規模、会場、ターゲット層、開催日時などを簡潔にまとめます。特に社内承認を得る際には、実施イメージを具体的に描けるような説明が重要です。
タイトルを決める際のポイントは次の通りです。
- 一目で内容や目的がわかるようにする
- ターゲットに響くキーワードを入れる
- イベント全体のテーマと一貫性を持たせる
- 宣伝やSNS投稿でも使いやすい表現にする
また、タイトルや概要には、成果や効果が伝わる言葉を使うとより印象的になります。例えば、「その場で商談までできるオフライン交流会」や「オンライン交流後に対面で会えるハイブリッドイベント」など、目的を含めた表現が効果的です。
さらに、パワーポイントやWordで作成する場合は、テンプレートを活用しつつ、自社のブランドカラーやフォントを統一することで、企画書全体の完成度を高められます。整ったフォーマットは、決裁者や外部パートナーへの信頼感にもつながります。
テンプレートを活用した効率的な企画書作成
効率的にイベント企画書を作成するためには、テンプレートを活用する方法が有効です。特に、WordやExcel、PowerPointなどの一般的なツールを使えば、誰でも短時間で整った資料を作成できます。テンプレートを使うことで、構成や項目の抜け漏れを防ぎ、企画書全体の統一感を保つことができます。
テンプレート活用のメリットは次の通りです。
- 構成が整理されており、初心者でも使いやすい
- 目的や内容に応じてカスタマイズできる
- チーム内で共有しやすく、修正や追記も簡単
- デザインやフォーマットを統一できる
また、自社のブランドやイベントの目的に合わせてテンプレートを調整することも重要です。イベントの種類や規模によって、必要な項目や強調すべき要素は異なります。たとえば、展示会では出展社や来場者数を明記し、セミナー型イベントではプログラムや講師情報を中心に構成します。
企画書テンプレートは無料で入手できるものも多く、社外への提案書や社内承認資料としても十分に活用できます。用途に応じてテンプレートを使い分けることで、作成時間を短縮しながら品質を保つことが可能です。
Wordや無料テンプレートを使った基本構成
Wordや無料のテンプレートを使う場合は、基本構成を理解した上で使いこなすことが大切です。単にフォーマットを埋めるのではなく、目的やターゲットに合わせて内容を最適化することで、より説得力のある企画書に仕上がります。
Word形式のテンプレートでは、以下のような構成が一般的です。
- 表紙(タイトル、主催社、開催日時、会場)
- 目的・背景・開催意義
- イベント概要(形式、ターゲット、参加人数、規模)
- スケジュールと体制(担当者・役割分担・準備スケジュール)
- 予算・収支計画(費用項目・会場費・人件費など)
- 宣伝・集客プラン(SNSやメディアを活用した告知方法)
- 効果測定と改善計画
テンプレートを利用する際のポイントは、全体の流れを保ちながら、関係者にとって読みやすい順序で構成することです。特に、社内で承認を得る段階では、目的と予算を明確に示すことで、スムーズな判断を促せます。
なお、自社だけで企画書をまとめることが難しい場合は、EventHubの「イベントプロデュースプラン」の活用がおすすめです。
企画立案から資料作成、会場選定、運営までを一貫してサポートし、イベントの目的達成に向けた最適なプランをご提案します。
詳細はこちら:https://eventhub.jp/exercise-conference/

イベント実施後の改善と次回への活用
イベントは開催して終わりではなく、実施後の振り返りと改善が次の成功につながります。企画書の段階から効果測定の指標(KPI)を設定しておくことで、成果を正確に評価できます。たとえば、参加者数、アンケート回答率、SNSでの反応、来場者の満足度などを定量的に把握し、どの要素が集客や成果に寄与したかを分析します。
イベント後には、関係者全員で振り返りミーティングを行い、改善点を明確にすることが重要です。その際、次の観点で整理すると効果的です。
- 企画段階:目的やターゲット設定が適切だったか
- 準備段階:スケジュール管理や役割分担に問題がなかったか
- 当日運営:スタッフや外部協力会社との連携に課題がなかったか
- 成果:設定した目標をどの程度達成できたか
- 改善策:次回に向けて体制やツールをどう強化するか
こうしたフィードバックを体系的に整理し、次回の企画書作成に反映させることで、より質の高いイベントが実現します。
企画書の振り返りと改善点の整理
振り返りでは、作成した企画書と実際の運営内容を突き合わせ、計画と実績の差を把握します。たとえば、スケジュールの遅延や予算超過が発生した場合、その原因を明確にしておくことで、次回以降のトラブルを防げます。
改善点を整理する際のポイントは次の通りです。
- データに基づいた評価:アンケート結果やKPIを基準に数値で比較する
- 社内外の意見を共有:スタッフや外部パートナーの声を集約する
- 記録の蓄積:実施報告書や資料を社内共有フォルダに保存する
- 改善策の提案:次回に向けたプランを具体的に記載する
特に、イベントマーケティングを継続的に行う企業では、過去の事例やデータを活用した改善が成果向上の鍵になります。企画書のフォーマットやテンプレートも、振り返りを踏まえて定期的に更新するとよいでしょう。
また、振り返り内容を基にしたプレゼンや社内報告は、決裁者や他部門への説明資料としても有効です。効果測定の結果を共有することで、社内全体の理解が深まり、次回以降の承認プロセスがスムーズになります。
もし、次回のイベントをより効果的に実施したい場合は、EventHubのイベントプロデュースプランを検討してみてください。経験豊富な専門チームが、目的設計から開催後の効果測定までをサポートし、成果につながるイベントを実現します。
詳しくはこちら:https://eventhub.jp/exercise-conference/
まとめ:イベント企画書を通して効果的なイベントマーケティングを実現する
イベント企画書は、単なる計画書ではなく、イベント全体の方向性を示す重要な戦略ツールといえます。目的を明確にし、ターゲットやテーマを的確に設定することで、効果的なイベント運営と成果の向上が実現します。
最後に、イベント企画書作成における重要なポイントを整理します。
- 目的・ゴールを明確にし、全体の構成に一貫性を持たせる
- 関係者が理解しやすい言葉と順序で記載する
- 予算やスケジュールを現実的かつ余裕を持って設定する
- テンプレートを活用し、フォーマットの統一と品質向上を図る
- 効果測定と振り返りを行い、次回の改善に活かす
これらの要素を押さえることで、イベントの準備から実施、そして次回への改善までを一貫した流れで進めることができます。企画書を通じて社内外の理解を深め、チーム全体で目的達成に向けた体制を整えることが、イベント成功への第一歩です。
よくあるご質問
質問:イベント企画書を作成する際、最初に決めるべき項目は何ですか?
回答:まずは目的とターゲットを明確に設定することが重要です。どのような課題を解決したいのか、どんな参加者を想定しているのかを定義しましょう。目的が定まれば、テーマ・タイトル・スケジュール・予算など他の要素も整理しやすくなります。
質問:イベント企画書のテンプレートはWordとPowerPointのどちらを使うのがよいですか?
回答:社内承認用であればWord・Googleドキュメント、プレゼンや外部共有を想定する場合はPowerPoint・Googleスライドが適しています。Word・Googleドキュメントは文章や構成の整理に優れ、PowerPoint・Googleスライドはビジュアルで全体像を伝えやすいのが特徴です。どちらを使う場合も、自社のフォーマットやロゴを反映し、統一感を保つことが大切です。
質問:予算や会場費をどの段階で企画書に盛り込むべきですか?
回答:基本的には、企画内容の方向性が固まった段階で記載します。開催規模や参加人数、使用ツール、外部協力先などが決まると、費用の見積もりがしやすくなります。余裕をもった収支計画を立てることで、リスクの把握や社内承認がスムーズになります。
質問:イベントの効果測定はどのように行えばよいですか?
回答:アンケートや参加者データ、SNSの反応などを基に定量的な指標(KPI)を設定して評価します。事前に効果測定の方法を企画書に明記しておくと、イベント後の振り返りや改善がしやすくなります。特に集客数や顧客満足度、商談化率などの指標を活用すると成果を可視化できます。
なお、イベント後の効果測定をより正確に行いたい場合は、イベントマーケティングプラットフォーム「EventHub」の活用もおすすめです。
EventHubでは、詳細な視聴ログや行動履歴をもとに顧客のエンゲージメントをリアルタイムで可視化できます。
分析ダッシュボードでは、集客状況や参加統計、リード情報のエクスポート、流入経路パラメータの分析などを一括で行えます。
また、顧客情報・メール開封履歴・交流履歴・出展ブース単位の行動ログなど、多角的なデータ分析に対応しており、データドリブンなイベントマーケティングを実現します。
詳しくはこちら:https://eventhub.jp/
質問:イベント実施中にトラブルが発生した場合、どのように対応すればよいですか?
回答:あらかじめリスクを想定し、対応フローを企画書に記載しておくことが重要です。当日はスタッフ間で迅速に情報共有できる体制を整え、担当者ごとの役割を明確にしておきましょう。トラブル発生後は、事後報告書で原因と改善策を整理し、次回の開催に反映させます。