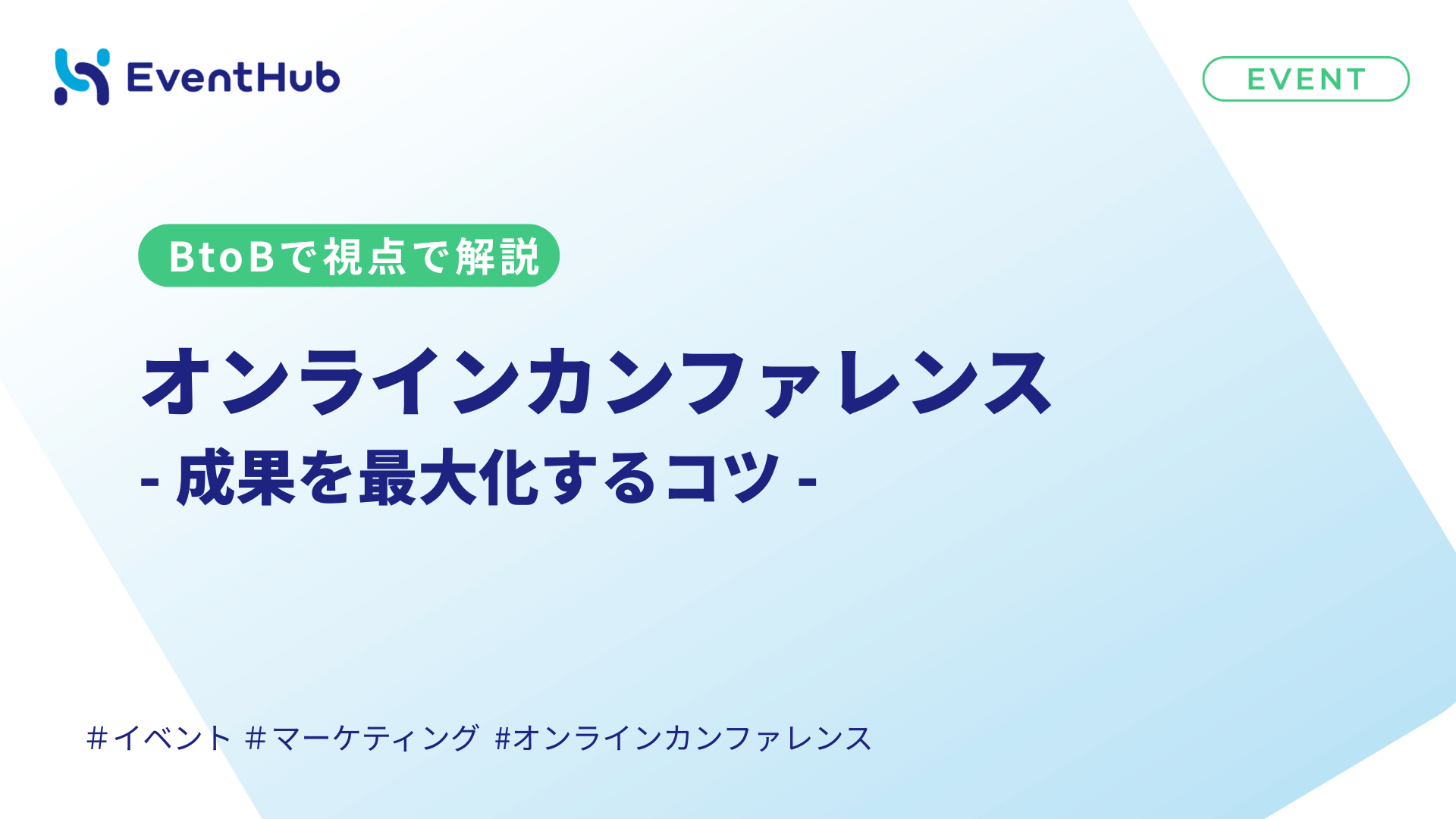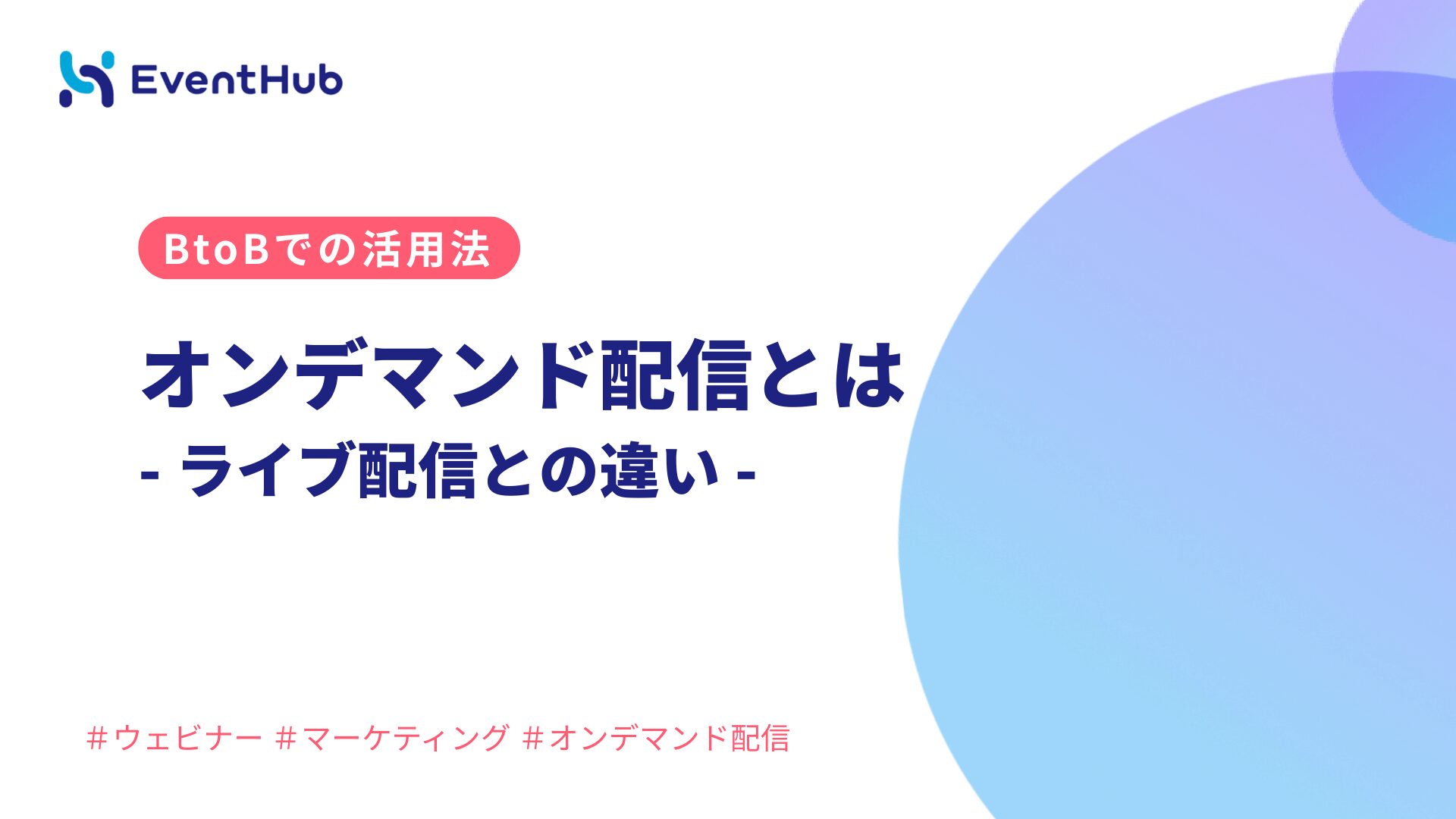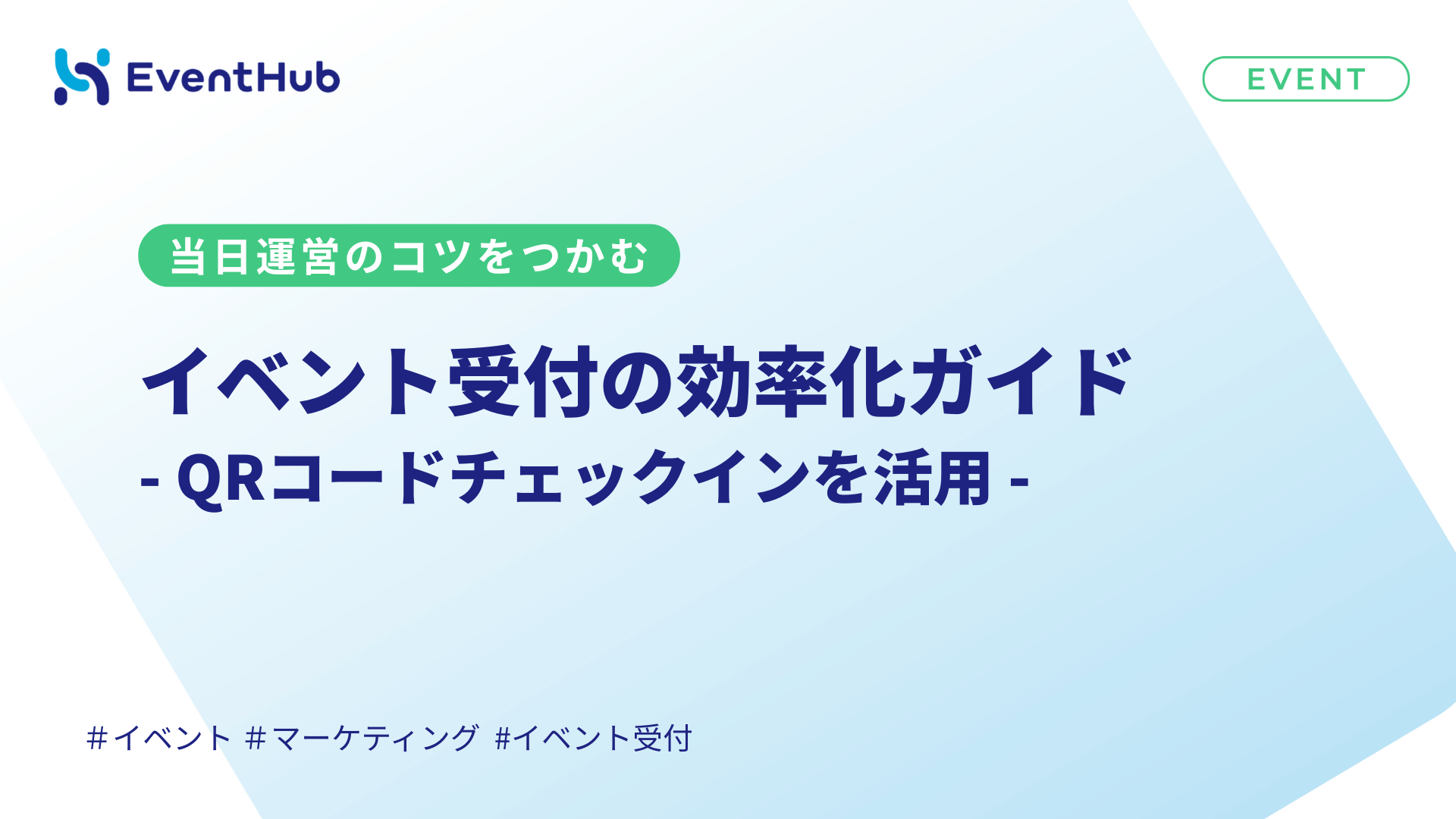今注目を集める『MICE』とは?経済メリットと国内での取組み
昨今イベントやカンファレンスの多様化に伴い、ビジネス業界において「MICE」が大いに注目を集めています。今やビジネス業界のみならず、世界各国がインバウンド振興策としてMICEの開催・誘致に注力しています。そんなタイムリーな「MICE」が何かご存じでしょうか?そこで、本記事では「MICE」とは?、MICEの動向と今後の展開について、ご紹介します
MICEとは?
MICEとは、「Meeting」「Incentive Travel」「Convention/Conference」「Exhibition/Event」の頭文字をとったもので、集客と交流、さらには経済効果やブランド発信が期待されるビジネスイベントの総称です。
もともとは観光業界の用語として使われていましたが、現在では企業のマーケティング戦略、人材開発、国際関係の構築、地域活性といった多様な分野において、MICEは“接点と体験を通じて価値を生む場”として再定義されています。その影響範囲は、従来の展示会や国際会議にとどまらず、社内イベントや報奨旅行、カンファレンスのような学術・政策の議論の場まで幅広くカバーしています。
こうした幅広さを持つMICEは、一見すると単なるイベントのように見えるかもしれませんが、実際には事業戦略、組織間連携、地域との共創など、多層的な文脈で設計・運営されるものです。その本質を理解することで、企業がMICEをどう活用しうるかの可能性が大きく広がります。
それでは、MICEを構成する4つのパートを順に見ていきましょう。
Meeting(会議、研修)
主に社内外で行われる会議や研修のことを指します。意思決定や戦略立案、人材育成など、組織の中核に関わる活動が中心です。
例:社員研修、株主総会、経営層向けセミナー
Incentive Travel(インセンティブ旅行)
営業成績や業務貢献などの成果に対して、企業が報奨として従業員や関係者に提供する旅行です。福利厚生やモチベーション向上の文脈で実施され、経費計上の対象にもなり得ます。
例:優秀社員の表彰旅行、リーダー層向け報奨ツアー
Convention/Conference(カンファレンス)
学会、国際会議、業界フォーラムなど、多国籍・多組織のステークホルダーが集まり、知見を共有し議論する場です。公共性・専門性が高く、政策形成や産業界の連携促進にも寄与します。
例:伊勢志摩サミット、IMF・世界銀行総会、業界団体の年次総会
Exhibition/Event(展示会/イベント)
製品・サービスを紹介する展示会から、文化・スポーツ・地域振興に至るまで、多様な来場者との接点を創出する広義のイベントが含まれます。ブランド訴求・新規顧客獲得において非常に重要なチャネルです。
例:東京モーターショー、EXPO 2025大阪・関西、カンヌ映画祭
MICEの急発展:開催国や地域の経済が活性化し、経済的利益を享受できるチャンス
近年、MICE市場は世界的に急成長を遂げています。グローバルなビジネス交流の活性化や、国家・都市単位での経済政策との連動により、MICEがもたらす経済的メリットは以前にも増して注目を集めています。
観光庁の調査によれば、日本国内で開催される国際MICEによる経済波及効果は年間1兆円を超える規模に達しており、宿泊、飲食、交通、設営、人材、観光といった幅広い業種に利益をもたらしています。これは開催地にとって、国際競争力を高める経済的チャンスであり、都市のブランド力強化やインフラ整備にも直結する投資効果をもたらしています。
地域レベルでは、MICE誘致によって平日・非観光シーズンの需要喚起が可能となり、地元経済の活性化に貢献します。また、地場企業への発注機会や雇用創出にもつながるため、行政・自治体にとっても持続可能な成長戦略の一環として捉えられています。
企業にとっても、MICEイベントは単なる集客手段ではありません。リアルな接点を通じて、ブランド体験を設計し、意思決定層との商談創出や関係構築を促す“高密度なマーケティングの場”として価値を持っています。
特にエンタープライズ企業においては、こうしたイベントを通じて中長期的なパイプライン育成や市場浸透を図る動きが強まりつつあります。単なる施策ではなく、全社戦略の一環としてのMICE活用が求められているのです。
とはいえ、規模が大きく、関係者も多岐にわたるMICEの運営には、多くのハードルが伴います。ツールの分散、データの煩雑化、運営負荷、効果測定の難しさ——。それらをどう乗り越えるかが、今後のMICE成功を左右する分岐点となっています。
アジアにおけるMICE開催の推進:日本はアジア1位に返り咲き!
アジア太平洋地域は、MICE市場において近年最も活発なエリアの一つです。中国、シンガポール、韓国、インドネシアなどが積極的なMICE投資を行い、インフラや人材の整備、国際的な誘致活動が加速しています。その中で、日本はアジア第2位のMICE開催国として確固たるポジションを築いています。
特に大阪は、過去にアジア太平洋地域での国際会議開催件数ランキングで1位を獲得した実績があり、世界的なMICE都市として高い評価を得ています。東京、名古屋、福岡なども各地で大型展示場やコンベンション施設を備え、自治体・DMOとの連携によって受け入れ体制を強化しています。
日本の強みは、ビジネス都市としての機能性と、観光資源や文化体験の豊富さを兼ね備えている点にあります。多言語対応、交通インフラ、安全性といった開催国としての総合力も、海外主催者から高く評価されています。
また、MICEにおけるハイブリッド開催やデジタル体験のニーズに対しても、日本のテクノロジー企業との連携により柔軟に対応可能です。これは今後のMICE競争において、大きな差別化要因となるでしょう。
アジア各国との競争が激化する中で、日本が今後さらにシェアを伸ばすためには、「質の高い開催体験」と「運営の効率化」を両立する仕組みが必要です。単に箱を用意するだけではなく、テクノロジーとホスピタリティの融合によるスマートMICEが、次の成長ドライバーとなっていくと考えられます。

今後のMICEの展開:2030年までにはアジアNO.1の国際会議開催国としての不動を地位を築く!
日本政府は、2030年までに「アジアNo.1の国際会議開催国」としての地位を確立することを国家戦略として掲げています。この目標に向け、観光庁や地方自治体を中心に、MICE誘致力の強化、人材育成、受け入れ環境の整備、そしてサステナブルな運営方針の確立など、さまざまな施策が進行中です。
また、2025年には大阪・関西万博という世界的なイベントを控えており、ここで得られる知見やネットワークは、日本のMICE推進において大きなレバレッジとなると期待されています。
一方で、日本が“真のMICE先進国”としてグローバル市場における優位性を確立するためには、「量」だけでなく「質」が問われる段階に入っています。開催体験の質、参加者満足度、持続可能性、データに基づいた運営といった要素が、新たな競争力の源泉となるでしょう。
これは企業にとっても同様です。自社でMICEを開催・活用する際にも、いかにスムーズに運営し、正確に成果を可視化できるかが問われます。ツールが分散し、参加者データがバラバラで、振り返りが困難——そんな課題を乗り越えられるかどうかが、今後の成否を分ける重要な分岐点です。
そこで注目されているのが、イベント運営を統合的に支える“オールインワン型”のプラットフォーム。次章では、MICEを成功させるために必要な「運営基盤」について詳しく見ていきます。
イベント運営を変革する「EventHub」の実力
分散・煩雑な運営を、ひとつに
MICEを戦略的に活用するうえでは「運営基盤の統合」が欠かせません。
しかし、実際には集客、受付、配信、アンケート、データ管理など、複数のツールを使い分けている企業が多く、業務の属人化や情報の分断が大きな障壁となっています。
EventHubは、そうした課題を解決する“オールインワン型イベントマネジメントプラットフォーム”です。
オンライン・オフライン・ハイブリッドのいずれにも対応し、一つの画面で参加者体験と運営業務を一元管理できる構造になっています。
EventHubが選ばれる理由
EventHubが多くの企業に選ばれている理由は、「単なるツール」ではなく、「MICEの設計思想そのものをアップデートできる仕組み」だからです。
- 初心者でも迷わない直感的なUI
- BtoBイベントに特化した構成(リード獲得、商談創出の導線が明確)
- Salesforce、Marketo、HubSpotなど外部MA/CRMとの連携によるデータ活用
- ハイブリッド開催にも対応したUX設計
こうした特徴により、マーケティング・営業・経営企画といった部署横断の取り組みにおいても、共通言語・共通基盤として活用できる点が高く評価されています。
あらゆる業種・規模に対応する柔軟性
EventHubは、エンタープライズ企業からスタートアップ、地方自治体、教育機関まで、さまざまな業種・業態・開催形式で導入実績があります。
- 小規模な社内ウェビナーから数万人規模のグローバルカンファレンスまで対応
- オンライン/オフライン/ハイブリッド問わず柔軟に設計
- 専任カスタマーサクセスによる手厚い支援体制
- 高い継続利用率(リテンション)が、ユーザー満足度の証
導入支援や、ナレッジ共有の支援も充実しており、「導入したが使いこなせない」という心配も不要です。
まずは資料から、ご覧ください
イベント運営にこんなお悩み、ありませんか?
- 担当部門やツールが分散して非効率…
- 参加者データをうまく活用できていない…
- 費用対効果がわかりづらくて、社内に説明しづらい…
EventHubなら、これらの課題をひとつのプラットフォームでまるごと解決できます。
まずは、サービスの全体像をご確認ください。