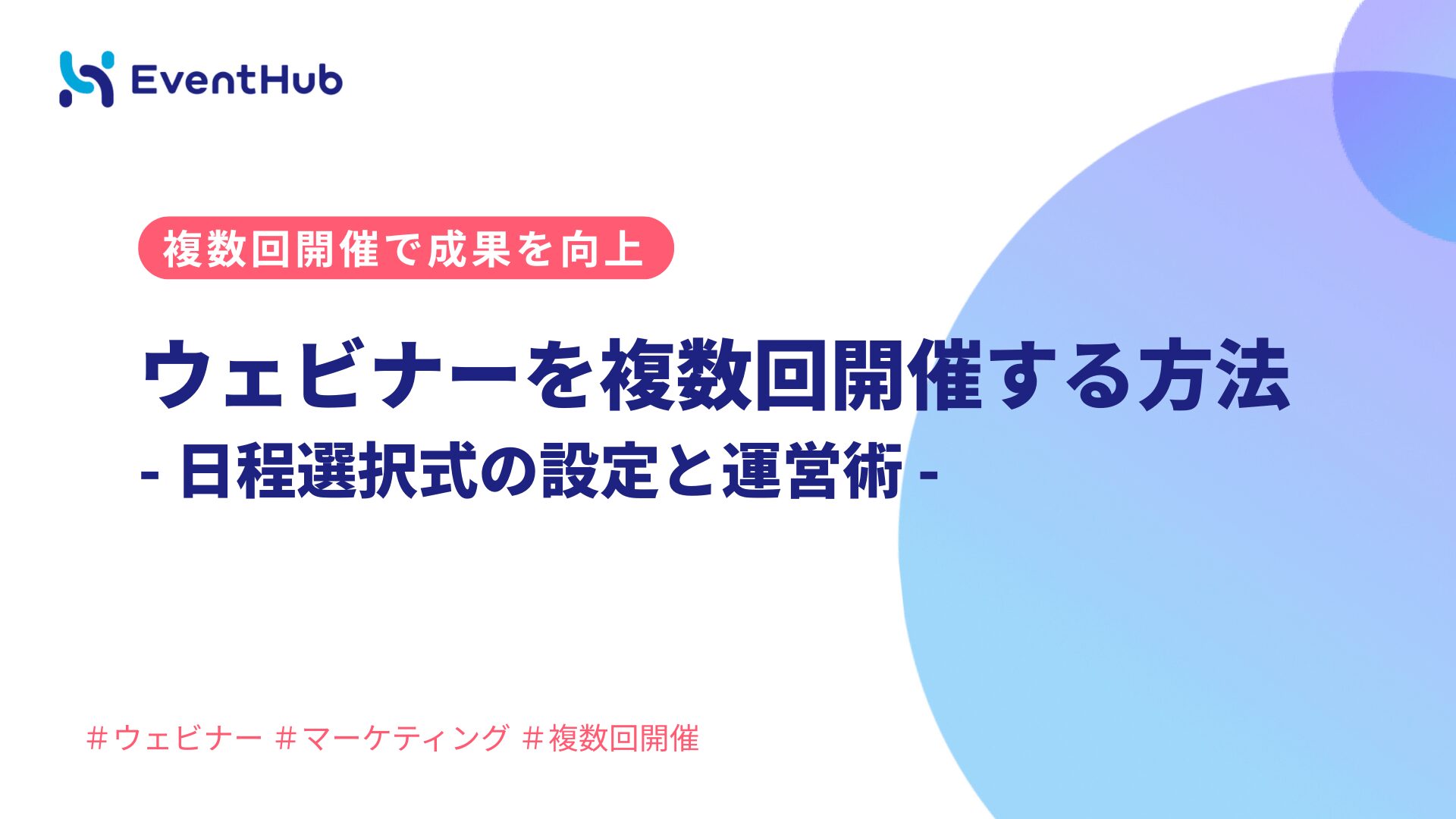オンラインカンファレンスとは?開催方法とメリット・デメリットを解説
オンラインカンファレンスは、インターネットを通じて開催されるビジネス向けの会議やセミナーのことです。近年では、働き方の多様化や業務効率化の観点から、全国・グローバルに情報を届ける手段として、多くの企業が導入しています。
オンラインカンファレンスは、対面イベントに比べて開催の自由度が高く、マーケティングや営業活動、情報発信など幅広い目的で活用されています。本記事では、その概要や開催の手順、メリット・デメリットについて詳しくご紹介します。
オンラインカンファレンスとは?特徴と種類を解説
オンラインカンファレンスは、配信プラットフォームを使って複数人に情報を届けるイベント形式の一つです。新製品の発表、業界動向の共有、パートナー向けの説明会など、用途は多岐にわたります。
物理的な制限がないため、国内外を問わず幅広い参加者に向けた情報発信が可能です。また、企業によっては、ユーザー会や展示会をオンラインで開催し、リード獲得やナーチャリングに活用するケースも増えています。
オンライン配信型カンファレンスの特徴と主な活用シーン
オンラインでの配信には、ZoomやTeamsなどの一般的な会議ツールだけでなく、イベント専用のプラットフォームが活用されることもあります。
こうしたツールでは、チャット、Q&A、アンケート、投票など、視聴者参加型の機能を備えており、単なる一方通行の配信にとどまらず、参加者とのインタラクションを生み出せるのが特徴です。
また、事前収録動画をライブ風に見せる「疑似ライブ」や、オンデマンド配信への切り替えによって、開催後の継続視聴も可能にするなど、柔軟な運用が実現できます。
ハイブリッド型オンラインカンファレンスとは?導入メリットと注意点
オンライン配信に加えて、リアル会場での参加も並行して行う「ハイブリッド型カンファレンス」も定着しつつあります。
これにより、物理的に移動が難しい層にもリーチしつつ、現地参加によるネットワーキングや体験価値も提供できるため、企業イベントの選択肢として広く活用されています。
ハイブリッドでは、参加手法の違いによるエンゲージメント格差が課題になりますが、専用プラットフォームを用いれば、現地・オンライン問わず一体感のある参加体験を設計することができます。
オンラインカンファレンスのメリット・デメリットを詳しく紹介
オンラインカンファレンスのメリットとその背景
オンラインに切り替えることで、運営の効率化を実現することができます。
コスト・時間の削減と運営の効率化
オンライン開催では、会場の手配や設備設置が不要なため、会場費や設営費といった大きな固定費を抑えることができます。また、資料を事前にダウンロード可能なツールを活用すれば、紙の印刷・配布の手間も削減可能です。
受付や誘導といった人員の配置も最小限で済むほか、主催者側も自宅やオフィスなど好きな場所から準備・運営ができるため、移動にかかるコストや時間のロスも防げます。
実際に、企画開始から開催までを1〜2ヶ月で完了した事例もあり、リアル開催に比べてスピーディかつ効率的な進行が可能です。
参加ハードルの低さと集客しやすさ
オンラインカンファレンスは、リアルイベントに比べて参加の心理的ハードルが低い点が特長です。自宅や職場からの視聴はもちろん、業務をしながらの“ながら視聴”や、時間の合うタイミングでアーカイブを視聴するなど、参加者の生活スタイルに合わせた柔軟な参加が可能です。
その結果、申込み数の増加につながりやすく、これまで接点のなかった層へのアプローチにも適しています。ただし、その分キャンセル率やイベント中の離脱率が高まる傾向もあるため、設計段階での工夫(導線設計やリマインド施策、参加メリットの明確化)が重要になります。
データ取得・分析による振り返りのしやすさ
視聴履歴、チャットログ、アンケート結果などをもとに、参加者の関心や行動を可視化し、次回の施策に活かせます。ツールによっては、参加者ごとの視聴時間や資料ダウンロード状況など、詳細なデータを取得できるため、営業やマーケティング活動との連携もスムーズです。
オンラインカンファレンスのデメリットと対策
通信トラブルのリスクと事前対策の重要性
オンライン配信では、配信者・視聴者ともに安定したインターネット環境が必要不可欠です。Wi-Fi環境下での視聴では映像や音声が途切れる、遅延するなどの問題が発生することもあります。
特に配信側は、十分な帯域幅を確保できる回線を用意し、有線接続を基本とするのが望ましいです。トラブルを想定したバックアップ配信や緊急連絡手段の用意も検討すべきポイントです。
なお、配信に特化したプラットフォームを利用すれば、ネットワーク負荷を抑える仕組みや、万一に備えた運用支援機能を備えているケースもあります。
視聴者の反応・集中力をどう把握するか
対面イベントと違い、オンラインでは参加者の表情や空気感を把握しにくく、登壇者側が盛り上がりや反応を掴みにくいという課題があります。
このギャップを埋めるには、チャット欄でのリアクション促進やライブQ&A機能の活用が有効です。最近では、視聴ログやアンケート結果を自動で集計し、イベント後の分析に活かせる機能を備えたプラットフォームも増えています。EventHubのように、視聴者の行動データを可視化し、セールスチームとスムーズに連携できる環境を整えておくことで、こうした課題にも対応しやすくなります。
- チャット機能
- オンライン名刺交換
- 投票機能
- 交流機能
- Webミーティング機能
- アンケート機能
- 顧客管理機能
などの機能により、双方向性の高いカンファレンスを開催することが可能です。オンライン開催のデメリットを払拭できる機能が充実したツールを選定することで、オンラインの良さだけを活かしたカンファレンス開催が可能となります。
オンラインカンファレンスの開催方法と成功のポイント
 オンラインカンファレンスは、以下の5ステップを軸に開催されます。
オンラインカンファレンスは、以下の5ステップを軸に開催されます。
それぞれの工程でポイントを押さえることで、参加者満足度と運営効率を両立できます。
1.イベントの目的設定とKPI設計
まずは、「このイベントで何を達成したいのか」を明確にすることが重要です。新規リードの獲得、見込み顧客の育成、社内外への情報共有など、目的によって内容や構成が大きく変わってきます。
加えて、「申込数」「参加率」「アンケート回収率」など、定量的なKPIを設定しておくと、効果測定と振り返りがスムーズになります。
2.ツール選びと配信体制の構築方法
配信ツールは、視聴のしやすさ、インタラクティブ機能、ログ取得の有無などを基準に選定します。視聴者にアプリのインストールを求めないブラウザ完結型のツールは、参加率向上にもつながります。
あわせて、運営サイドのリソースに応じて、外部パートナーや配信サポート付きのサービスを検討するのも有効です。たとえばEventHubのように、配信から参加登録・アンケート回収・データ連携までワンストップで対応できるプラットフォームもあります。
3.登壇者・コンテンツ設計のコツ
視聴者が興味を持つテーマ設定、講演者のブッキング、スライドや台本の作成などを進めます。
登壇者には「オンライン向けの話し方」や「間の取り方」に慣れてもらうため、リハーサルを実施するのがおすすめです。
また、長尺コンテンツは集中力が続きにくいため、1セッション20〜30分程度を目安に構成し、チャットでの呼びかけや質問受付を盛り込むと、視聴体験が向上します。
4.集客・リマインドの流れと改善ポイント
イベントLPの作成後、既存顧客への一斉メール配信や、SNS・広告での告知を行います。申込者へのフォロー(受付完了通知、前日・当日リマインドメール)も忘れずに。
集客段階でのコンテンツの打ち出し方(例:「業界動向がわかる」「成功事例を紹介」など)によって、参加の動機付けが大きく変わります。
5.配信当日の対応とイベント後のフォロー体制
配信は、安定したインターネット環境・冗長構成の確認が基本です。トラブル時の対応連絡先やマニュアルも準備しておくと安心です。
イベント後は、アンケート結果や行動ログをもとに、参加者ごとの関心に応じたフォローを行うことで、商談化やリード育成につながります。
この部分も一気通貫で対応可能なツールを選ぶと、運営チームの負担を大きく軽減できます。
まとめ: オンラインカンファレンスの課題はツールと設計で解決可能
オンラインカンファレンスは、従来のイベントに比べて高い柔軟性と効率性を持ち、目的に応じた成果創出が期待できる手法です。
一方で、運営や参加者体験に関する課題もあるため、ツールの機能や設計の工夫でカバーすることが成功の鍵となります。
目的を明確にし、参加者の満足と自社の成果が両立できるイベント運営を目指しましょう。