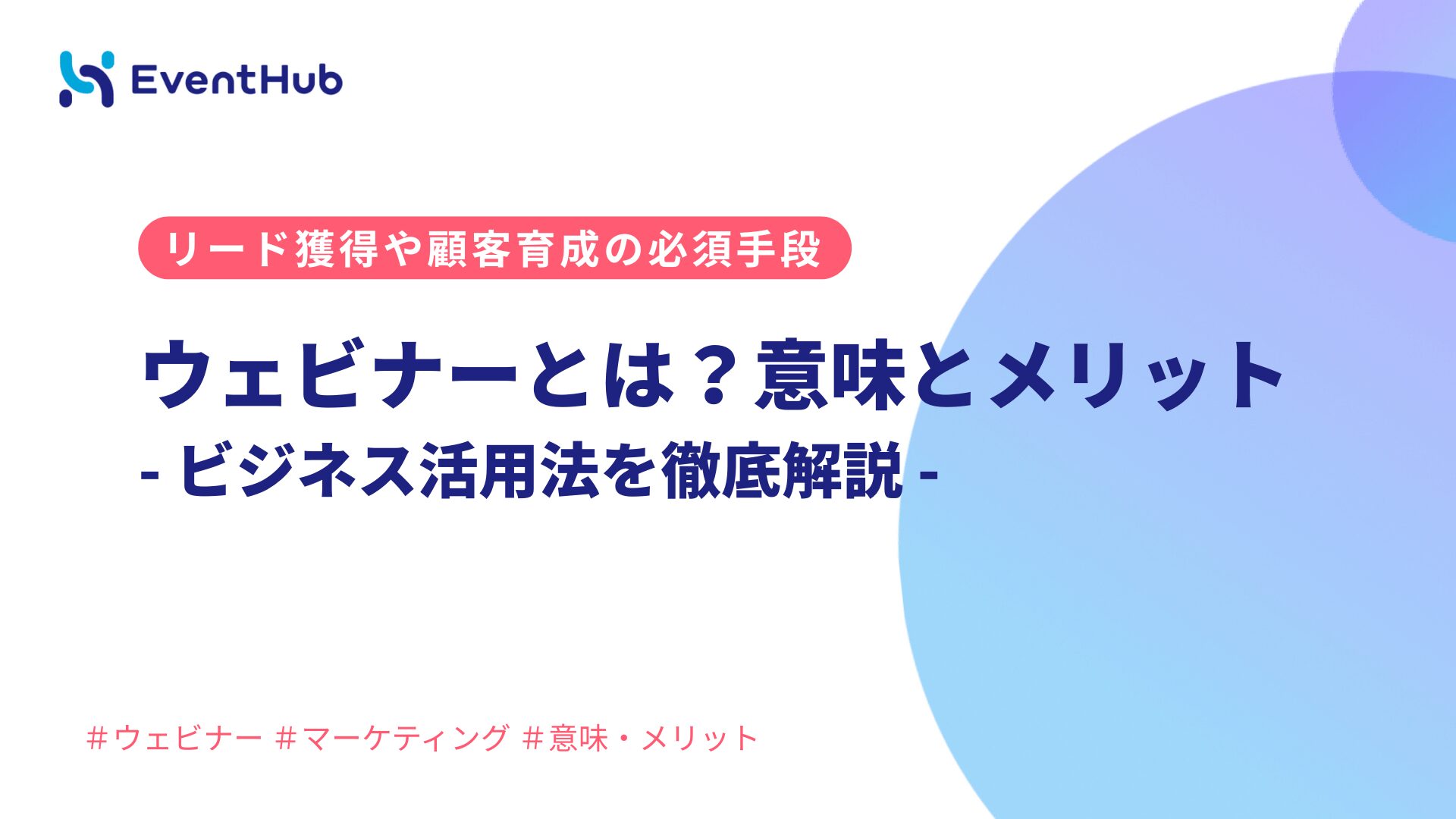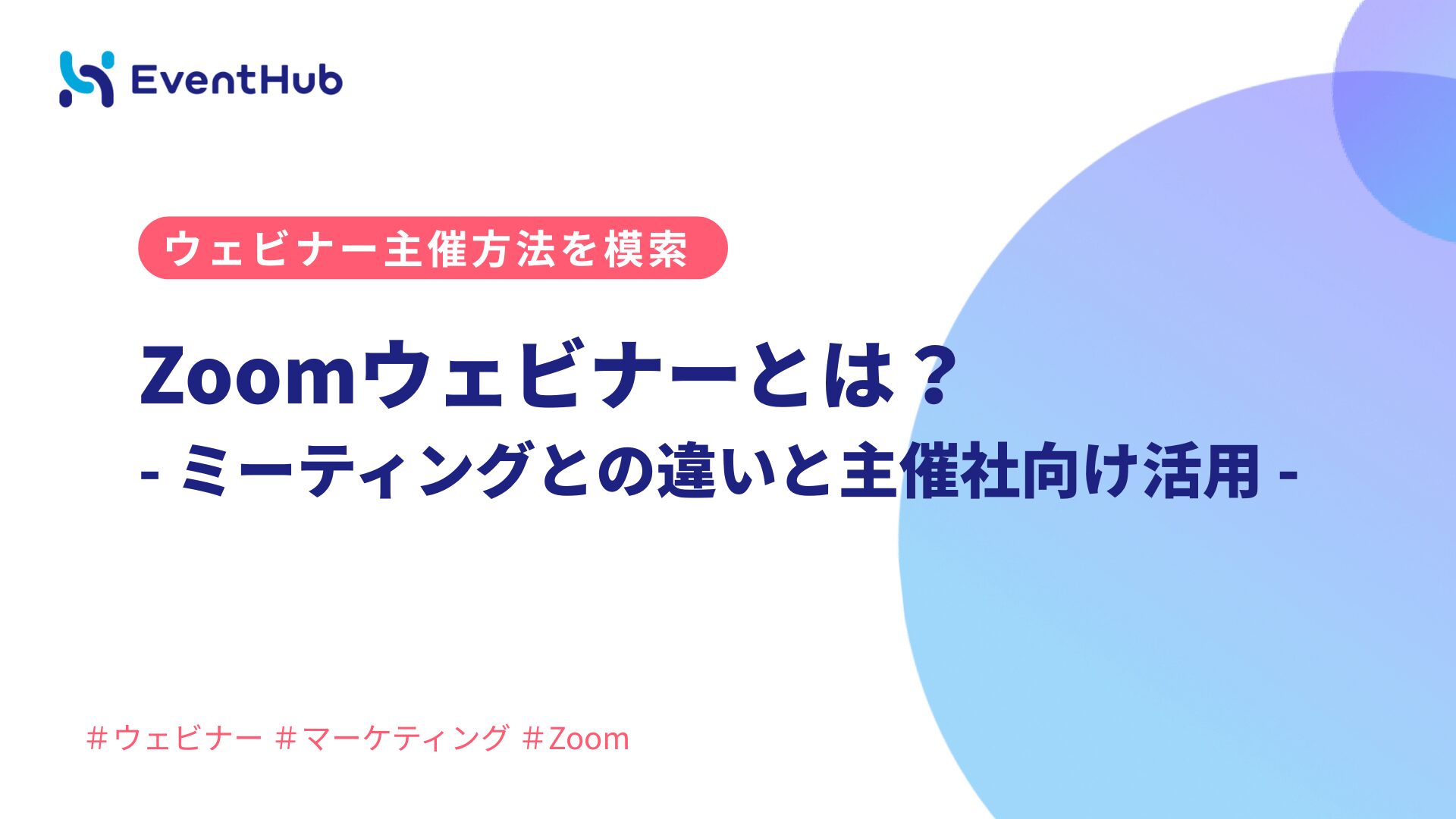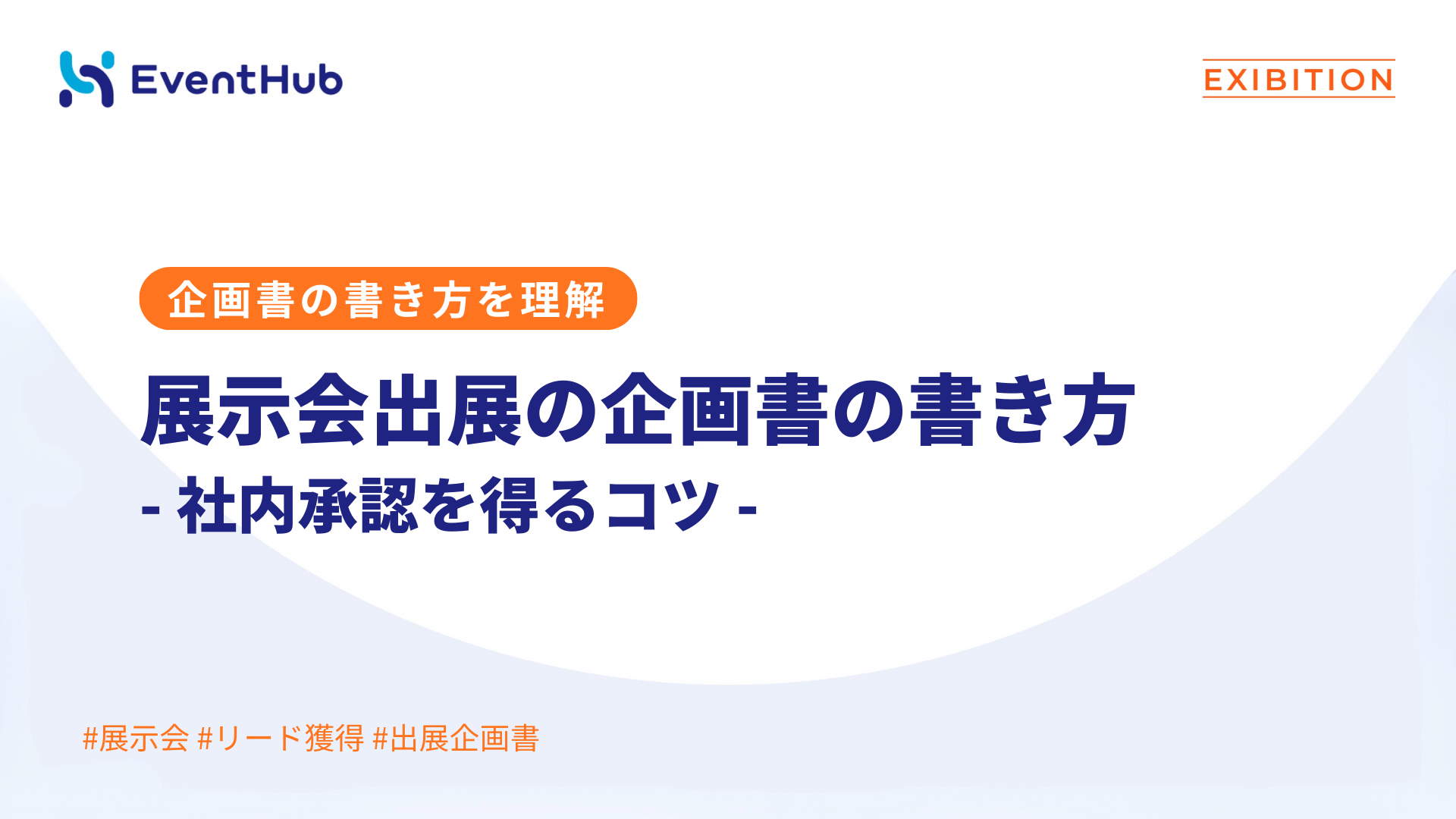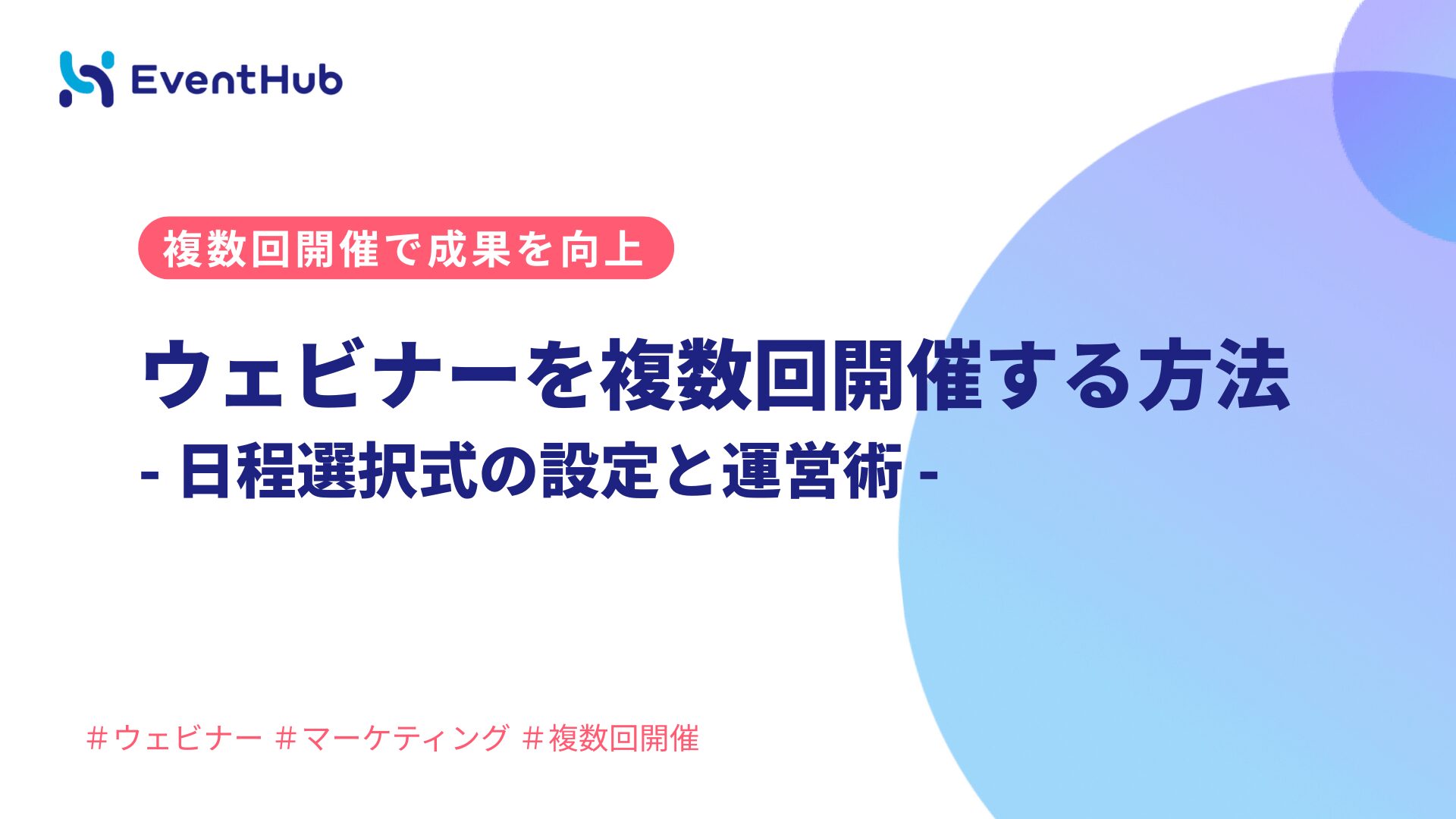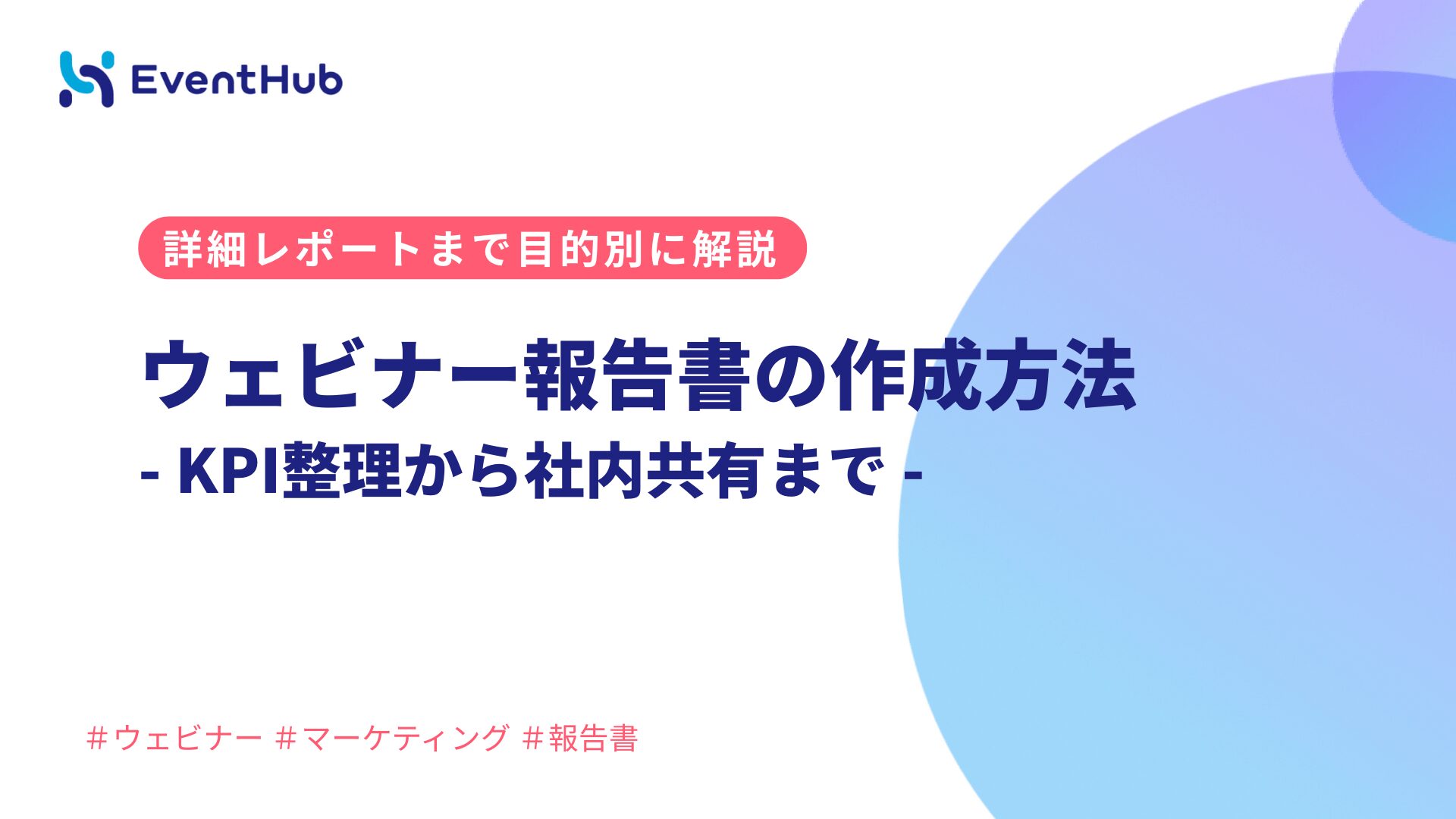イベントマーケティングとは?手法・メリット・事例・Webの活用も徹底解説
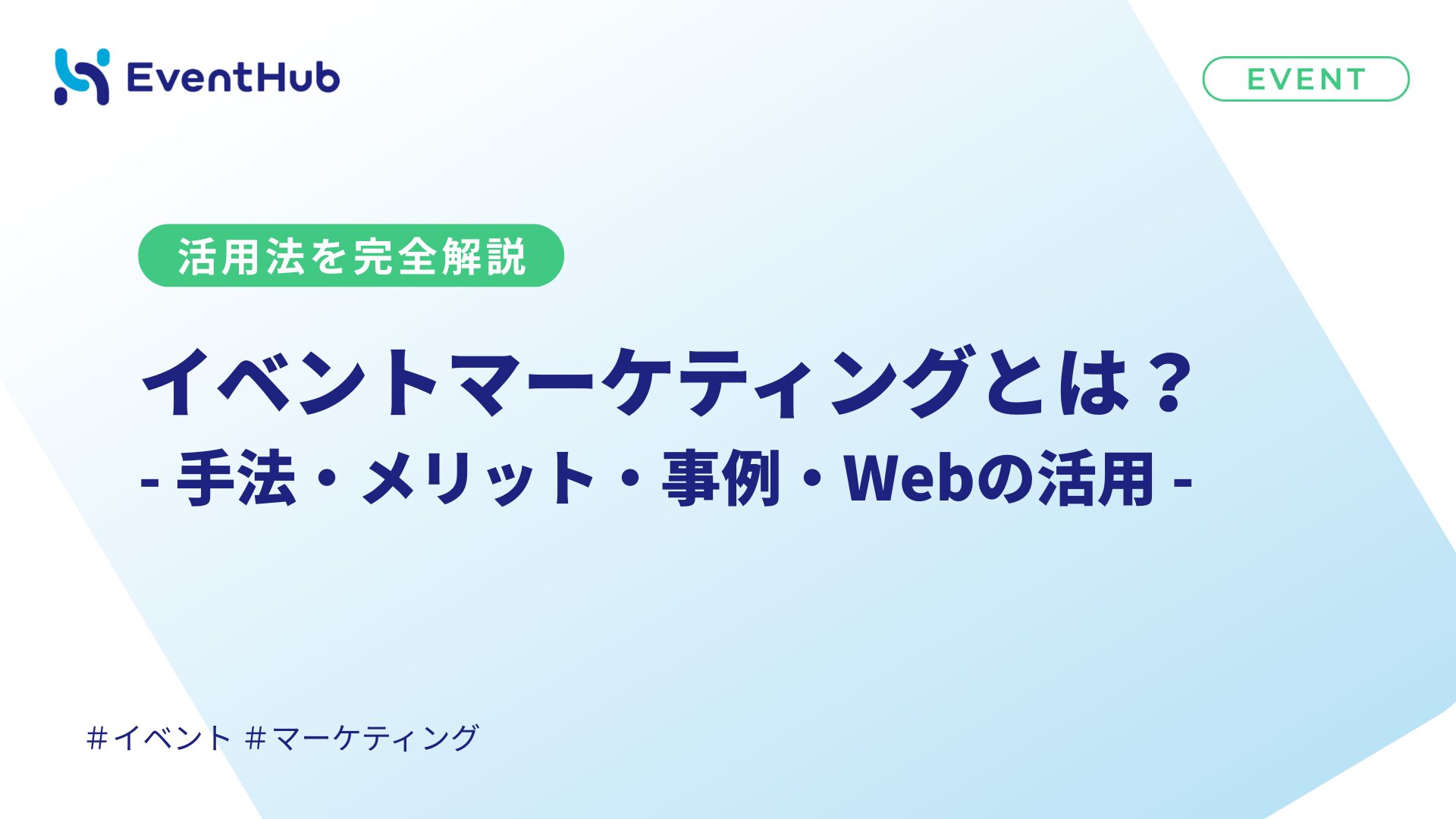
イベントマーケティングは、企業が製品やサービスの認知拡大、顧客との接点創出、リード獲得を目的として行う重要なマーケティング手法の一つです。BtoBビジネスにおいては、展示会やセミナー、交流会、ウェビナーなどを活用し、参加者との関係性を築くことが営業活動や商談の起点となるケースも少なくありません。
昨今では、リアル開催だけでなくオンラインやハイブリッド形式のイベントも増加しており、WebサイトやSNSと連携した集客施策の重要性が高まっています。また、イベントの実施後には参加者へのアフターフォローやデータ分析を通じた改善活動が求められ、マーケターには幅広い視点とノウハウが必要とされています。
本記事では、イベントマーケティングの基本的な定義から、主な手法や種類、企画・運営のポイント、Web活用による集客の最大化まで、企業が成果を上げるために押さえるべき実践的な情報を徹底的に解説していきます。
イベントマーケティングの基本を理解する
イベントマーケティングは、企業が顧客との接点を創出し、関係性を構築・強化するためのマーケティング活動の一つです。リアルな展示会やセミナー、オンラインイベント、交流会など、形式は多様化しており、目的やターゲットに応じて柔軟に設計されます。
特にBtoB分野では、新規見込み顧客との出会いだけでなく、既存顧客との関係維持・深耕、さらには商談機会の創出にも大きく寄与します。単なるプロモーション施策にとどまらず、営業活動の起点や、ブランドの信頼性を高める活動としても位置づけられています。
イベントを通じて得られるリアルな反応は、製品・サービス改善や、新たなニーズの発掘にもつながります。企業が戦略的にイベントを企画・実施することで、マーケティング活動全体の成果を押し上げることが可能となります。
イベントマーケティングとは何か?定義とその重要性を解説
イベントマーケティングとは、企業や団体が主催・出展・協賛などの形でイベントを実施し、来場者や参加者とのコミュニケーションを通じて、認知の向上やリードの獲得、商談の創出、ブランド価値の向上を図る活動です。
この手法の重要性は、他のマーケティング施策と比較して「直接的な接触」が可能である点にあります。展示会やカンファレンス、体験型イベントなどでは、来場者が実際に製品に触れたり、担当者と対話したりすることで、深い関心や購買意欲が生まれやすくなります。
また、デジタル施策では得られないリアルな反応や、会場の空気感を通じたブランドイメージの伝達も強みです。さらに、WebやSNSと連動することで、イベント前後の情報発信やフォローアップも可能となり、長期的な関係性の構築にもつながります。
BtoB領域でのイベントマーケティングの役割と価値
BtoB企業にとって、イベントマーケティングは単なる販促活動ではなく、営業・マーケティング活動全体を支える戦略的な手段です。BtoB商材は一般的に購買プロセスが長く、複数の関係者が意思決定に関わるため、製品やサービスの価値を直接伝え、相手の理解を深める機会が必要です。
その点、展示会やセミナー、カンファレンスなどのイベントは、顧客と深く関わる絶好の機会になります。来場者が製品を体験したり、担当者から直接説明を受けたりすることで、信頼感や関心が高まり、購買意欲の育成につながります。また、イベントを通じて得た名刺やアンケートなどの情報は、後続の営業活動やマーケティング施策において重要な資産となります。
さらに、BtoB分野では、イベントを通じてパートナー企業や業界関係者とのネットワークを広げ、ブランディングや共同プロモーションのきっかけを作ることも期待されます。リアル・オンラインを問わず、適切に設計されたイベントは、認知度を高めることから商談のきっかけづくり、そして顧客との関係を深めるところまで、一貫して後押ししてくれる大切なマーケティング手段といえるでしょう。
顧客獲得や認知拡大におけるイベント活用のメリット
イベントは、新たな顧客との接点を創出し、製品やサービスの価値を直接伝えることで、リード獲得や認知度の向上に大きく寄与します。特に展示会や体験型イベントでは、興味・関心を持つ見込み顧客と直接対話する機会が得られ、購買意欲の高い層への効果的なアプローチが可能となります。
また、イベントに参加した来場者は、通常の広告やWeb施策よりも深い印象を持ちやすく、ブランドのイメージ形成にも貢献します。ターゲットに合わせたテーマ設計や、ブースの設計、プレゼンテーション内容などを工夫することで、イベントそのものが強力なプロモーションツールとなります。
さらに、イベント実施中や実施後のSNS発信、動画配信、メディア露出などにより、直接の来場者以外にも広く情報を届けることが可能です。認知の拡大だけでなく、既存顧客との関係強化や、紹介による新たな顧客の創出といった波及効果も期待できます。
イベントマーケティングの主な手法と種類
イベントマーケティングにおいては、目的やターゲットに応じて多様な形式のイベントが活用されます。形式ごとの特性を理解し、自社に適した方法を選定することが重要です。
主なイベント形式には、展示会、セミナー、体験型イベント、交流会、ウェビナー、カンファレンスなどがあります。これらはそれぞれ特定の課題解決やターゲットとの関係性構築において有効であり、リアル・オンラインの両面からアプローチが可能です。
たとえば、リード獲得を主目的とする場合は展示会、深い理解や啓発を重視する場合はセミナー、関係性構築には交流会や懇親イベントが適しています。また、オンライン形式を取り入れることで、地域的な制限を超えて、幅広いターゲットに届けられるようになります。
ここでは、代表的なイベント形式について、その特徴や活用のポイントを解説します。
展示会・セミナー・交流会などイベント形式ごとの特徴
展示会は、不特定多数の来場者と接点を持ち、短期間で多くのリードを獲得できるイベント形式です。ブース設計や資料配布の工夫により、自社商材の魅力を効果的に伝えることができます。新製品のPRや市場の反応を把握する機会としても優れています。
セミナーは、特定のテーマに関心を持つ参加者を集めて知識を提供する形式で、業界動向や事例の紹介、自社の専門性アピールに最適です。オンラインでの配信も多くなり、参加ハードルが下がることで幅広い層への情報提供が可能です。
交流会は、来場者同士のつながりを促進しながら、企業担当者との自然なコミュニケーションを生み出せるイベントです。参加者の本音を引き出したり、信頼関係の構築に役立つため、営業活動にも波及効果があります。
これらの形式は単独で実施するだけでなく、複数を組み合わせることで相乗効果を生み、より高い成果を狙うことも可能です。
体験型イベントの魅力とエンゲージメントの強化
体験型イベントは、参加者が製品やサービスを実際に「体験」することで、企業とのつながりを深め、強い印象を与えることができる手法です。五感を使って直接触れることができる体験は、参加者の記憶にも残りやすく、エンゲージメントの強化に非常に効果的です。
たとえば、自社商材を実際に試せるデモ体験会や、製品を使ったワークショップなどが該当します。こうした形式は、単なる説明やパンフレットでは伝えきれない価値や特徴を、直感的に伝えることができ、参加者の関心や理解を高める上で大きな力を発揮します。
また、体験型イベントでは、参加者の行動や反応を直接観察できるため、マーケティング活動における定性的なインサイトの獲得にもつながります。これらの情報は、今後の製品開発や顧客育成戦略の立案にも活用できます。
さらに、SNSでの投稿や動画共有を促す施策を組み合わせることで、参加者の行動を通じてイベントの価値が拡散され、来場していない層への認知拡大にもつながります。リアルとデジタルの融合が可能な体験型イベントは、マーケティング施策として今後ますます重要性を増していくと考えられます。
オンライン・ハイブリッド開催の可能性と支援ツール
近年のデジタルシフトにより、イベントの開催形式は大きく変化しています。特にオンライン開催とハイブリッド開催(リアルとオンラインの併用)は、多様なニーズに応える新しい選択肢として定着しつつあります。物理的な制約を超えて広範囲のターゲットにリーチできる点が、大きなメリットです。
オンラインイベントは、配信ツールを使って場所を選ばずに参加できるため、移動時間やコストの削減が可能です。録画配信やアーカイブを通じた情報提供も柔軟で、参加者の状況に合わせた視聴体験を設計できます。ウェビナーやオンラインセミナーなどは、その代表的な形式です。
一方で、リアルな体験や交流を重視したい場合には、オンラインとリアルの融合であるハイブリッド型が効果的です。来場者には直接の体験価値を提供しつつ、遠隔地の見込み顧客にも情報を届けられるため、効率的に広範なリードを獲得できます。
このような開催形式の運営を支援するためのツールも充実しています。イベント管理プラットフォーム、来場者のデータ計測ツール、SNS連携機能、アンケート・フィードバック収集機能など、目的に応じて適切なツールを選択することが重要です。
オンラインやハイブリッド開催は、今後のマーケティング戦略において欠かせない要素となっており、予算や目標、ターゲットの属性に応じた柔軟な設計が求められます。
オンラインイベントを開催された企業様の事例を参考にされる場合はこちらの資料をダウンロードください。アドビ株式会社、株式会社ニューズピックス、株式会社Sansan等のオンラインイベントの開催事例を資料でご紹介しています。

ハイブリッドイベントの開催ノウハウについてもっと詳細にお知りになりたい場合はこちらの資料をダウンロードください。

成功するイベントの企画と準備
イベントマーケティングを成功に導くためには、実施前の企画と準備がとても重要です。行き当たりばったりの開催ではなく、明確な目標設定と戦略的な設計を行うことで、集客・顧客獲得・商談創出といった成果につながります。
まず、目的の明確化がスタート地点となります。製品・サービスの認知向上を目指すのか、新規リードの獲得を狙うのか、既存顧客との関係強化なのかによって、イベントの種類や内容、集客方法が大きく変わります。さらに、開催の形式(リアル/オンライン/ハイブリッド)や規模感、会場の選定も初期段階で整理すべきポイントです。
目的設定とターゲットユーザーの明確化方法
イベントの企画で最初に行うべきは、マーケティング上の目的を言語化することです。「製品認知の向上」「見込み顧客との接点創出」「商談化の促進」「既存顧客との関係強化」など、目的が明確であればあるほど、その後の設計がスムーズになります。
次に重要なのがターゲット設定です。自社の商材に興味を持ちそうなユーザー像を描き、業種、役職、課題、検討段階などを細かく分類します。BtoBの場合は、意思決定プロセスが複雑なため、関係者それぞれのニーズを考慮する必要があります。
ターゲットが明確になれば、その関心を引くテーマやコンテンツを設計しやすくなります。たとえば、課題解決を前提にしたセッションや、導入事例を交えた講演などは、高い訴求力を持ちます。また、案内方法もターゲットごとに最適化することで、集客効率が大きく向上します。
イベント企画書・進行表・資料の作成ノウハウ
イベントを円滑に進行させるためには、事前にしっかりとした企画書・進行表・配布資料などを作成することが不可欠です。これらの資料は、関係者間の認識を統一し、当日のトラブル回避や業務効率の向上に大きく貢献します。
まず企画書には、イベントの概要、開催目的、ターゲット層、想定来場者数、会場またはオンラインプラットフォームの選定理由、実施形式、想定される成果などを記載します。これにより、社内外の関係者と目標や期待値を共有しやすくなります。
次に進行表では、当日のスケジュールを時間単位で細かく設定し、受付開始、開会挨拶、講演、デモ、Q&A、クロージングといった各セクションの流れを可視化します。登壇者やスタッフが迷うことなく動けるよう、詳細なタスクと担当者の明記も必要です。
また、参加者に配布する資料は、製品情報やサービス内容だけでなく、講演内容のスライドや事例紹介、会場案内、アンケートなど、多面的な情報を網羅するように構成することが望まれます。デザインにも気を配り、ブランドイメージに沿った見せ方を意識することで、参加者の印象や理解度が向上します。
これらの資料をきちんと用意することで、イベントの進行がスムーズになり、参加者満足度の向上と主催者側の業務効率化の両立が実現します。
出展企業との連携とソリューション提案型ブースの工夫
展示会やカンファレンスなどの大型イベントでは、出展企業との連携がイベント全体の成功に直結します。単なるスペース提供ではなく、双方にとって価値ある機会を創出するには、主催者と出展者の間で目的や期待値を共有し、協力体制を築くことが欠かせません。
特に注目されているのが、「ソリューション提案型ブース」の設計です。これは、単に製品を展示するのではなく、来場者が抱える課題に対して、自社の製品・サービスがどのように貢献できるかを、具体的な事例やデモンストレーションを通じて伝える手法です。
例えば、業界特有の悩みを取り上げ、それに対する解決策を体験型で紹介する構成にすることで、ブース訪問者の関心を惹きつけやすくなります。さらに、課題解決の流れを明確に伝える構成にすることで、商談化率を高めることも可能です。
出展企業との連携においては、事前の情報共有が非常に重要です。主催者は、来場者の属性や関心傾向などを出展企業に提供し、最適な訴求ができるよう支援すべきです。また、資料の統一フォーマット、ロゴ使用のルール、プレゼンテーションのタイムスロット調整など、細かな運営ルールを整備することが、トラブル防止にもつながります。
ソリューション提案型のアプローチを採用することで、出展企業はより多くの見込み顧客と深い対話を持ちやすくなり、イベント全体としての満足度や成果が向上します。
イベント集客とSNS・Web連携の効果的な活用法
イベントを成功させる上で、効率的に集客できるかどうかはとても重要です。近年では、従来のDMや電話営業に加え、SNSやWebサイトを活用した集客施策が主流となっており、オンライン・オフラインを問わず、どのような施策を選択するかで、イベントの集客力が大きく左右されます。
SNSは、情報拡散力に優れており、開催告知からイベント当日の実況、実施後のフォローアップまで、多段階での活用が可能です。一方、Webサイトでは、詳細なイベント情報の掲載や申し込みフォームの設置など、ユーザーのアクションを促す設計が求められます。
SNS施策とWebサイト連携による集客の最大化
まず、SNSでの集客を成功させるためには、対象となるユーザーの行動パターンに合わせたメディア選定が重要です。例えば、ビジネスパーソンが多く利用するFacebookやX(旧Twitter)は、BtoBイベントに適したプラットフォームです。投稿のタイミング、内容、ハッシュタグ設計などを工夫することで、より多くの対象層に情報を届けることができます。
また、SNS広告の活用も有効です。関心層や職種などをターゲティングして、申し込みページへの導線を確保することで、効率的にリードを獲得できます。イベント用に専用アカウントを開設したり、複数回にわたる投稿でイベントへの期待感を醸成する手法も効果的です。
一方、Webサイトは集客施策のハブとして機能させる必要があります。イベント概要、プログラム内容、講演者紹介、申し込みフォームなどを一元的に掲載し、ユーザーがスムーズに行動できる導線を整備します。さらに、申し込み後のサンクスページに資料請求やメールマガジン登録の導線を組み込むことで、リード育成につなげることも可能です。
SNSとWebの役割を明確に分け、戦略的に連携させることで、限られた期間でも効率よく集客することが可能になります。
見込み顧客へのアプローチとエンゲージメント施策
イベントは、見込み顧客との初期接点を作るだけでなく、その後の関係構築を通じて、商談や購買へと導くプロセスの起点になります。そのため、イベント開催前から開催後まで、一貫したアプローチ戦略とエンゲージメント施策が求められます。
まず、開催前の段階では、見込み顧客の関心を引くために、それぞれに合わせた案内やコンテンツ提供が重要です。過去の接点情報や業種、役職に基づいたメール配信や、業界特化型の告知資料を活用することで、より高い参加意欲を引き出すことができます。また、Web広告やSNSでも、リターゲティング広告や動画による製品紹介などが効果的です。
イベント当日は、参加者とのコミュニケーションを重視し、質の高い体験を提供することがエンゲージメント強化につながります。リアルであればスタッフによる丁寧な説明や、体験コーナー、対話のしやすいブース設計が有効です。オンラインであれば、チャット機能やQ&Aセッションなど、双方向の接点を意識した設計が求められます。
開催後は、必ずアフターフォローを行いましょう。アンケートの収集や、イベントで配布した資料の再送付、関連製品の紹介メールなど、タイミングを逃さずに継続的なコミュニケーションを取ることで、関係性を深めることが可能です。また、営業部門と連携し、ホットリードへの迅速なアプローチを行う体制も重要です。
イベント前後のフォローアップ体制を強化する方法
イベントマーケティングでは、開催そのものよりも「前後のフォローアップ」が成果を大きく左右します。イベント当日に得られた接点を活かし、参加者との関係を深め、商談化やリード育成へとつなげる体制を整えることが非常に重要です。
イベント前の段階では、招待メールの送信、リマインドの案内、参加申込者への情報提供などを通じて、参加率を高めるための働きかけが必要です。開催直前のタイミングで、会場案内やタイムテーブルの送付、講演内容の予告などを行うと、参加者のモチベーションも上がり、当日の積極的な行動につながることもあります。
一方、イベント後には、迅速なフォローが求められます。参加のお礼メールをはじめ、アンケートの配信、講演資料や動画の共有、関連製品・サービスの案内などをタイムリーに行うことで、参加者の関心を維持しやすくなります。また、特に関心度の高かった参加者には、個別に営業担当から連絡を行い、具体的な商談へとつなげるべきです。
このプロセスで重要なのは、営業部門とマーケティング部門の連携です。イベントで得た名刺情報やアンケートデータを速やかにCRMやMAツールに取り込み、スコアリングやセグメント分けを行い、最適なタイミングで次のアクションに移せるように設計します。
さらに、イベントの反響や課題点を社内で共有し、次回に活かす仕組みを作ることで、フォローアップ体制は継続的に改善されていきます。単なる「対応」ではなく、「戦略的な仕組み」としてのフォローアップ体制を築くことが、長期的な成果創出につながります。
成果を上げるイベント運営と効果測定
イベント当日の運営は、企業の信頼感やブランドイメージを左右します。どれだけ入念な準備をしても、当日の運営がスムーズでなければ、参加者に不安や不満を与えてしまい、ビジネスチャンスを逃す可能性もあります。
また、単なる「イベントの実施」ではなく、参加者が有意義な時間を過ごし、情報を得られたと感じることが、顧客満足度や成果の最大化に直結します。このセクションでは、当日運営のポイントと、参加者体験の最適化について詳しく解説します。
イベント当日の運営体制と参加者体験の最適化
イベント当日は、あらゆるトラブルを想定しながら、スムーズな進行を支える運営体制の構築が必要です。受付からセッションの進行、ブース対応、会場案内、質疑応答対応、終了後の誘導まで、すべての流れにおいて「混乱を生まない設計」が求められます。
具体的には、以下のような体制を整えることが重要です。
- 役割分担を明確にしたスタッフ配置
- 受付・誘導の動線設計
- タイムスケジュールに基づいた進行管理
- トラブル時の対応フローと責任者の明確化
- 来場者への分かりやすい案内資料やサイン表示の用意
また、参加者の体験価値を高めるためには「快適さ」「分かりやすさ」「記憶に残ること」の3つが重要なポイントとなります。たとえば、資料の配布や説明方法に工夫を加えたり、講演内容にストーリー性を持たせたりすることで、来場者の理解と記憶への定着を高めることができます。
さらに、休憩スペースやネットワーキングエリアの設計も、満足度を左右する要因の一つです。参加者が自然に交流できるような空間を用意することで、イベント自体の価値が高まり、次回以降の参加意欲や企業への好感度にもつながります。
成果指標の設定とデータ分析による改善プロセス
イベントマーケティングにおいては、「やりっぱなし」で終わらせず、明確な成果指標(KPI)に基づいた評価と改善を繰り返すことが、マーケティング活動全体の質を高めます。実施後の振り返りがなければ、どれだけ集客できたか、参加者にどのような影響を与えられたか、次につなげるべき要素は何かといった本質的な問いに答えることができません。
まず、イベントの目的に応じて、適切なKPIを設定する必要があります。以下は代表的な指標の例です。
- 登録者数・実参加者数(来場率)
- リード獲得件数(質と量)
- 商談化件数・売上への貢献度
- アンケートによる満足度スコア
- WebアクセスやSNSでの言及数
- 資料ダウンロード数や動画再生回数
これらの定量データに加え、アンケートの自由回答や当日の現場スタッフのフィードバックなど、定性的な情報も合わせて分析することで、より深いインサイトが得られます。
データ分析では、MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRMを活用し、イベントで得た見込み顧客情報をセグメント化・スコアリングすることが有効です。どのような属性の参加者が反応を示したのか、どの施策が集客や興味喚起に効果的だったかを把握し、次回イベントの企画・設計に反映させていきます。
また、施策単体ではなく、「参加から商談、受注までのプロセス」に対して、イベントがどの段階でどのような貢献をしたかを可視化することで、経営層や営業部門との連携もスムーズになります。
実施後のマーケティング施策の展開
イベントは開催当日で終わるものではありません。むしろ、イベント後にどのようなマーケティング施策を展開するかが、成果を最大化するための重要なポイントとなります。実施後のアクションを戦略的に設計することで、イベントが一過性の活動ではなく、継続的なビジネス成長につながる資産となります。
まず、イベントで獲得したリードに対しては、すぐにアプローチを開始することが肝心です。参加者の関心度や行動履歴に基づいて、セグメントを分けた上で、メールや電話によるフォロー、資料送付、個別商談の打診などを展開していきます。反応の高いリードは営業部門へ速やかに引き継ぎ、最適なタイミングを逃さない対応が求められます。
また、イベントで使用したコンテンツを再活用することも有効です。講演動画のアーカイブ配信、スライド資料のダウンロード提供、イベントレポート記事の制作など、参加できなかった見込み顧客に対しても接触の機会を提供できます。こうした情報提供は、見込み顧客の育成やブランドの継続的な認知拡大に役立ちます。
さらに、イベントの結果や参加者からのフィードバックを社内で共有することで、ナレッジの蓄積と今後の改善にもつながります。マーケティングチーム、営業チーム、製品開発部門などが連携し、得られた情報を次の施策や製品改善に活かすことで、マーケティング全体の質を高めることができます。
このように、イベント後の施策展開をしっかりと計画し、継続的なコミュニケーションと情報活用を行うことが、企業のマーケティング活動を戦略的かつ効果的に進める上で欠かせないプロセスです。
まとめ:イベントマーケティングを成功に導くためのポイント
イベントマーケティングは、単なる販促活動ではなく、顧客との接点を創出し、関係性を構築・強化するための戦略的な手段です。展示会やセミナー、交流会、オンラインイベントなど、多様な形式を活用しながら目的に応じた設計を行うことで、以下のような成果につなげることが可能です。
- 見込み顧客の獲得
- 既存顧客のナーチャリング
- ブランド認知や信頼の向上
イベントマーケティングを成功に導くためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 開催目的とターゲットの明確化 目的や訴求ポイントが曖昧なイベントは成果が出にくくなります。
- コンテンツと体験価値の設計 セミナー内容や展示ブースの導線など、参加者視点の設計が鍵になります。
- Webサイト・SNSなどを活用した集客施策 イベントの告知やリマインドによって、参加率や質を向上させます。
- リアル・オンライン両面での戦略構築 会場開催とオンライン施策を組み合わせることで接点を最大化できます。
- イベント前後のフォローアップ体制の整備 アフターフォローを含めた一連の流れがリード獲得や信頼構築につながります。
- 営業・マーケティング部門との連携 部門間で役割分担やデータ共有を行うことで、施策の成果を最大化できます。
- 効果測定と改善サイクルの構築 イベント後の分析により、次回開催への改善点が明確になります。
イベントを単発の施策として終わらせるのではなく、「点」ではなく「線」「面」として捉え、全体戦略の中に位置づけることで、企業の成長を支える継続的なマーケティング活動として成果を上げることができます。
よくあるご質問
質問:イベントマーケティングとはどのような手法ですか?
答え:
イベントマーケティングとは、展示会やセミナーなどのイベントを活用して、見込み顧客との接点を創出し、認知度向上やリード獲得を目的とするマーケティング手法です。顧客の関心を引き、関係性を築くために有効です。
質問:BtoB企業がイベントを活用するメリットは何ですか?
答え:
BtoB企業にとって、イベントは商談機会の創出、顧客との関係強化、ブランド信頼性の向上といった複数のメリットがあります。製品・サービスの理解を深めてもらえる貴重な場として活用されています。
質問:オンラインイベントとリアルイベントの効果的な使い分けは?
答え:
オンラインイベントは広範囲のターゲットに効率よくリーチでき、コスト面でも有利です。一方で、リアルイベントは体験や対面のコミュニケーションを重視する際に有効で、信頼構築に優れています。目的に応じて使い分けが重要です。
質問:イベントで獲得したリードはどのように活用すべきですか?
答え:
獲得したリードは、属性や関心度に応じて分類し、資料送付・メール配信・営業アプローチなどで育成していきます。イベント後すぐにフォローを開始し、商談や購買につなげる流れを整えることが大切です。
質問:イベントの成果を測定するには何を指標にすればよいですか?
答え:
登録者数や来場率、アンケート結果、リード獲得件数、商談化数、売上貢献度などが主な指標です。あわせてSNS反応数や資料ダウンロード数などの定性データも活用し、改善点を明確にします。