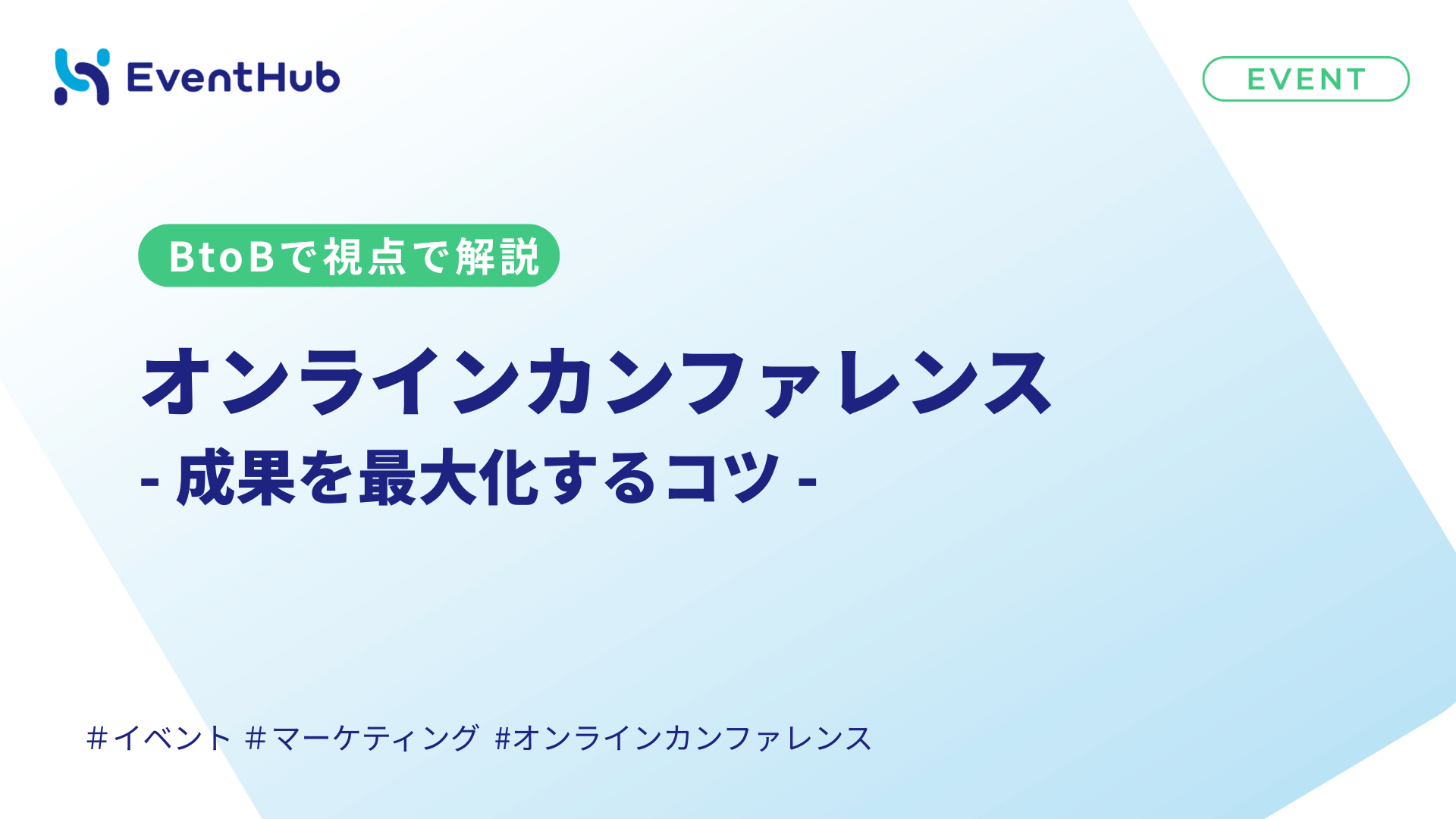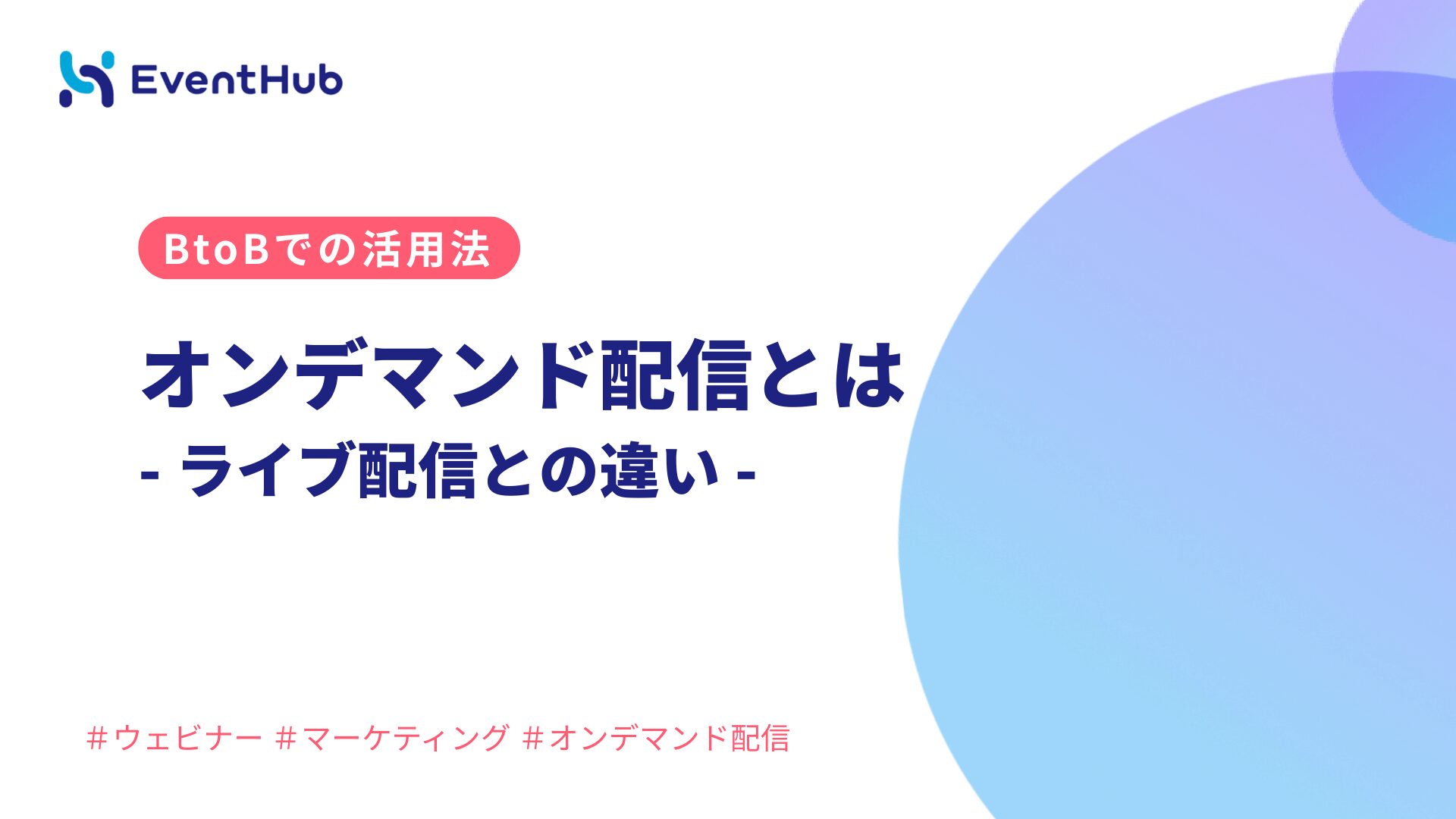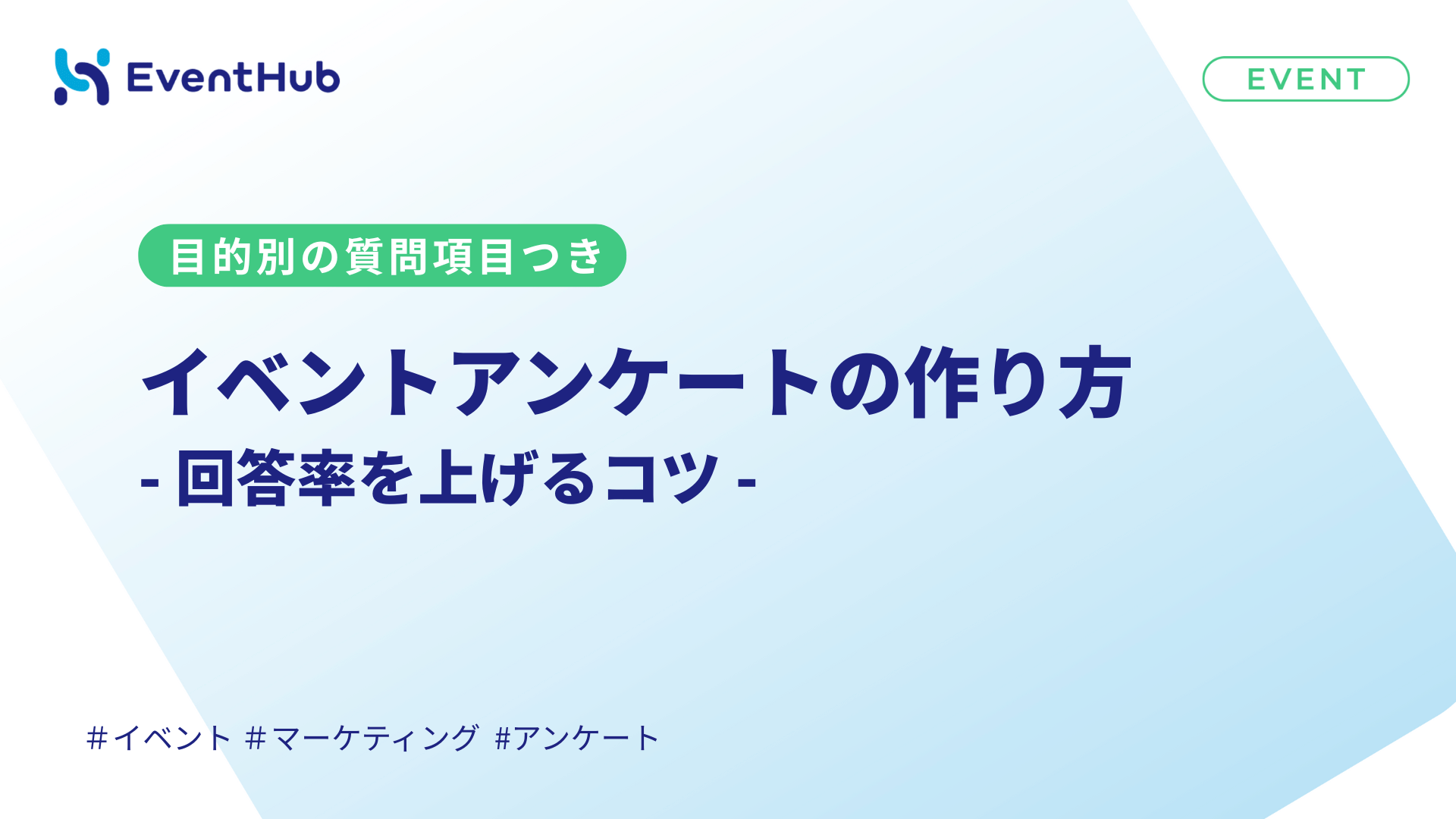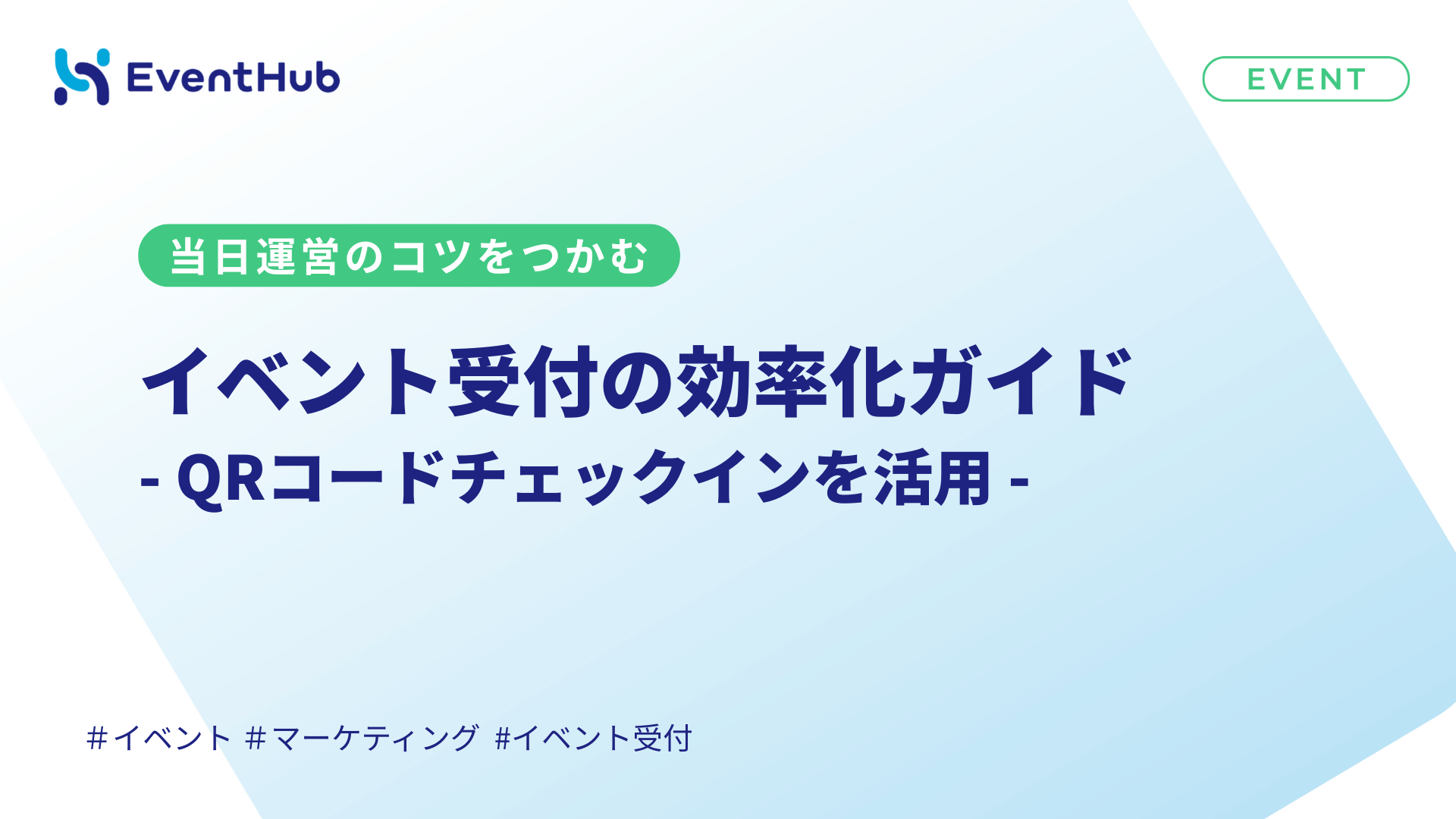ウェビナーマーケティングとは?リード獲得と商談化を最大化するマーケティング手法
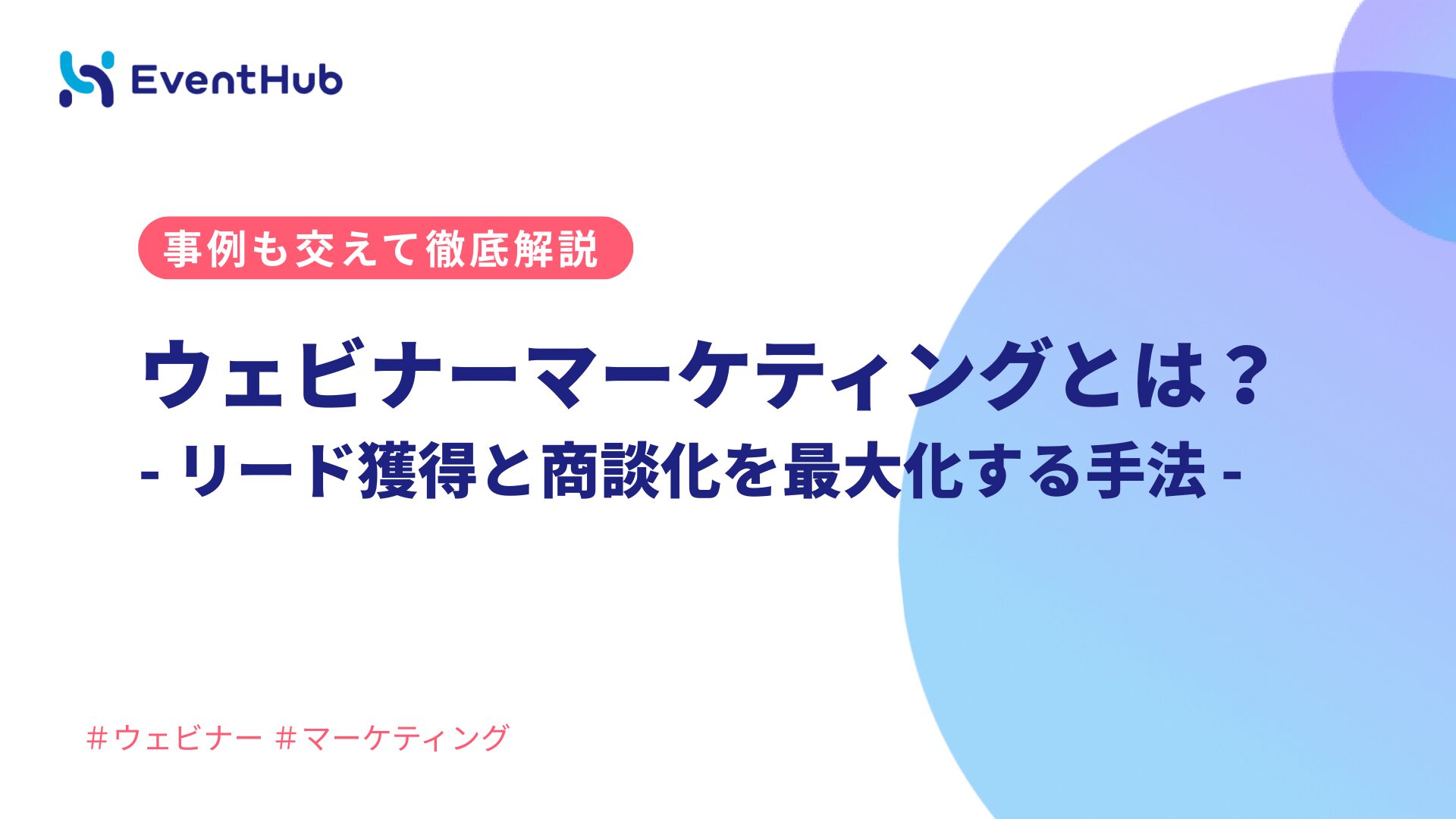
ウェビナーマーケティングとは、オンライン上で実施されるウェビナーを活用し、見込み顧客の獲得から商談化までを一貫して推進するマーケティング手法です。近年、BtoB企業におけるマーケティング活動は、従来の展示会や訪問営業から、デジタルを活用した効率的なアプローチへと急速に移行しています。その中で、ウェビナーは移動や会場手配といった手間をかけず、低コストかつリアルタイムな情報発信を可能にする手段として注目を集めています。
ウェビナーマーケティングでは、情報提供にとどまらず、興味関心に応じたアプローチ設計や、配信後のデータ活用、インサイドセールスとの連携が成果に大きく影響します。また、動画配信やオンデマンド展開、SNSを活用した告知活動など、ウェビナーを軸にした施策は多岐にわたります。この記事では、ウェビナーマーケティングの全体像と具体的な実施方法を、企画・集客・配信・フォローアップの各フェーズに分けて解説します。
ウェビナーマーケティングの基本と重要性
ウェビナーマーケティングは、オンライン環境を活用して見込み顧客との関係構築やリードの育成を行う施策です。特にBtoB領域においては、製品やサービスの導入検討に時間を要することが多く、複数の接点を通じて信頼関係を構築するアプローチが重要になります。その点で、ウェビナーは情報提供・質疑応答・リアルタイムでの状況把握が同時に行える有効な手段です。
以下のような特徴から、多くの企業が導入を進めています。
- 参加ハードルの低さ:会場への移動が不要で、インターネット環境さえあれば視聴可能
- 録画・オンデマンドでの再利用:コンテンツの資産化が可能で、費用対効果が高い
- 配信形式の柔軟性:ライブ配信・疑似ライブ・オンデマンドなど、目的に応じた形式が選べる
- データ活用のしやすさ:参加者の行動やアンケート結果などの情報を収集・分析しやすい
ウェビナーを活用したマーケティングは、商談化率の向上や営業活動の効率化に寄与します。また、参加者の温度感や興味のあるテーマに基づいたコンテンツ設計ができるため、従来のセミナーと比べて高いエンゲージメントを得ることが可能です。
ウェビナーとセミナーの違いとは
「ウェビナー」と「セミナー」はどちらも情報提供の手段ですが、開催形式や運用方法に大きな違いがあります。以下に代表的な違いをまとめます。
| 比較項目 | セミナー | ウェビナー |
|---|---|---|
| 開催場所の違い | 物理的な会場で実施 | オンライン上で配信。Webカメラと配信ツールを用いて実施 |
| 参加のしやすさ | 移動や時間の制約があるため、参加ハードルが高い | 好きな場所から参加可能で、リアルタイム視聴またはアーカイブ視聴が可能 |
| 実施コスト | 会場費・スタッフ・印刷物などの準備が必要 | 配信ツールやWeb環境さえ整えば比較的低コストで実現可能 |
| 情報収集のしやすさ | ー | 参加時間・興味を持った資料・チャットの質問など、詳細な視聴者データが取得でき、ニーズ分析に活用可 |
このように、ウェビナーは情報提供と参加者理解を同時に実現できるマーケティング手段として、現代のビジネス環境において重要性を増しています。
ウェビナーマーケティングの企画設計と目的設定
ウェビナーマーケティングを成功に導くには、配信やフォローアップといった各施策に加えて、事前の企画設計が最も重要な要素になります。企画段階で目的やターゲットが不明確なまま進めると、視聴者の関心を引けず、参加率や商談化率が伸びない原因になります。
まずはウェビナー開催の目的を明確にしましょう。目的に応じて適切な内容や構成、使用すべき配信方式が決まります。
以下のような目的分類が参考になります。
- リード獲得:新規見込み顧客の登録を目的とする
- 案件育成:既存リードの検討段階を前進させる
- 製品理解促進:製品・ソリューションの深い理解を促す
- 顧客フォロー:既存顧客との関係維持、追加提案の場とする
企画時に「誰に」、「何を」、「どのように」伝えるかを設計することで、ウェビナーの構成やツールの選定、配信形式の判断がスムーズになります。
また、ウェビナーはリアルイベントよりも参加者の集中力が持続しづらいため、テーマの絞り込みや資料構成にも工夫が求められます。
成功する企画の立て方とターゲット設計
ウェビナーマーケティングでは、企画の質が成果に直結します。特にBtoB領域では、視聴者の課題や興味に的確に応える設計が不可欠です。以下の観点から、成功する企画を立てるためのポイントを整理します。
ターゲットの明確化
企画の初期段階で、誰に向けたウェビナーなのかを明確にすることが必要です。
- ペルソナの設計:業種・職種・課題・情報収集フェーズなど、詳細な設定を行います。
- 購買段階の明示:新規リード獲得か、既存顧客の理解促進かなど、目的に応じた分類を行います。
- 商談化を見据えた設計:営業チームとの連携を通じて、訴求ポイントを具体化します。
関心を引くテーマの設定
視聴者が「この内容は自分に関係がある」と感じられるテーマを選ぶことが重要です。
- 例:最新業界トレンドの解説、他社の成功事例、業務改善ソリューションなど
- タイトル設計:「○○のプロが語る」「今すぐ使える○○対策」などの文言を含めると訴求力が高まります
ウェビナーの形式選定
視聴者の視聴スタイルや目的に応じて、以下のような形式を選択しましょう。
- ライブ配信:リアルタイムで質疑応答や参加型の仕掛けが可能
- オンデマンド:録画視聴により、好きな時間に視聴できる利便性がある
- 疑似ライブ:実施感を演出しつつ、スケジュール調整の柔軟性を持たせる形式
社内連携と情報収集
マーケティング部門だけでなく、営業やプロダクト、サポートチームと密接に連携することで、現場の声を企画に反映できます。また、過去ウェビナーのデータも有効です。
- アンケートの活用:過去開催時の反応や質問を分析し、ニーズに沿ったテーマ選定に活かします
- 資料やチャットログの分析:視聴者が興味を示したトピックを次回の企画に反映させます
企画書の作り方や共催企業の選び方、KPI設計や登壇者の依頼方法までを7つのステップで解説した詳細記事を公開しています。テンプレートもダウンロード可能ですので、より実務的な情報をお探しの方は、以下の記事をご覧ください。
👉 ウェビナー企画の完全ガイド|成功する企画づくりの7ステップと企画書テンプレート
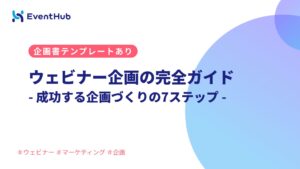
効果的な集客と参加率を高める方法
どれほど優れた企画内容でも、視聴者が集まらなければウェビナーの成果にはつながりません。集客はウェビナーマーケティング全体の成功を左右する重要なフェーズです。特にBtoBの場合、単に参加者数を増やすだけでなく、自社のターゲット層を的確に集められるかどうかが大きな分かれ目になります。
集客の基本:チャネルの組み合わせとタイミング設計
ウェビナー集客を成功させるには、複数チャネルの活用とタイミング設計の最適化が欠かせません。以下の手法は、それぞれ異なる属性の見込み顧客にアプローチできます。
メールマーケティング
- 自社の顧客リストをもとに、ペルソナに即した案内を送信
- 件名や配信タイミングをテストし、開封率・クリック率を改善
- 過去参加者や資料ダウンロード者向けにパーソナライズした内容を送付
SNS告知
- 自社のX(旧Twitter)、Facebook、LinkedInなどを活用し、短文で訴求
- バナーや動画を添付することで視覚的に注目を集める
- ハッシュタグを工夫し、新規層へのリーチを拡大
ランディングページ(LP)
- ウェビナー専用のLPを作成し、概要・日時・申込みボタンを明確に設置
- アーカイブ配信の有無や参加メリットを記載して登録率を向上
- LPをメール・SNS・Web広告と連携させて集客を一元化
Web広告の活用
- Google広告やSNS広告で、新規層への認知拡大を実現
- キーワードや業種・職種などを絞り込んだターゲティングで高精度配信が可能
オフライン施策との連携
- 展示会や商談時に獲得した名刺へのフォローアップとして、ウェビナー参加を案内
- 名刺管理ツールとMAの連携により、スムーズな案内が可能に
上記のような施策を組み合わせ、段階的かつ統合的なスケジュールで配信・告知を行うことが参加者数と視聴率の増加につながります。
より詳細な手法と成功事例については、以下の記事で7つの集客施策を解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
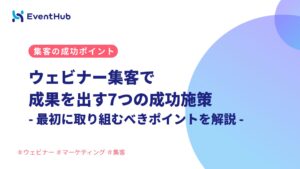
参加率を高めるためのリマインド・導線設計
申込みがあっても、当日に参加してもらえなければ意味がありません。参加率を上げるためには、開催前のリマインド設計と、参加導線の最適化が重要です。
- 申込み直後に自動返信メールを送信し、日時や視聴URL、よくある質問などを明記
- 開催1週間前、3日前、前日、当日の4回程度で段階的に案内
- 内容に変化をつけ「参加メリット」「講師紹介」「見どころ」などを案内
- 視聴URLは視認性の高いボタン形式で記載
- カレンダー登録や事前質問受付フォームも設置することで、参加意欲を向上
特にBtoBの場合、営業部門との連携による個別のフォローアップや電話でのリマインドも効果的です。
SNSとメールを活用したベストな告知運用
それぞれのチャネルには異なる特性があります。適切な使い分けが、訴求力の向上につながります。
- メール配信
既存リードへの直接アプローチとして有効。セグメントごとに最適なメッセージで配信し、申込みフォームへの導線を明確に設定します。 - SNS告知
潜在層へのリーチや拡散に優れており、開催日が近づくタイミングでの複数回投稿が有効。登壇者のSNSも活用し、共催プロモーションとしての展開も効果を発揮します。
イベント当日の演出で離脱を防ぐ
参加率だけでなく、「最後まで見てもらう」ための工夫も必要です。
- 開始10〜15分前にオープニングスライドやカウントダウン表示を行う
- 講師がリアルタイムでチャットに反応するなど、ライブ感を演出
- 終了後には次回の案内・アンケート・特典案内などを盛り込むことでフォローアップへつなげる
集客施策の質を決めるのは「ターゲティング」と「検証」
集客施策はやみくもに実施するのではなく、ターゲットを明確にし、検証と改善を重ねることが成果につながります。たとえば:
- 商談化率が高い参加者の共通点を分析し、広告やメールのターゲティングに反映
- SNSで反応が良かった投稿の表現を、他チャネルでも活用
- アンケートや視聴ログを分析し、最適な配信時間や曜日を見極める
これらの施策は、継続的な運用と改善サイクル(PDCA)のなかで、徐々に成果を積み重ねていくことが肝要です。
ウェビナー配信と当日の運営のポイント
ウェビナー当日の運営は、視聴者の満足度や商談化率に直結するものです。どれだけ企画や集客に成功しても、配信トラブルや視聴しづらい環境があれば、参加者の離脱やネガティブな印象につながってしまいます。そのため、事前準備・技術設計・進行管理の3軸で構成された運営体制が不可欠です。
安定した配信環境を整えるための準備
参加者が快適に視聴できる配信環境を整えるには、下記のようなハード面・ソフト面での準備が重要です。
- インターネット回線の確保
有線接続を基本とし、事前に速度テストを実施。予備のWi-Fi環境やモバイル回線も用意しておくと安心です。 - 機材の点検と予備の用意
Webカメラ、マイク、スピーカー、照明機器を事前にチェックし、バックアップ機材も常備します。 - 映像・音声・背景の確認
カメラの角度や背景映り、マイクの音質を事前にテストし、視聴者にとってストレスのない環境を整備します。
配信形式の選定とその特徴
目的やターゲットに応じて、配信形式を使い分けることで、視聴体験とエンゲージメントの最大化が期待できます。
| 配信形式 | 特徴と活用シーン |
|---|---|
| ライブ配信 | 登壇者とリアルタイムでやりとりができ、質疑応答や投票機能との連携が可能。参加者とのコミュニケーションを重視するウェビナーに適しています。 |
| オンデマンド配信 | あらかじめ録画された映像を好きな時間に視聴でき、参加ハードルが低いのが特徴。リード育成や情報提供型のコンテンツに向いています。 |
| 疑似ライブ配信 | 収録済みの映像をライブ配信のように見せ、チャット対応などでリアルタイム性を演出。高品質なコンテンツ提供とインタラクティブな体験を両立できます。 |
各形式の選定基準については、以下のように整理できます。
- 新規リード獲得を目的とする場合:ライブ配信で参加意欲を喚起
- 営業部門のフォロー施策:オンデマンド配信で視聴の利便性を確保
- 信頼構築を重視:疑似ライブ形式でブランド価値を強調
使用する配信ツールの選定と確認ポイント
自社の配信体制や目的に応じて、以下のような配信ツールを使い分けることが推奨されます。
- Zoom/Webex/Microsoft Teams
ビジネス用途での利用実績が多く、安定した品質と操作性を確保できます。チャット・Q&A・投票機能なども充実。 - YouTube Live
幅広いユーザーに向けたオープンなウェビナーで有効。事前登録が不要なケースに適しています。 - EventHub
EventHubは上記ツールを連携させて配信することもできますし、独自の配信機能も有しています。社内のご事情に合わせた配信体制が組めます。
選定時には以下のポイントをチェックしましょう。
- 参加者の登録・管理機能があるか
- 視聴データ(滞在時間・クリック数・質問など)が取得できるか
- チャット・質疑応答・アンケートなどの双方向機能の有無
- 録画・アーカイブ配信への対応可否
トラブル対応とリスクマネジメント
当日の配信トラブルを防ぐため、トラブルシナリオと対処マニュアルを事前に整備しておくことが不可欠です。
- 想定されるトラブルの例
- 音声が聞こえない
- 画面共有がうまくいかない
- 登壇者の接続遅延
- 対応策と準備内容
- 代替資料やスライドを共有できる体制
- 事前に複数の通信手段(チャット・電話)を関係者と設定
- オンラインリハーサルでトラブルをシミュレーション
また、EventHubでは、配信当日のトラブル対応に備えたマニュアル提供や支援体制も整備されているため、社内リソースが不足している場合には活用を検討すると効果的です。
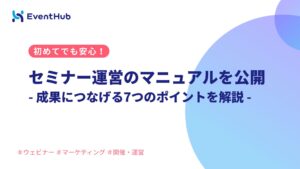
インタラクションの工夫で参加者のエンゲージメントを向上
視聴者が「受け身」にならないよう、インタラクション設計を組み込むことが離脱防止と印象向上の鍵です。
- チャットやQ&A機能を活用して、視聴中の疑問や感想をリアルタイムで収集
- 講演の中で投票や簡易アンケートを実施し、参加型の構成にする
- 登壇者がチャットに反応したり、視聴者の質問を取り上げることで双方向性を演出
こうした設計により、参加者の集中力や満足度が向上し、商談や資料請求などのアクションにもつながりやすくなります。
顧客データ活用と商談化へのフォローアップ
ウェビナーは単に「情報を届ける場」ではなく、見込み顧客の行動データを取得し、商談へとつなげる接点として活用することが重要です。参加者の視聴状況や反応、アンケート結果などを活用することで、マーケティング活動の精度を高め、営業部門と連携した戦略的なアプローチが可能になります。
特にBtoBにおいては、リードナーチャリングの考え方が不可欠です。ウェビナー参加をきっかけにした継続的なフォローアップによって、商談化・受注へとつながる確率も変わっていきます。
以下は、効果的なデータ活用とフォローアップのポイントです。
- 視聴ログの取得と分析
- 参加・途中離脱・視聴完了といった行動を把握し、関心度の高さを可視化
- チャット・質疑応答の内容から、関心を持ったテーマや課題を抽出
- アンケートによる温度感の確認
- セッション後にアンケートを実施し、内容の理解度や興味のある製品分野を把握
- アンケート回答率を高めるために、視聴後すぐのタイミングで配信する
- データの一元管理と突合作業
- MAやCRMツールにより、ウェビナー視聴データと営業活動の情報を一元管理
- 過去の接点や商談履歴との突合作業により、対応の優先順位を明確化
- インサイドセールス(IS)との連携
- 関心度が高い参加者から優先的にアプローチし、タイミングを逃さずに商談化を図る
ウェビナー参加データの収集・分析手法
参加者データは、フォローアップや営業アプローチを最適化するための有益な情報です。以下のような手法を通じて、より実践的な活用が可能となります。
- 視聴ログの詳細取得
- 登録情報(会社名・役職・業種など)と視聴時間、滞在時間を分析し、温度感を数値化
- 複数回視聴者や録画視聴者の行動も含めて、興味の強さを評価
- 視聴行動のスコアリング
- セグメントごとにスコアを設定し、営業部門が優先すべきリードを明確化
- 例:視聴完了+質疑応答あり→高スコア、冒頭離脱→低スコア
- アンケートデータの活用
- 検討状況や興味のある製品カテゴリに関する項目を設定し、インサイトを獲得
- フリーコメント欄を活用し、具体的な関心や課題を直接引き出す
- データの再利用と改善施策
- 過去のデータをもとにした次回ウェビナーのテーマ設定やターゲティングの改善
- 成果の高かった構成や配信方法を分析し、成功パターンを構築
このように、ウェビナーはコンテンツの提供にとどまらず、営業活動に直結する、顧客データの収集も可能にします。収集したデータを次のアクションに結びつけることが、マーケティング成果の向上につながります。
成功事例に学ぶウェビナーマーケティングの実施ポイント
実際の企業がウェビナーをどのように活用して成果を上げているのかを知ることは、自社の施策に大きな示唆を与えます。ここでは、EventHubを活用した代表的な企業事例をもとに、成果につながるウェビナー運営のポイントを紹介します。
株式会社マネーフォワード|無人配信で月間開催数を4倍に拡大
マネーフォワードでは、人的リソースに制約があるなかで、開催本数の増加と工数削減の両立を目指し、EventHubの「擬似ライブ配信」機能を活用して完全無人配信を実現しました。
- 準備〜配信の所要時間を約75%削減
- 月間ウェビナー開催数を3本から11~12本に拡大
- 視聴維持率は70〜80%を安定的に達成
- コンテンツ改善への時間投資が可能となり、リード獲得成果も向上
詳しくは[株式会社マネーフォワードの導入事例]をご覧ください。
🔗 事例記事:完全無人配信が実現!工数が1/4、開催数は4倍に!工数削減で企画運営に注力、リード獲得のKPIを大幅達成

NTTデータ先端技術株式会社|アンケート回収率を回復、少人数で200回超を運営
セミナーの自動化と標準化を進めたことで、年30回から200回以上の開催を少人数体制で実現。擬似ライブ配信とアンケートプッシュ機能の活用により、回収率や満足度の改善にも成功しました。
- 回答率がオフライン時代と同等まで回復
- セミナーの属人化を解消し、再現性ある運用を確立
- アンケートデータを起点としたナーチャリング強化を実現
詳しくは[NTTデータ先端技術株式会社の導入事例]をご覧ください。
🔗 事例記事:EventHub導入によりオンラインセミナ運営を効率化・省力化!年間200回以上のセミナ開催を少人数で実現

株式会社カオナビ|イベント経由で商談全体の約40%を創出
「イベントマーケティング=商談の起点」として位置づけ、MarketoやSalesforceとの連携によりスコアリングや突合作業の自動化を実現。営業部門とのスムーズな連携で、商談化精度が向上しています。
- 総商談の約40%をイベント経由で創出
- データ連携の自動化で作業時間を5分の1に短縮
- HOTリードへの即時アプローチ体制を構築
詳しくは[株式会社カオナビの導入事例]をご覧ください。
🔗 事例記事:総商談の約40%がイベントマーケティングから!イベントマーケの効果をEventHubで最大化し、事業成長に貢献

野村不動産株式会社|ウェビナーから面談化率50%を実現
マンション販売において、ウェビナーからの個別面談誘導を重要視し、参加後のスムーズな遷移導線をEventHubで設計。個別チャットや高解像度な配信によって、顧客満足度と面談率の両立を実現しました。
- 面談への遷移率が50%を超え、KPIを大きく上回る成果
- 3日間で9回配信する体制を少人数で運用
- フォロー施策と連動した設計で成果を最大化
詳しくは[野村不動産株式会社の導入事例]をご覧ください。
🔗 事例記事:Zoomから乗り換えて3ヶ月でウェビナー参加数200件・個別面談98件を創出 ウェビナーからのシームレスな画面遷移が個別面談遷移率50%の決め手に

成功事例から見える共通ポイント
これらの事例には、次のような共通項が見られます。
- 明確な目的設計とターゲット設定
「誰に、何を、どう届けるか」が明確な設計になっており、ウェビナーの内容もターゲットに即したものとなっています。 - 属人化の解消と再現性ある運用
EventHubなどのプラットフォームを活用し、誰が担当しても一定の成果が出せる体制を構築しています。 - データに基づく施策の最適化
アンケート結果や行動ログなどを活用し、PDCAを回しながらウェビナーを改善しています。 - フォローアップの仕組み化
MAやCRMと連携し、HOTリードに対するタイムリーなアプローチを実現しています。
こうした成功要因を押さえることで、ウェビナーは単なる情報提供の場ではなく、マーケティングと営業を橋渡しする戦略的なチャネルとして機能します。
さらに網羅してウェビナーの成功事例をおまとめしている記事をご一読ください。
🔗 記事「BtoBウェビナー成功事例 13選|EventHubを活用することで成果を最大化」
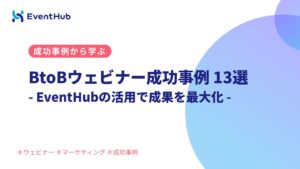
まとめ:ウェビナーマーケティングで商談化率を最大化するには
ウェビナーマーケティングは、リード獲得から商談化、さらに受注へとつながる流れをオンライン上で完結できるマーケティング手法です。配信形式の選択から顧客データの活用に至るまで、各工程における設計と運用が成果を左右します。
以下に、本記事で解説した要点をトピックと補足説明で整理します。
- ウェビナー開催の目的を明確にする
リード獲得、育成、製品理解促進、顧客フォローなど、目的ごとに施策を設計することが成果最大化の第一歩となります。 - ターゲットとテーマを具体化する
ペルソナに基づいた関心領域を洗い出し、参加者のニーズに応えるテーマ設定が必要です。 - 集客チャネルは多面的に活用する
メール、SNS、ランディングページ、Web広告を連動させ、視認性と訴求力を高めます。 - 配信環境と形式は目的に合わせて選択する
ライブ配信、オンデマンド、疑似ライブなどの形式を使い分け、参加者体験を最適化します。 - 配信後のデータ分析と営業連携を徹底する
視聴履歴やアンケートを分析し、インサイドセールス(IS)や営業担当との連携で商談化を促進します。 - 成功事例から実施の勘所を学ぶ
他社の取り組みを参考に、自社に合った企画・配信・フォロー体制を構築することで改善の精度を高められます。
これらの要素を一貫したプロセスとして構築することで、ウェビナーは商談創出や受注貢献というビジネス成果に直結するマーケティング活動へと発展します。
自社のフェーズや商材特性に合わせて、効果的なウェビナーマーケティングの運用体制を整えていきましょう。
よくあるご質問
質問:ウェビナーマーケティングに必要なツールにはどんな種類がありますか?
回答:配信ツール(Zoom、YouTubeなど)に加え、ランディングページ作成ツール、MAツール、CRMなどが必要です。また、アンケート作成ツールや視聴ログ分析ツールなども活用すると、参加者の理解や関心の可視化に役立ちます。目的や予算に応じて最適な組み合わせを選択しましょう。
質問:オンデマンド配信とライブ配信はどちらが効果的ですか?
回答:目的によって効果的な配信形式は異なります。リアルタイムの反応や質疑応答を重視する場合はライブ配信が有効です。一方で、参加のハードルを下げたい、長期間リード獲得を続けたい場合はオンデマンド配信が適しています。疑似ライブという選択肢も併せて検討すると良いでしょう。
質問:参加者からの反応を高めるためにできる工夫はありますか?
回答:視聴者とのコミュニケーションを設計することが効果的です。チャット機能でのリアルタイム質問受付、投票、参加型コンテンツの導入などが挙げられます。さらに、アンケートの実施や終了後のフォローアップも重要です。視聴者の行動フェーズに合わせて双方向の仕組みを設計しましょう。
質問:ウェビナー後のフォローアップではどのような施策が効果的ですか?
回答:参加者の視聴データやアンケート結果をもとに、優先度を見極めたうえでメール配信や電話によるフォローを実施します。特に、質疑応答に積極的だった視聴者は温度感が高いため、インサイドセールス(IS)との連携で迅速な商談化が可能です。ナーチャリング用のコンテンツ提供も併せて検討しましょう。
質問:BtoB企業が初めてウェビナーを実施する際に注意すべき点は?
回答:まず目的を明確にし、社内の関係者と役割を分担したうえで進行管理を徹底することが重要です。また、配信形式やツールの選定だけでなく、トラブル対策、リハーサル、視聴環境の確認など事前準備も欠かせません。初回は特に、参加者満足度を高めるための導線とフォロー設計が成功の鍵となります。