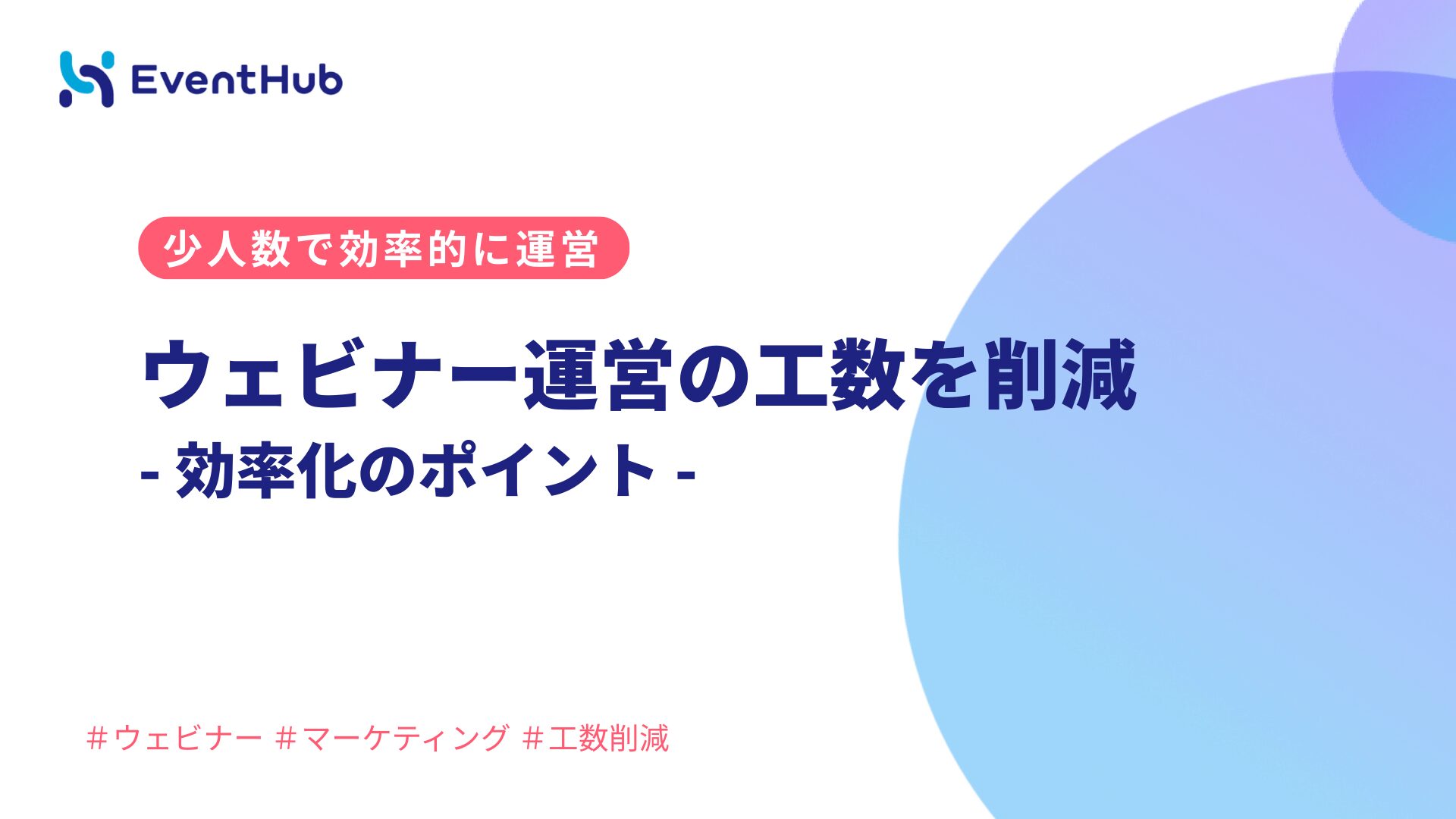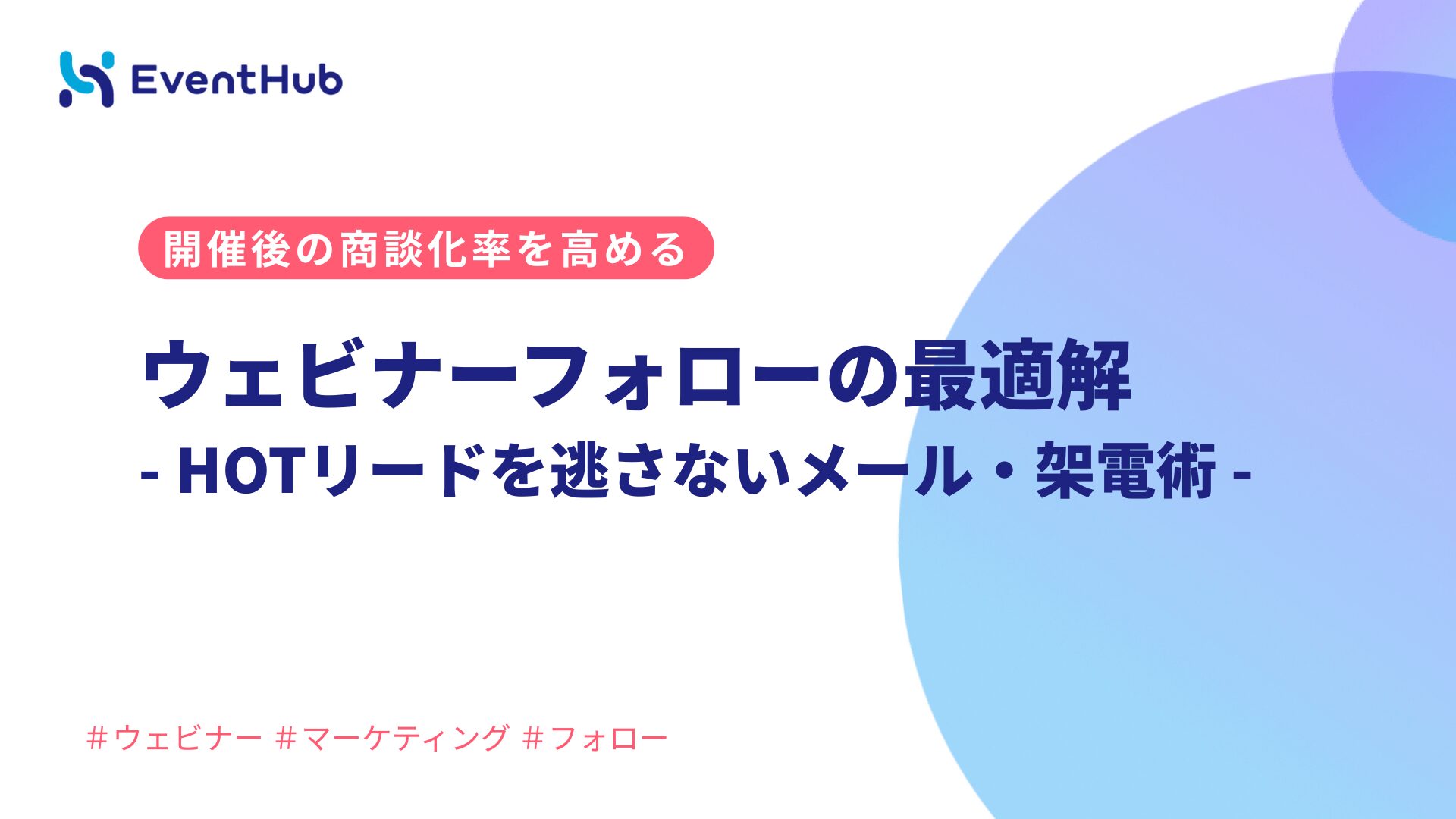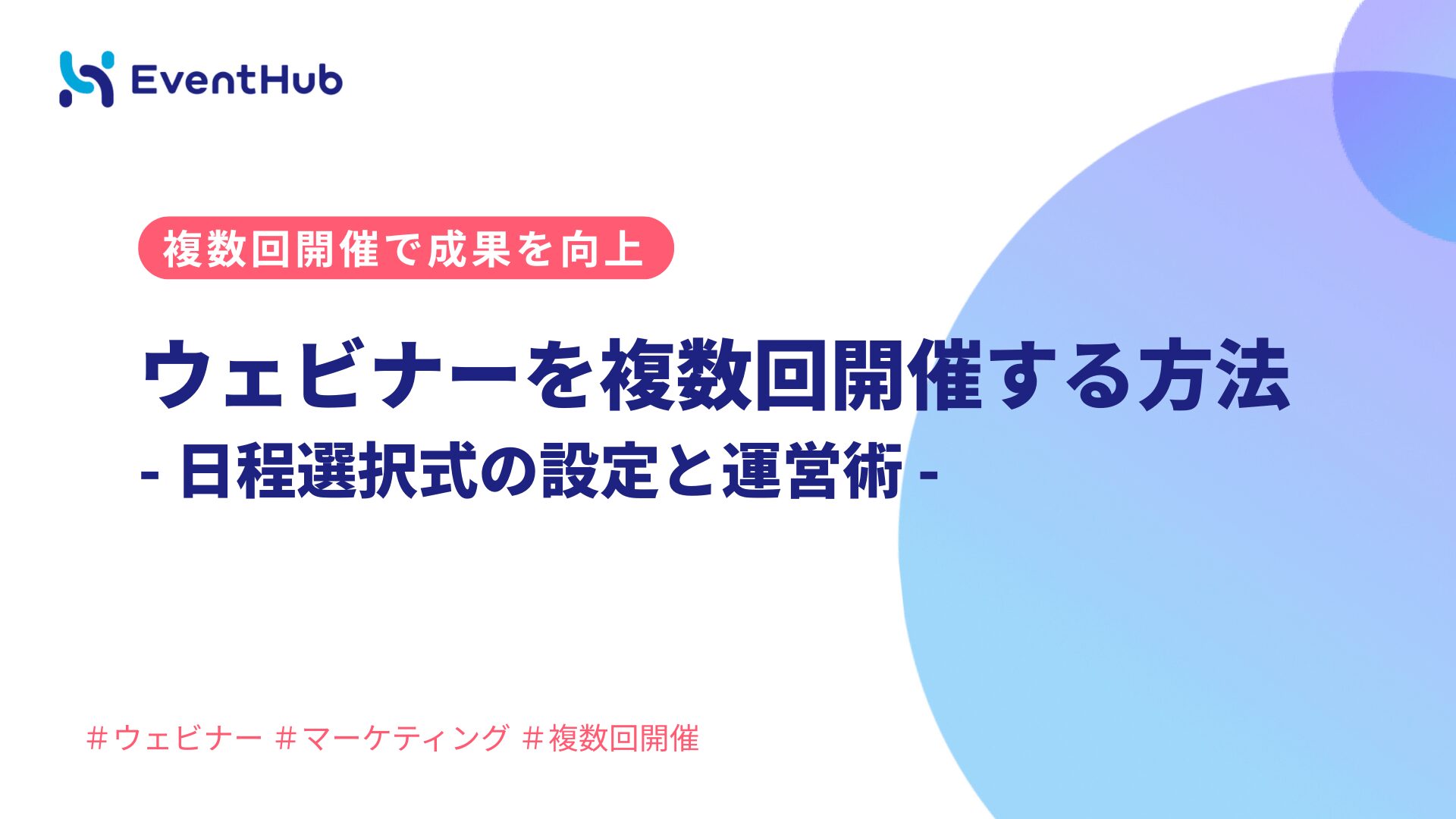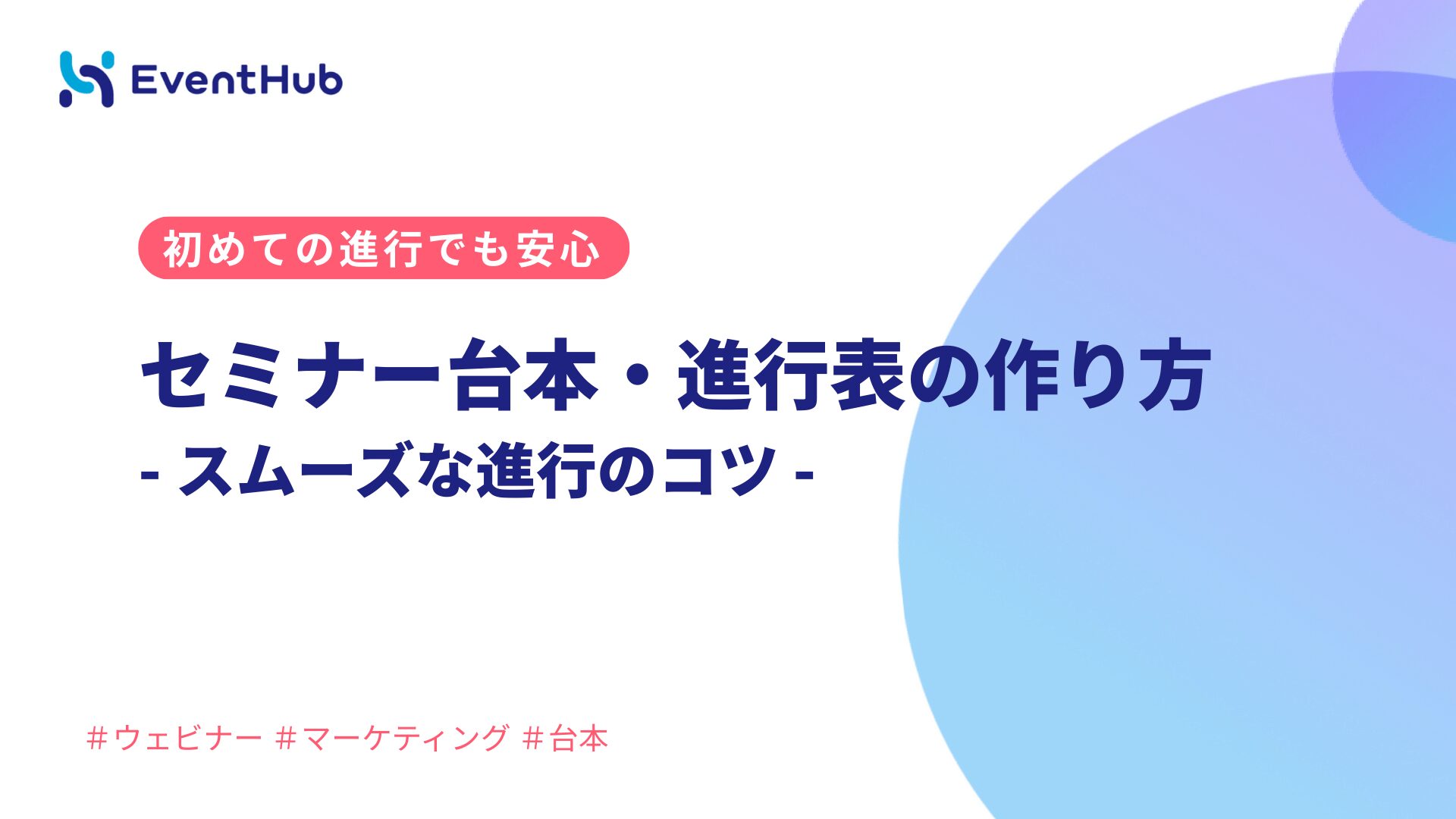BtoBウェビナー成功事例 13選|EventHubを活用することで成果を最大化
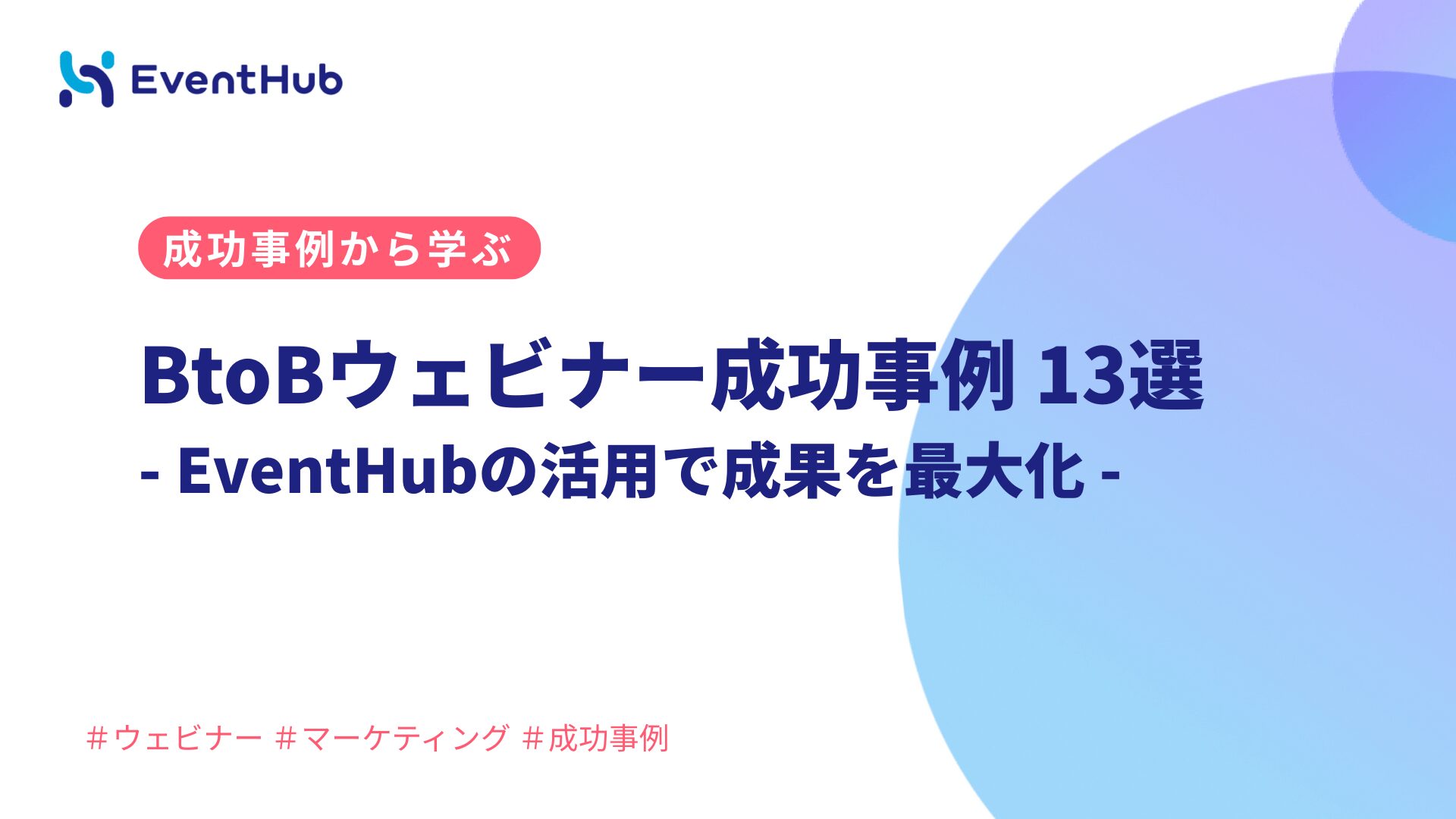
近年、BtoBマーケティングにおいて「ウェビナー」の活用が急速に広がっています。オンラインでの開催が一般化したことで、場所や時間の制約を受けずに多くの参加者にリーチできる点が評価されており、マーケティング施策の中心に据える企業も増加しています。
本記事では、EventHubを活用した企業の成功事例をもとに、ウェビナーを戦略的に設計・運用する方法を解説します。配信形式やツールの選定、事前準備からアフターフォローまで、実際の導入事例をもとに具体的なノウハウを紹介します。また、集客力の高いテーマ設計や、商談化率を高める仕組み作りなど、成果に直結する取り組みについても詳しく掘り下げます。
本記事を通じて、単なる情報提供の場ではなく、見込み顧客の獲得や育成、商談への移行といった目的達成につながるウェビナーの実践的な運用方法を学べます。今後のマーケティング戦略を設計するうえでの参考として、ぜひ最後までご覧ください。
ウェビナー成功事例から学ぶポイント|13社の事例から見える共通項
ウェビナーを効果的に活用している企業には、いくつかの共通点があります。成功の鍵となるのは、事前準備・当日運営・事後フォローという一連の流れをデータに基づいて設計し、再現性のある運用を構築している点です。
- データ活用を前提とした設計
参加者の行動ログやアンケート結果をもとに、次のアクションを明確にする構成が必要です。 - 施策の一貫性とスピード感
企画から告知、配信、フォローアップまでを一元的に管理することで、機会損失を最小化します。 - 適切なツールの導入と連携
MA/CRMとの連携により、リードの優先度付けやナーチャリングの精度を高めています。 - 成果指標の明確化と定量的評価
単なる参加者数だけでなく、商談化率やアンケート回答率といった指標を重視する傾向があります。 - 継続的な改善による最適化
初回の施策で終わらせず、定期的な分析と改善を繰り返すことで、効果の最大化を図っています。
このような運用を実現している企業は、マーケティングと営業をつなぐ戦略的なチャネルとしてウェビナーを活用しています。
データドリブンなアプローチの重要性
成功事例に共通するのが、データを軸とした施策展開です。以下のような要素が、成果の差を生み出すポイントとなっています。
- アンケートデータと行動ログの分析
参加者がどの資料を閲覧したか、どの時間帯に離脱したかなどを可視化し、施策の精度を高めています。 - リアルタイムでの反応把握と対応
チャットでの質問内容や視聴中の反応を収集し、次回の内容やアプローチ方法の改善に反映しています。 - セールス部門との連携を前提としたスコアリング設計
アンケート回答内容や視聴時間をもとに、見込み顧客をスコアリングし、インサイドセールス(IS)や営業への引き継ぎ精度を向上させています。 - 配信終了後のフォローアップ設計
フォローアップメールの内容やタイミングも、データに基づいて最適化されています。回答が得られたタイミングで個別対応を実施することで、商談化率が高まります。
このように、ウェビナーの価値は「配信して終わり」ではなく、そこから得られる情報をいかに分析し、次に生かせるかにかかっています。
ウェビナー事例 分類①|スケール運用型(無人配信・多頻度)
スケール運用型は、限られた人員の中で、高頻度でウェビナーを開催する企業に適した形式です。特に擬似ライブ配信を活用することで、リアルタイムでの対応を省きながらも「ライブ感」のある進行を実現しています。
- 複数日程化による視聴機会の最大化
異なるタイミングで参加できるよう日程を分散することで、参加者の都合に合わせた柔軟な対応が可能です。 - 録画配信と自動メールを組み合わせた省力運用
申込み、視聴URL配布、リマインド、アフターフォローまでを自動化することで、人的リソースを大幅に削減できます。 - イベントマーケティングプラットフォームとの連携
EventHubのようなプラットフォームを活用することで、申込み管理から配信、アンケート回収、データ分析まで一元管理が可能です。 - 工数削減とKPI達成の両立
準備から配信、分析にかかる時間を短縮しつつ、視聴率や商談化といった成果にもつなげる運用が確立されています。
このタイプは、製品紹介やユーザー教育など、繰り返しニーズがあるテーマに適しています。
株式会社マネーフォワード|完全無人配信で開催数4倍
【導入の目的】
ウェビナー施策において「開催本数の拡大」と「本質業務への集中」を両立することが課題となっていた同社では、配信準備や当日の対応にかかる工数の多さが障壁となっていました。また、複数日程での開催を実現したい意向がありながらも、人的リソースの制約から運用負荷がネックとなり、現実的な実行が難しい状況でした。そこで、配信を完全無人化し、運用の省力化を図ることを目的に「EventHub」を導入しました。
【戦略・課題】
リード獲得をKPIに設定する中で、成果を安定して出すには開催数の増加と、1回あたりの成果の最大化が不可欠でした。複数日程での配信やアーカイブ活用も検討していたものの、増加する配信本数に比例して運営負荷も高まり、企画や分析といった重要業務への注力が困難になっていました。また、以前は録画データをYouTubeで配信していましたが、参加率・視聴維持率ともに低調で、効果的な運用とはいえない状況でした。
【取り組み・EventHub活用】
選定にあたっては、「無人配信への対応」「MAツール(Marketo)との連携」「誰でも使えるUI」「コスト効率の良さ」を重視し、特に開催回数に応じた追加料金が発生しない料金体系や、複数日程での配信が可能な点が大きな決め手となりました。
導入後は、擬似ライブ配信を活用し、録画した動画を事前に設定することで完全無人での配信を実現。チャット機能は閉じ、「お知らせ機能」を活用して必要な情報を提示するようにしました。
さらに、MarketoとのAPI連携によって申込みデータや視聴ログを効率的に突合・活用し、スコアリングやフォロー施策の精度も向上しました。加えて、「横断イベント分析」機能を活用し、申込み数・参加率・視聴時間といった複数回の配信結果を横断的に確認できる仕組みを構築しました。
【成果】
- 完全無人配信の実現により、準備から配信完了までの所要時間が約1/4に短縮。現在では、1回あたりの準備が10〜20分程度に抑えられ、当日は他業務に専念しながら配信が可能な状態に。
- ウェビナー開催本数は月3本から11〜12本に拡大し、約4倍のスケールに。
- 擬似ライブ形式の導入により参加率は約70%、視聴維持率も70〜80%を安定的に維持。従来のYouTube配信では、参加率50%・平均視聴時間10分程度にとどまっていたことを踏まえると、顕著な改善が見られました。
- 時間的余裕が生まれたことで、コンテンツの質向上や顧客理解に向けた取り組みに注力できるようになり、リード獲得KPIの達成にも貢献しました。
EventHubの導入によって、運用効率と成果の両立を実現した同社は、今後も実務に役立つ情報を届けるウェビナー企画に取り組むとともに、生成AIなどのテクノロジーを活用したさらなる業務効率化やデータ活用の高度化にも挑戦していく方針です。
マネーフォワード|完全無人配信
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社マネーフォワードの導入事例]でご確認ください。

NTTデータ先端技術株式会社|自動化×標準化で年間200回超を少人数運営
【導入の目的】
統合運用管理ソフトウェア「Hinemos」の認知拡大と理解促進のため、同社では対面セミナーを積極的に活用してきました。しかし、コロナ禍によるオンライン化へのシフトに伴い、セミナー運営の質を維持しながら効率化を実現することが課題となりました。特に、減少したアンケート回答率の回復や運営作業のミス防止と省力化、さらに臨場感を維持したままのセミナー自動化を目的に、イベント特化型プラットフォーム「EventHub」の導入を決定しました。
【戦略・課題】
オンライン化当初はZoomやWebEXなどの汎用会議ツールを利用していたものの、以下のような運営課題が顕在化していました。
- アンケート回答率の大幅な低下
- 運営作業中の人的ミスやインシデントの発生
- ミスを防ぐための確認作業の肥大化
- 上記により少人数での高頻度開催が困難に
同社では、ウェビナーでオンラインならではの価値を提供することを目指しました。その中で、セミナー参加者の離脱を防ぎつつ、回答率を向上させる仕組みと、運営の効率化を同時に実現することが求められていました。
【取り組み・EventHub活用】
EventHubを導入した理由は、オンラインセミナーに最適化された機能と日本市場にフィットした操作性にありました。具体的な活用内容は以下の通りです。
- 擬似ライブ配信機能により、ライブ感を損なわずに運営作業を定型化・自動化
- アンケートプッシュ機能により、セミナー中・終了直後のタイミングで回答を促進
- インタフェースの直感的な操作性により、非専門人材でも運営が可能に
- 日本語UI、国内サポート体制、必要機能に絞られた設計により、社内での承認もスムーズ
また、セミナー構成そのものもオンラインに最適化。2時間を超える大規模セミナーでは30分以上の休憩時間を設けることで、参加者の途中離脱を抑え、満足度向上と回答率改善を両立しています。さらに、資料送付やアーカイブ配信、個別相談会案内といったフォロー施策と連動させることで、アンケートを「単体のお願い」ではなく、価値あるコミュニケーションの一環として位置づけ、参加者の協力を得やすい環境を構築しました。
【成果】
- 年間30回→200回超へと大幅な開催数増加を少人数体制で実現
- 擬似ライブ配信と定型化による運営工数の削減と人的ミスの防止を両立
- アンケート回答率はオンライン移行前の水準まで回復
- オンラインならではの形式に最適化したコンテンツ設計により、参加者満足度が向上
- 社内では「オンラインセミナー運営の標準化」が進み、再現性の高い運用体制を確立
EventHubの導入により、同社は配信効率化にとどまらず、セミナー品質の維持・向上と同時に省力化・自動化を実現し、今後も、オンラインを前提としたセミナー設計により、マーケティング施策の効果最大化を目指しています。
NTTデータ先端技術|自動化×標準化
→ さらに詳しい運用設計と数値は[NTTデータ先端技術株式会社の導入事例]でご確認ください。

ウェビナー事例 分類②|セールス連携強化型(MA/CRM連携・優先度付け)
株式会社カオナビ|総商談の約40%をイベントマーケから創出
【導入の目的】
株式会社カオナビでは、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を中心に、複数のサービスを展開しています。同社のマーケティング戦略において、イベントマーケティングは商談創出の中核を担う施策であり、インバウンド施策と組み合わせて「面」の最大化を図ってきました。
しかし、ウェビナーやカンファレンスの開催数が増えるにつれ、データ管理の煩雑さやアプローチ優先度の判別の難しさが課題となり、マーケティングと営業連携の精度を向上させるために、イベントマーケティングプラットフォーム「EventHub」の導入を決定しました。
【戦略・課題】
カオナビでは、新規リード獲得から商談化までをマーケティング部門とアカウント部門が連携して推進していますが、以下のような課題が存在していました。
- 数百名が参加するウェビナーにおいて、優先的にアプローチすべきリードを特定できない
- Googleフォームを利用したアンケート運用では回答率が低く、リードのスコアリングが困難
- ウェビナー開催数の増加に伴い、手作業によるデータ突合に時間と工数がかかり、ミスのリスクも高い
- オフラインカンファレンス開催時には受付業務の属人化や当日の運営負荷が高く、対応が煩雑
特に、マーケティングから営業部門(インサイドセールス)への引き渡しプロセスにおけるデータ整備やアプローチ優先順位付けが大きな課題となっており、可視化と効率化が求められていました。
【取り組み・EventHub活用】
EventHubの導入により、以下のような活用が実現しました。
- Marketo・Salesforceとのノーコード連携
マーケティングオートメーション(MA)とCRMを連携させることで、参加者情報・アンケート結果・行動ログが自動で反映。従来5時間かかっていたデータ突合作業が1時間程度に短縮され、人的ミスのリスクも軽減されました。 - アンケートポップアップによる回答促進
ウェビナー中に継続的にアンケートの表示を行うことで、回答率が向上。得られた情報をもとにインサイドセールス(IS)がHOTリードを優先的にフォローできるようになりました。 - Slack通知によるリアルタイム把握
オフラインカンファレンスでは、参加者のチェックインをSlackで通知。営業担当者は「今、誰が来場しているか」を即時把握でき、適切なタイミングで対応・紹介が可能になりました。 - 受付業務の外部委託による運営負荷軽減
カンファレンス「FACE to FES」では、受付業務をEventHubに一任。これにより当日のトラブル対応や準備工数が削減され、企画や顧客対応に集中できる環境が整いました。
【成果】
- 総商談の約40%をイベントマーケティング経由で創出。イベント施策が商談パイプライン形成の要となっています。
- アンケート回答率が改善し、ISによるアプローチ優先度が明確に。より確度の高い商談化が可能に。
- Marketo×Salesforce連携による突合作業時間が5時間→1時間に短縮。業務効率と正確性を両立。
- ウェビナーやカンファレンス開催の生産性向上により、社内体制を大きく変えることなく、開催本数やフォロー精度を向上。
- FACE to FESでは受付~フォローまでの一連の運用をスムーズに実施し、参加者同士・主催社との自然な交流機会を創出。
EventHubの導入によって、イベント施策全体の戦略設計・運用・データ活用のレベルが一段上がり、マーケティングと営業の一体運用が高精度で実現しました。今後も、さらなるスピード感と再現性をもって、新規事業の拡大や顧客とのエンゲージメント強化に取り組んでいく方針です。
カオナビ|セールス連携強化
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社カオナビの導入事例]でご確認ください。

株式会社Speee|Account Engagement連携で月間開催数1.5倍
【導入の目的】
株式会社Speeeでは、従来のアウトバウンドを中心とした営業スタイルを採用していましたが、コロナ禍により対面での営業活動が困難となりました。そこで、新たな集客手段としてオンライン施策の導入を検討し始め、最も効果を発揮したのが「ウェビナー」でした。
ウェビナーの開催数が増加する中で、Zoomでは限界が見え始めたことから、工数削減・自動化・データ連携が可能なツールの導入を目的にEventHubの採用を決定しました。
【戦略・課題】
Speeeが取り扱うサービスは、SEO・CVR改善・MA活用支援からDXコンサルティングまで多岐に渡り、一つ一つのサービスについて丁寧に伝える必要があるため、テキストベースでは不十分でした。
その中で、尺を気にせず詳細を伝えられるウェビナーは、同社の商材と非常に相性が良く、効果的な訴求手段となりました。
一方で、Zoomを使ったウェビナーでは次のような課題が顕在化していました。
- 開催時は担当者が常時張り付きで運用負荷が高い
- 応募者が800名を超えた際に配信品質(画面のカクつき)に課題
- リード管理・アンケート対応などの作業に人的リソースが限界
- ウェビナー後のインサイドセールス部門へのデータ受け渡しに工数が発生
これらの状況を踏まえ、「自動化と拡張性の両立」が急務となり、機能要件を満たすEventHubの導入が本格的に検討されました。
【取り組み・EventHub活用】
EventHub導入により、ウェビナー運営にかかる工数削減と質の向上を両立した取り組みを実施しています。
- 擬似ライブ機能を活用し、録画済みコンテンツを自動配信
担当者の張り付きが不要となり、心理的・物理的な負担を大幅軽減 - 自動アンケート送信とログ取得により、フォロー業務の省力化を実現
ウェビナー中にアンケートを自動で表示することで、回収率も改善 - Account Engagement/Salesforceとのノーコード連携
登録情報・視聴データ・アンケート結果がリアルタイムで一元管理され、インサイドセールス(IS)へのデータ共有がスムーズに - 手厚いサポート体制
API設定や画面操作に不明点があった際も、カスタマーサクセス担当者から迅速なサポートを受け、1日未満で連携完了
これにより、Zoom時代に発生していた複雑な突合作業が不要となり、スムーズかつ正確なデータ活用が可能となりました。
【成果】
- 月間ウェビナー開催数が10回→15回に増加(約1.5倍)
午前枠の活用や擬似ライブによって開催可能な時間帯・頻度が拡大 - 配信業務・アンケート対応の自動化により、担当者の稼働時間を大幅削減
メール送信・チャット対応・再生操作などの業務が自動化され、1開催あたりの運用時間が10時間以上短縮 - Salesforceとのリアルタイム連携でデータ突合の手作業がゼロに
マーケティング部門からIS部門への連携がスムーズに。リード活用のスピードと精度が向上 - 視聴ログ・アンケートデータの可視化によりリードの質が明確化
HOTリードの発見が迅速になり、営業アプローチの最適化が可能に
EventHub導入によって、同社はウェビナーの拡大と運用負荷の軽減を両立し、マーケティング部門がより戦略的な業務に時間を投下できるようになりました。今後は、自社ウェビナーのさらなる精緻化と、新たなコンテンツ設計を通じて、見込み顧客の獲得と育成を強化していく方針です。
Speee|Account Engagement連携
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社Speeeの導入事例]でご確認ください。

ウェビナー事例 分類③|面談・商談創出最適化型(ウェビナー→個別対応)
野村不動産株式会社|個別面談への遷移率50%を実現
【導入の目的】
野村不動産株式会社は、分譲マンションブランド「プラウド」シリーズを展開する中で、コロナ禍を契機にオンラインでの顧客接点拡大に着手。個別面談中心だった営業スタイルから、より多くの見込み顧客にリーチする手段としてウェビナーを活用し、住まい探しのオンライン総合窓口「プラウドオンラインサロン」の運営を開始しました。
しかし、従来のZoom配信ではウェビナー参加から個別面談への転換が進まず、KPIである面談化率の改善が大きな課題となっていました。そこで、個別対応へのスムーズな導線整備と配信品質の向上を実現するため、EventHubを導入しました。
【戦略・課題】
オンラインによる集客は一定の成果を上げていたものの、次のような問題が顕在化していました。
- ウェビナー後に個別面談へ進む参加者が少ない
- URL遷移や別画面での予約フォームなど、個別面談への導線が分かりづらく離脱が多発
- Zoomによる配信では画質・資料表示の不鮮明さが顧客満足度を下げる要因に
- 手動でのリマインドやフォローアップ、事務作業の工数が大きな負担
「まずは参加してもらいやすいウェビナー→個別面談へ」という一連の流れを確立し、営業成果につなげる仕組み化と工数削減の両立が求められていました。
【取り組み・EventHub活用】
EventHubの導入により、以下のような改善が実現しました。
- 個別面談へのシームレスな導線
– ウェビナー内のチャットやメッセージ機能から、URL遷移なしでそのまま個別面談に接続可能。
– 個別面談への心理的・操作的ハードルを排除し、遷移率が向上 - 高解像度な配信環境の実現
– 画像やフォントの視認性が高く、資料や物件紹介の説明がクリアに伝わるようになり、顧客満足度が改善。 - EventHub上でのメール配信・リマインド対応
– 参加登録・予約者への自動メール送信や、お礼メールも全てプラットフォーム内で完結。
– リスト抽出や外部ツール不要で、運営の手間を大幅削減 - 擬似ライブ・複製機能の活用
– 録画済みコンテンツを活用し、複数回同内容の配信を実施可能。準備負荷を抑えながら、3日間で9回の配信体制を実現。 - 安心して使えるチャット設計とサポート体制
– 個別チャットが他参加者と混在せず、事故のリスクが排除され、一人ひとりに丁寧な対応が可能に。
– また、EventHubのカスタマーサポートから初期導入や運用中の手厚い支援を受け、導入後すぐに安定運用が実現。
【成果】
- 個別面談遷移率50%を達成(目標は30%)
– 多くのウェビナーで目標を大きく上回る結果に。KPI達成率が飛躍的に向上。
– 2024年1月・3月は高水準を維持し、効果が継続。 - 3ヶ月で200件以上のウェビナー参加/98件の個別面談を創出
– 土曜日1日で100名の参加があるなど、高反響の企画運営が可能に。 - 配信・フォロー業務の工数削減
– メール・配信管理・資料共有などの作業をEventHubに集約。手動対応を大幅に削減し、精神的な負担も軽減 - 少人数体制でも高頻度開催が可能に
– 約5~6名の運営メンバーで1テーマ・3日間・9回の配信を実施し、高品質な運営体制を確立。
EventHubの導入によって、野村不動産では「ウェビナーから個別面談へ」という自然な流れを構築し、オンライン営業成果の最大化に成功しました。今後も、テーマごとの設計と運用体制をさらに強化し、より多くの見込み顧客との接点創出と、事業成果への貢献を目指していきます。
野村不動産|面談遷移率50%
→ さらに詳しい運用設計と数値は[野村不動産株式会社の導入事例]でご確認ください。

REHATCH株式会社|商談化率1.15〜1.2倍、ウェビナー経由の大型受注増
【導入の目的】
REHATCH株式会社は、WEBマーケティング支援やAI×マーケティングのプラットフォームを提供する中で、ウェビナーをリード獲得・商談創出の起点とする戦略を推進してきました。しかし従来のツールでは、参加率やアンケート回収率が伸び悩み、Salesforceとの連携やオフラインイベント対応の非効率さも課題となっていました。
これらの課題を解決し、より戦略的にウェビナーを活用する体制を構築するために、EventHubを導入しました。
【戦略・課題】
REHATCHでは以前から、ウェビナーの開催自体は推進していましたが、商談化や大型受注へのつながりが弱く、成果が頭打ちの状態にありました。特に以下の点が課題でした。
- ウェビナー参加率が5〜6割程度に留まり、集客効率が非効率
- アンケート回答率が50%未満で、参加者の関心を把握しきれない
- 商談化や受注につながる導線が不明確
- オフラインで得たリードの手動データ化による工数増大
- ウェビナーに関する情報(申込・参加・回答)のSalesforce連携が煩雑
これらの課題をクリアするために、ファネル設計をもとにしたウェビナー構成と、システムによる自動化・可視化の実現が急務でした。
【取り組み・EventHub活用】
REHATCHではEventHub導入後、ウェビナー戦略と運用を以下のように再構築しました。
- 3層構造のファネル戦略を設計
1. TOP〜Middleファネル向けのオンラインカンファレンス
2. 共催ウェビナーによる理解促進
3. ニーズ別に絞った自社単独ウェビナー
– 各ウェビナーに明確な目的を設定し、段階的に商談へつなげる設計を構築 - Salesforceとの自動連携でデータ一元化
– 申込・参加・アンケート結果がリアルタイムで反映され、営業チームとの連携がスムーズに - EventHub Lead Scanの活用によるオフライン効率化
– 展示会での名刺情報をその場でスキャン・メモ付きでデータ化
– 後から商談優先度の高いリードの可視化と抽出が可能に - アンケート表示や配信設計の最適化で情報取得率が改善
– ウェビナー参加者の関心や検討度を可視化し、より精度の高いフォローアップが可能 - 開催数の増加と効率的な運用体制を実現
– 従来の4倍の開催数でも同等の工数で運営が可能に
このように、EventHubを基盤にした戦略的な設計・運用によって、ウェビナーを「単発のイベント」から「商談の起点」へと位置づけ直しました。
【成果】
- ウェビナー開催数が約4倍に増加
– 運用効率化により、同じリソースで多頻度開催が可能に - 参加率が最大1.2倍に向上
– ターゲット層との接点数が増加し、見込み顧客の層が広がる - アンケート回答率が50〜60%に改善
– 質の高いインサイトを獲得し、精度の高い営業活動へと連動 - 商談化率が1.15〜1.2倍に向上
– ウェビナーが「受注起点」としての役割を強化
– 特に複数回参加者からの受注が増加傾向 - 展示会での600件の名刺情報から約20件の商談創出
– EventHub Lead Scanによる迅速かつ質の高いリード活用が実現
REHATCHでは現在、ウェビナーがアポイント獲得の主力チャネルとなり、四半期で数件程度だった商談創出が全体の5〜6割を占めるまでに成長しています。今後も、ファネル設計を軸に、コンテンツ精度と連携体制を強化し、商談化・受注の最大化を目指していきます。
REHATCH|商談化率向上
→ さらに詳しい運用設計と数値は[REHATCH株式会社の導入事例]でご確認ください。

ウェビナー事例 分類④|リーチ最大化型(共催・複数日程・アーカイブ)
株式会社OPTEMO|ハウスリードが少数でも“毎週開催”で一気に拡張
【導入の目的】
株式会社OPTEMOでは、自社プロダクト『OPTEMO』の認知拡大と商談創出を目的に、2024年よりウェビナー施策を本格始動しました。当時はハウスリードが数百件しかなく、集客力や商談化の導線に課題を抱えており、少人数体制でも高頻度で成果につなげられる柔軟なウェビナー運営の仕組みが求められていました。
その中で、手間をかけずに複数日程開催や自動化が可能で、HubSpot連携にも対応したEventHubの導入を決定しました。
【戦略・課題】
マーケティングを専任1名で推進する中、以下のような課題に直面していました。
- ハウスリードが少なく、ウェビナーの初回参加者は数名程度
- 毎週の開催や多様な日程対応が必要だったが、運用工数が大きな負担に
- 参加機会を広げるためのアーカイブ配信やリマインド施策の整備が不十分
- 多くの施策を1人で運用する中で、メール配信・日程管理・社内連携に限界
これらを乗り越えるために、共催ウェビナーの仕組み化・自動化・多日程対応・アーカイブ拡充といった機能面が必須でした。
【取り組み・EventHub活用】
OPTEMOでは、EventHubの各種機能をフル活用し、少人数体制でも高頻度で質の高いウェビナー運営を実現しました。
- 共催ウェビナーと単独ウェビナーを明確に分けて運用
– 共催ウェビナー:新規リード獲得が目的
– 単独ウェビナー:サービス理解促進・商談前提の導線強化 - HubSpotとの連携による複数日程開催の効率化
– 1つの申込ページで複数日程を選択可能にし、申込数を拡大
– 取得データはEventHubに自動連携され、リード管理が容易に - アーカイブ配信と自動リマインドで接点を強化
– メルマガで「日程が合わなくてもアーカイブ視聴可能」と訴求
– EventHubのサンクスメール・リマインドメールの自動送信により、運用負荷を大幅軽減 - Googleカレンダー連携による申込者のリマインド強化
– 申込時に予定が自動反映され、当日参加率の向上に寄与 - 社内連携による商談化率向上の工夫
– 質問やコメントに対して営業・インサイドセールスに即共有
– 顧客ニーズに即応する動きで、ウェビナーからの商談化を促進
【成果】
- ウェビナー参加者が数人から最大100人規模に成長
特に共催ウェビナーでの集客力が大きく向上し、新規リードの獲得効率が飛躍的に改善 - 毎週のウェビナー開催が常態化
「100人以下であれば月間開催無制限」の料金体系により、回数を気にせず柔軟に開催可能 - HubSpot連携×複数日程対応で申込機会を最大化
ユーザーは希望日を選んで参加できることで、参加率向上と継続的な関心喚起に成功 - マーケティング専任1名でも多チャネル施策を安定運用
EventHubの自動化機能により、ウェビナーだけでなくオフラインイベント(インサイドセールス研究会)とも連携 - 社内連携によるリアルタイムな営業支援
ウェビナー参加者からの問い合わせを即座に関連部門へ共有し、受注への好循環を形成
OPTEMOは、少人数かつ限られたハウスリードという状況から、EventHubを活用して“毎週ウェビナー開催”という高頻度運用を実現し、事業成長の加速に繋げています。今後も、HubSpotとの連携やアーカイブ施策のさらなる活用を通じて、商談化率の最大化とブランド認知の向上を目指していきます。
OPTEMO|リーチ最大化
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社OPTEMOの導入事例]でご確認ください。

MNTSQ株式会社|3週間で自社ウェビナー立ち上げ、参加率52%→80%超
【導入の目的】
これまで法律事務所と共催で実施していたウェビナーでは、参加者の行動データの取得や運営の自由度に限界があり、自社主導でのウェビナー開催が必要とされていました。自社プロダクトの認知拡大・リード獲得・商談機会創出を目的に、限られた準備期間でもスムーズに開催できるウェビナープラットフォームとして、EventHubの導入を決定しました。
【戦略・課題】
自社でのウェビナー立ち上げに際し、MNTSQでは以下のような課題を抱えていました。
- 共催イベントでは参加者の詳細な動向把握や施策改善が困難
- ウェビナー開催経験がなく、短期間での準備が必要(わずか3週間)
- 初めての主催にあたり、費用を抑えつつ、運営の自由度と信頼性が求められた
- 法務・契約関連という難解なテーマを、分かりやすく丁寧に伝える手段が必要
【取り組み・EventHub活用】
MNTSQではEventHubを活用し、初めての自社ウェビナーを短期間で立ち上げ、継続的に改善を重ねる体制を構築しました。
- 3週間の準備期間でウェビナー構築からアーカイブ配信までを実現
– UIが直感的で使いやすく、チュートリアルやQ&Aも充実
– 告知ページ・チケット作成・アンケート・リマインドメールなど、全てをEventHub内で完結 - 自社でのウェビナー開催に必要な機能を網羅
– Googleカレンダー連携で参加者の申込み忘れを防止
– アンケート機能や属性データ収集により、参加者分析と施策改善が可能に - 社内誰でも運営できる環境を整備し、開催頻度が向上
– UIの分かりやすさにより、専任担当者でなくても実施が可能
– 開催数が増加し、分析と改善のサイクルが加速 - 定期開催によるナーチャリング施策としても活用
– 専門性の高いサービス内容を「言葉で丁寧に伝える」ことで、潜在層のニーズを顕在化
【成果】
- ウェビナー参加率が52%から80%超えへと大幅向上
カレンダー連携やメールテンプレートの活用が、参加忘れの防止に貢献 - アンケート回答率が25%から30%へ改善
属性データに基づいた内容の最適化と、お礼メール+アンケート導線の工夫が奏功 - 開催回数・データ分析機会の増加により、全社でマーケティング活動の底上げを実現
「どのテーマに何人集まったか」「誰が参加したか」など、イベントを起点とした施策立案が可能に - EventHubの導入により、1つのプラットフォームで運営全体が完結
撮影・配信・アンケート・フォローまでがワンストップで実行でき、人的リソースの制約もカバー
MNTSQでは、自社独自の情報発信とリード獲得の手段としてウェビナーを活用し、「理解が難しいサービスこそウェビナーが最適」という実感を得ながら、顧客との接点を深めています。今後も、定期的な情報提供と顧客ナーチャリングの場として、ウェビナーを軸に据えたマーケティング活動を継続していく方針です。
MNTSQ|短期立ち上げ×参加率向上
→ さらに詳しい運用設計と数値は[MNTSQ株式会社の導入事例]でご確認ください。

ウェビナー事例 分類⑤|ハイブリッド活用型(オンライン×オフライン連携)
NECネッツエスアイ株式会社|Zoom連携×マルチトラックで多様な体験を一元化
【導入の目的】
NECネッツエスアイでは、営業活動の高度化と共創型ビジネスの推進を目的に、イベントプロモーションを通じた顧客接点の強化に取り組んでいます。コロナ禍でのウェビナー開始以降、Zoomを軸としたイベント施策が一定の成果をあげたことから、より多様な形式に対応可能で、顧客体験を一元化できるイベント基盤の必要性を感じ、Zoom連携に強みを持つEventHubの導入に至りました。
【戦略・課題】
営業支援部門であるビジネスプロセスイノベーション推進本部では、注力事業の認知向上・新規顧客の発掘・共創パートナーとの接点構築を目的に、柔軟なイベント戦略を展開していましたが、以下のような課題が存在していました。
- イベント目的や顧客層に応じた最適な手法(オンライン/オフライン)を柔軟に選択したい
- マルチトラックやプライベートイベントなど多様なイベント形態を企画したい
- 動画視聴・質問投稿・資料ダウンロードに複数ツールが必要で、顧客体験が分断されていた
- 出席者情報の正確な把握や視聴履歴の取得が困難で、フォロー活動に課題があった
【取り組み・EventHub活用】
NECネッツエスアイでは、EventHubを通じてオンライン・オフライン問わず柔軟なイベント施策を展開し、営業活動の効率化と新たな顧客接点の創出に成功しています。
- Zoomとの親和性を活かし、従来の運用を維持しながら機能を拡張
– 既存のZoomベースの配信をEventHubと連携することで、マルチトラック構成や疑似ライブ配信を実現 - 22本の収録動画を3週間で配信する大規模イベントを開催
– 1セッション20〜30分に設計し、業務の合間に視聴しやすい構成に
– 擬似配信形式を採用することで、運営工数を抑えつつ集客は従来の約3倍に増加 - イベントマイページで顧客体験を一元化
– 質問投稿、簡易アンケート、資料ダウンロードなどを単一画面で完結
– slidoの表示もEventHub内で行い、ツール切替の煩雑さを解消 - 個別の視聴履歴の取得が可能に
– 各参加者の行動をマイページ単位で確認可能となり、イベント後のフォロー精度が向上 - オフラインイベントの来場管理にも対応
– イベントの目的に応じて、オンライン/オフラインを柔軟に選択し、効率的な人脈形成・商談化を促進
【成果】
- Zoom単体では実現困難だったマルチトラックイベントを開催可能に
顧客ニーズに合わせた多様なセッション構成で、参加満足度と理解度を向上 - 顧客体験の一元化により、視聴率と参加者満足度が向上
アプリの切替不要、コンテンツ集中型のUX設計で参加継続率も改善 - 集客数が約3倍に増加
擬似配信やコンパクトなセッション設計により、新規顧客層へのリーチを拡大 - イベント後のフォロー精度が向上し、営業アプローチが効率化
正確な参加者データ取得により、見込み顧客への優先順位付けが容易に - Zoomとの高い親和性とコストバランスで社内導入がスムーズに進行
既存ツールを活かしつつ、拡張性とユーザビリティの両立を実現
NECネッツエスアイでは、オンライン×オフラインのハイブリッド型施策をEventHubで一元管理し、多様化する顧客ニーズに即したマーケティング戦略を展開しています。今後も、目的に応じた柔軟なプロモーション施策を通じて、新たな商談機会と共創パートナーの獲得を目指しています。
NECネッツエスアイ|ハイブリッド一元化
→ さらに詳しい運用設計と数値は[NECネッツエスアイ株式会社の導入事例]でご確認ください。

株式会社リンクス|「LINX DAYS」×製品別ウェビナーを同一基盤で運営
【導入の目的】
20年にわたり開催してきた大型カンファレンス「LINX DAYS」をオンライン・オフラインの両形式でスムーズに運営しながら、既存顧客とのエンゲージメント強化と新規顧客のナーチャリング強化の両立を目指すにあたり、イベント基盤の一本化と省力化、スムーズな入場管理や参加者対応が課題でした。加えて、コロナ禍を経て開始した製品別ウェビナーも、マーケティング施策の一環として戦略的に運用していく必要がありました。
【戦略・課題】
- 既存顧客との継続的な関係性構築とブランドイメージの強化
- 新規顧客の開拓および育成に向けたタッチポイントの拡大
- オフラインイベントにおける入場管理の混雑・機材対応の煩雑さ
- 限られたマーケティング人員の中で多拠点・複数部門のイベントを効率的に運営する仕組みの整備
- ウェビナー・カンファレンスを一元管理し、顧客との接点をつなぐ導線設計
【取り組み・EventHub活用】
株式会社リンクスでは、EventHubを通じて大型カンファレンスと小規模ウェビナーを同一プラットフォーム上で管理・運用する体制を構築しました。
- LINX DAYSにおけるオフライン入場管理のスムーズ化
– QRコードチェックインによる受付対応で、従来の長蛇の列が解消
– スマートフォンと小型機材だけで対応可能となり、設営スペースも削減 - オンライン開催ではメッセージ機能や資料共有機能を活用
– 担当者との直接やり取りが可能となり、参加者満足度の向上に寄与 - ウェビナーとカンファレンスの一体運営
– EventHubは500名以下であれば追加費用がかからない料金体系で、小規模ウェビナーの導入ハードルが低い
– 製品別ウェビナーを各事業部が自発的に運営し、部門主導でのリード獲得が可能に
– UIの分かりやすさにより、初めてでもマニュアルなしで運用ができる - タッチポイントを横断したナーチャリング施策の実践
– ウェビナー経由で新規リードを獲得し、カンファレンスへ誘導
– メルマガ「LINX Express」など他チャネルとの連携でリード育成を加速
【成果】
- オフラインイベントでの受付待機列が解消され、スムーズな入場管理を実現
– 最大来場者数を記録したにもかかわらず、従来より効率的なオペレーションが実現 - オンライン・オフライン両軸でのイベント運営を一本化し、運用負荷を削減
– LINX DAYSとウェビナー双方の管理をEventHubに集約し、運営・集客・分析の効率化を実現 - 部門単位でのウェビナー開催が定着し、1回で700名集客するケースも
– 社内では「UIが使いやすく、誰でも自走できる」という声も多数 - 新規顧客の獲得にも波及効果
– 製品ウェビナーに参加した新規顧客を、カンファレンスへ案内する導線が確立
– 各チャネルをまたぐ“スパイラル型”の顧客育成が回り始めている
株式会社リンクスでは、EventHubを通じて新規・既存顧客を繋ぐイベントマーケティングの基盤を確立しました。今後もオンライン・オフラインを問わず、多様な接点を活かした顧客ナーチャリング戦略を強化していく方針です。
リンクス|大型カンファレンス×製品別ウェビナー
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社リンクスの導入事例]でご確認ください。

ウェビナー事例 分類⑥|運用効率化・標準化型(属人化解消・省力化)
株式会社マツリカ|準備・当日工数75%削減、成果最大化で商談数も増加
【導入の目的】
中堅〜大手企業向けのアプローチを強化する中で、ウェビナーを商談化に直結させる重要な施策と位置づけていたマツリカ。
運用の属人化や開催タイミングの制約、そして煩雑な準備・当日の作業工数を見直し、成果を最大化できる体制を整えることが主な目的でした。
- 担当者の負担が大きく、最適なタイミングでの開催が困難
- 毎回の設定作業に時間を要し、リソースの圧迫が課題に
- 属人化から脱却し、誰でも運用できる環境づくりを目指した
【戦略・課題】
マーケティング施策として展示会出展を起点に、中堅〜大手企業へのアプローチを進める中で、セミナー・ウェビナーは既存リストのナーチャリングに活用。
しかし、以下のような運用課題が戦略遂行の障壁となっていました。
- アーカイブ配信にも関わらず、1回あたり2名体制・1時間半の当日対応が必要
- Zoom、Googleフォーム、MA、スプレッドシートなど、複数ツールの連携で設定ミスが発生
- 担当者不在時に開催できないなど、施策の柔軟性が欠如
【取り組み・EventHub活用】
属人化の解消と工数削減を目的にEventHubを導入。操作の簡易性やセキュリティ面の信頼性、オフライン対応なども評価され、導入が決定しました。
主な取り組みは以下の通りです。
- イベント作成後の設定が自動化され、準備工数は120分→50分に短縮
- アーカイブ配信も自動化され、当日対応時間は90分→30分に
- ノーコード連携でスプレッドシートやMAへの情報反映を自動化
- カレンダー連携・ポップアップ表示・リマインドメール送信による参加促進
- セミナー視聴後、アンケート未回答者へ自動でリマインド送信を実施
【成果】
EventHub導入により、運用の負担が大幅に軽減されただけでなく、成果面でも高い改善が見られました。
- 準備・当日工数を合計で75%削減
- 参加率:53%→73%、アンケート回答率:47%→65%へ向上
- MQLの増加・商談数の増加にも貢献
- 施策のタイミング最適化により、集客効率とコンバージョン率も改善
工数削減・標準化による運用のスムーズ化と、成果の最大化を両立したマツリカの取り組みは、限られたリソースでも効果を最大限に引き出せる成功事例といえます。
マツリカ|属人化解消×75%工数削減
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社マツリカの導入事例]でご確認ください。

株式会社PKSHA Communication|工数大幅削減で開催数“約2倍”と質の両立
【導入の目的】
新規・既存顧客双方とのタッチポイントを増やしながら、属人的な運営体制を改善し、セミナー開催の標準化・効率化を実現するため、運用負荷の軽減と工数削減を目指してオンラインセミナーのプラットフォームを見直す必要がありました。従来のZoom運用では限界があり、セミナー数の増加や品質向上を阻んでいました。
【戦略・課題】
- 指名検索以外の潜在顧客への認知拡大とリード獲得
- オンラインセミナーにかかる運用負荷の大きさと属人化の解消
- 手動での予約受付・リマインドメール送信などがボトルネック
- データの取得・分析に時間がかかり、施策改善が難航
- セミナー開催数を増やしたいが、リソース的に実現困難
【取り組み・EventHub活用】
セミナー運営の工数削減と標準化を実現するために、EventHubを導入し、以下のような施策を展開しました。
- 自動化機能の活用による属人化の解消
– 予約受付・リマインド・フォローメール送信を自動化し、担当者の業務負担を大幅に軽減
– 担当者が「絶対に当日出社しなければいけない」状態を解消 - セミナーとメール・配信機能の統合運用
– イベントページ作成、申込受付、動画配信、メール送信を一元化
– UI上で視聴数・申込数の傾向を可視化し、リアルタイムで集客状況の把握と改善が可能に - 綺麗なデータ取得で分析と連携もスムーズに
– MAツールへのスムーズなデータ連携が可能になり、リード活用効率が向上 - セミナー準備の省力化により“企画”への注力が可能に
– 浮いた時間を活用し、顧客ニーズに合わせた内容企画に注力
– 結果として質の高いセミナーを安定的に提供
【成果】
- セミナー開催数が約2倍に増加
– Zoomで運営していた頃と比べて開催数がほぼ倍増
– 「週1回の新規向けセミナー」「月7回の既存向けトレーニング」を安定運用 - 企画・設計に注力でき、質と回数の両立を実現
– アンケート回答率や参加率はほとんど変動せず、質の維持に成功
– 顧客のニーズに即した内容を継続的に企画できる体制へ移行 - お客様との接点が増加し、リード創出にも寄与
– セミナーを通じて潜在層へのアプローチが強化され、商談数も増加
– オンボーディング以降の接点が増え、LTV最大化に貢献 - 社内リソースの最適化とチーム間連携の強化
– マーケティングとカスタマーサクセスが協力し、共通基盤でセミナーを実施
– 属人化を解消し、誰でも開催できる体制を実現
PKSHA Communicationは、EventHub導入によりセミナー運営を“人頼み”から“仕組み化”へ転換。運営負荷を抑えつつ、接点数の最大化とセミナー品質の両立を実現しています。今後はアーカイブ配信の強化なども視野に入れ、さらなる運用最適化を図っていく方針です。
PKSHA Communication|運用標準化
→ さらに詳しい運用設計と数値は[株式会社PKSHA Communicationの導入事例]でご確認ください。

ジャフコ グループ株式会社|アンケ回答率30%アップ、運営工数48%削減
【導入の目的】
投資先スタートアップとのマッチング創出を目的としたセミナーを、継続的かつ効率的に運用する仕組みの構築を必要としていました。属人化・煩雑化していたセミナー運営の全工程を一元化し、業務効率化・開催回数の拡大を実現するためにEventHubの導入を決めました。
【戦略・課題】
- 投資先企業のリード提供やマッチング創出のため、セミナー開催数を増やしたい
- ZoomやGoogle Formなど複数ツールによる煩雑な作業工程が大きな負担
- LP作成、集客、申込管理、配信、アンケート、データ突合…と作業が分断されていた
- 複数ツール運用による属人化が進行し、他メンバーへの業務移管が困難
- 工数過多により、本来注力すべきセミナー企画や改善に時間を割けない
【取り組み・EventHub活用】
ツールの一元化によって、セミナー運営の全工程を一括管理できる体制を整備。以下のような具体的な改善を実施。
- セミナー運営に必要な作業をすべてEventHub上で完結
– LP作成、申込受付、リマインド・フォローメール送信、アンケート、データ分析を一元管理
– 多機能なUIと直感的な操作性により、新たな担当者でも簡単に運用可能に - 工数削減と同時に属人化も解消
– 複数ツールの使い方を教える必要がなくなり、業務の引き継ぎがスムーズに
– 「担当者1人しか対応できない」状態から脱却し、チームでの運用体制へ移行 - セミナー設計・改善へ注力できる時間を創出
– データ突合などの煩雑な作業が不要になり、本質的な内容改善や効果測定が可能に
【成果】
- セミナー運営の総工数を48%削減
– 特に手間のかかっていたデータ突合業務は、97%削減(30→1)
– セミナー当日の午後には、即アプローチ可能な体制に - 属人化から脱却し、業務の分担・共有が可能に
– EventHub一つを教えれば誰でも運用できるようになり、運営体制が安定化 - アンケート回収率が30%向上
– 手間が省けたことで、内容や設問設計に注力できた結果、回収率が大幅に向上 - セミナー開催回数の安定化と拡大
– 従来はまちまちだった開催ペースが、月8〜9回の定期開催に
– 投資先と大企業のマッチング創出機会が増加し、活動効果が向上
ジャフコ グループでは、煩雑だったセミナー運営をEventHubで一本化することで、生産性と成果の両立を実現しました。
今後は、企画・内容面に一層注力しながら、投資先の支援と新たな事業機会の創出を加速していく方針です。
ジャフコ グループ|省力化×回収率アップ
→ さらに詳しい運用設計と数値は[ジャフコ グループ株式会社の導入事例]でご確認ください。

まとめ:成功事例に共通する“勝ち筋”
これまで紹介してきた各社のウェビナー活用事例から見えてきたのは、目的に応じて施策を柔軟に設計し、ツールを活用しながら運営体制と成果の両立を実現しているという共通点です。以下に、各社が成功に至ったポイントを整理します。
- 明確な目的設計とターゲット設定
各社は「リード獲得」「商談化」「既存顧客のアップセル」「ブランディング」など、目的を明確に定めた上で、コンテンツや共催パートナー、アプローチ手法を設計。さらに、新規・既存顧客を正確に分類し、フェーズごとに適したウェビナーを企画している。 - 属人化の解消と再現性ある運営体制の構築
誰が担当しても安定して運用できるよう、プロセスとツールを整備。EventHubの活用により、申込・配信・アンケート・データ活用までを一元管理し、少人数でも継続的に運営可能な体制を実現している。 - 効果検証と改善サイクルの徹底
参加率、アンケート回答率、商談化率などの指標を明確にし、開催後の振り返りと改善を継続。参加者属性の分析やアンケート設計の工夫を通じて、成果につながるPDCAを確立している。 - マルチチャネル・連動型のリードナーチャリング
ウェビナー単体に依存せず、展示会やメルマガ、オフラインイベントと連携し、顧客接点を多層的に設計。EventHubを基盤にすることで、タッチポイントの拡張と一貫したナーチャリング施策を可能にしている。 - 工数削減で“質と量”の両立を実現
リマインドメール、アンケート回収、アーカイブ配信などの自動化を活用し、担当者の工数を大幅に削減。その分、内容のブラッシュアップに集中でき、開催頻度とコンテンツ品質の両立を実現している。
成功の秘訣は「継続できる運用設計」と「マーケティング戦略との連動」
ウェビナーは単発の施策ではなく、中長期的な成果を出すための戦略的チャネルとして活用することが重要です。
運営の負担を軽減しながら継続的に開催できる仕組みを整え、事業・営業・マーケティングと連携したウェビナー施策の設計が、成果に繋がる鍵となります。
EventHubを活用することで、こうした体制構築や運用最適化が可能となり、再現性ある成功パターンを自社内に蓄積していくことができるでしょう。